「勉強ができるようになってほしい」
子供を持つ親なら願うことだろう。しかし、長年脳の研究に従事し、これまで1万人以上の脳を診断してきた小児科専門医の加藤俊徳さんによれば、「勉強は脳を働かせるための要素にしか過ぎない」とのこと。
大切なのは脳をどう使うか、それ次第で勉強や将来に役立つ力も養われていくという。
加藤さんの著書『成績が上がる!10歳からの脳タイプ別勉強法』(世界文化社)では、「自分の脳が得意なことを知ることで、成績も上がり、なりたい自分に近づける」と紹介している。
いったいどういうことだろう。加藤さん本人に聞いた。
子供にとっての勉強は脳と向き合うこと
――著書では「勉強の第一歩は、頭が働いているか・いないかを自分でチェックすること」とあります。
まず脳の仕組みを知ることが、勉強ができる第一歩と私は考えています。学校では友達、上級生・下級生、先生など、さまざまな人と接し、授業で新しい情報をどんどん得ていきます。そのため、子供の脳は大人より成長しやすいのです。
ただ、学校のテストによって「算数の点数が低かった…。次はいい点を目指そう」と親や先生は考えがちです。それは私が考える「脳の成長」からするとちょっと違います。
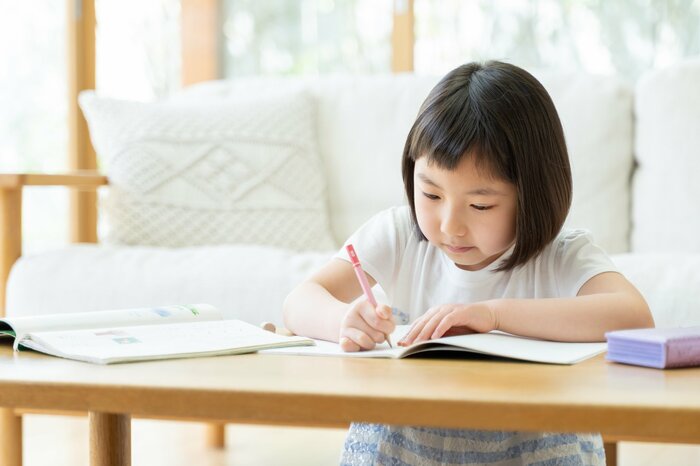
――どういうことでしょうか。
国語、算数、社会などの教科は脳にとって“成長するための要素”にしか過ぎないということです。「成績が上がったから脳が成長している」わけではなく、「脳が成長して成績が伸びる」のです。
脳は新しい情報が入ることで成長します。実は生まれた瞬間から「脳の得意」は存在し、脳に入ってくる情報を処理することで、能力が形成されていく。つまり、新しい情報を理解するために脳が発達していくのです。
勉強の場合もそれらの要素が脳にどんな影響を与えているのかを考える必要があり、“その子自身がどう成長していくか”が本質なのです。





