東日本大震災と福島第一原発事故の発生から間もなく14年となる。もっとも事故の被害が大きかった福島県の太平洋沿岸にある浜通り地域はいまどうなっているのか。第3回は浜通りに生まれた新たな教育のカタチを取材した。
浜通りに事実上大学のキャンパスができる
「この地域で1つ足りないのは教育だなと思っています」
元外交官で震災以降浜通りの浪江町に移住して様々な事業をしている高橋大就さんはこう語った。日本中のあらゆる地域で課題となるのが、高等教育機関が無いことだ。地元の若者がその地を離れ、子育て世代が移住を躊躇する大きな理由となっている。浜通りにより多くの人々を呼び込むため、オンラインによる高等教育機関との提携を進めている。
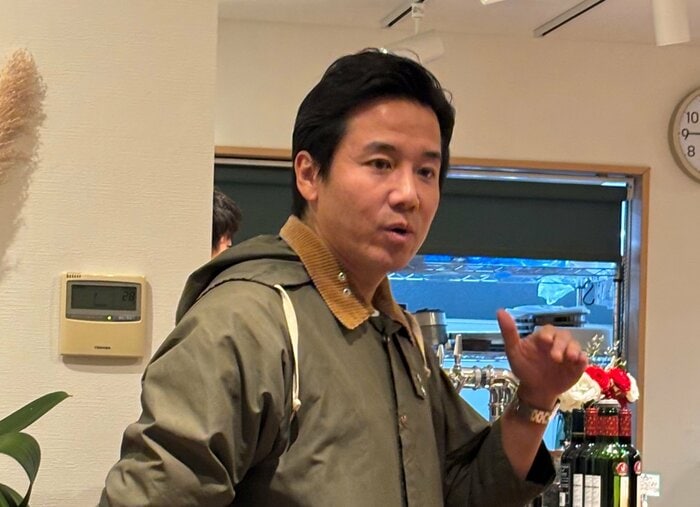
「浜通りには多くの方が集まって様々なチャレンジをしているので、学びの場としても素晴らしい状態にあると思っています。しかし高校の数は限られているので、昨年はオンライン最大のN高校と提携し、来月開校するオンラインのZEN大学とも組んで秋からフィールドプログラムをつくることになりました。そうすると事実上この地域に大学のキャンパスができることになります」(高橋さん)
浜通りにプロの「転校生」がやってきた
浜通りの富岡町では2017年に避難指示区域が解除され、2018年から町内で小中学校が再開した。その富岡小中学校ではいま「PinS(ぴんず)プロジェクト」という「教えない教育」の取り組みが行われている。
「PinS」とは「Professionals in School(プロフェッショナル転校生)」の略で、アーティストや建築家、音楽家などのクリエイティブな職種のプロたちが”転校生”としてやってきて、学校内で子どもたちと生活を共にしながら学びあうという取り組みだ。

この新たな学びの場をつくったのが、NPO法人インビジブルの山本曉甫さんたちだ。山本さんは東京生まれの東京育ちでこれまで現代美術を軸にした地域の活性化などに取り組んできた。
2018年の富岡小中学校再開の時に富岡町の教育委員会から「何か新しい学びの環境づくりができないか」との相談を受け、提案したのが「PinSプロジェクト」だった。
コミュニティの拠点となる学校づくり
山本さんは「学校再開の1年前から関わる中で、コミュニティの拠点となる学校づくりを提言していました」という。
「その一環としてプロフェッショナル転校生をスタートすることになったのです。芸術領域のプロの転校生と交流する中で、子どもたちが自分たちの中で何か新しい課題意識だったり、将来のビジョンを作って欲しいなと思っています」

2018年から始まったこのプロジェクトでは、これまで7人の転校生が参加した。2024年度は「空気の芸術」を創り上げているアーティストの三原聡一郎さんが転校してきて、子どもたちと交わっている。

「基本的には休み時間に三原さんがアート活動をする場所に子どもたちが遊びに来ます。授業に馴染めない子は授業中に来たりすることもあります。また三原さんも授業に出向いて一緒に体育や算数を学んだりしています。転校生は毎月1週間程度滞在してもらいます。大体1学期の6月ぐらいに転校生が決まり、8月ぐらいから年度終わりまでいて最終的に作品を1つ残してもらうかたちです」
子どもたちのマインドが切り替わる機会に
子どもたちの反応を聞くと、山本さんはこう続けた。
「アート自体に興味があって来る子どもたちはもちろんいますが、見ていると何となく何をやっているのか気になって子どもたちが集まる傾向はどの学年でもあります。また、学校には行きたくないけれど、アーティストが来るときだけは行ってみようという子どもたちもいて、そういう受け皿にもなっていますね」

「PinS」プロジェクトの次なる展開について山本さんは「コロナがなければ2020年くらいから転校生だけでなく留学生というプログラムをやろうとしていた」と語る。
「海外のアーティストが学校の中で活動すると、外国語に触れるだけでなくもの作りをしている人を通して子どもたちが海外を体感し、いまの自分たちの場所や生活を相対化、見える化できて、子どもたちのマインドが切り替わる機会にできたらいいと思っています」
未来の環境づくりを自由研究する秘密基地
「日本一美しい村」と呼ばれる福島県飯舘村は、原発事故により風に乗った放射性物質が山を越えて飛来し、全村民約6000人が避難を余儀なくされた。2017年に帰還困難区域を除く避難指示が解除され、帰村したのは移住者270人を含めて約1500人となっている。その飯舘村で2021年に廃屋となっていたホームセンターを改築し「図図倉庫(ずっとそうこ)」というプロジェクトを立ち上げたのが矢野淳さんだ。

矢野さんは東京生まれの東京育ちだが、物理の研究者だった父親が飯舘村で除染活動や実験を行いながら認定NPO法人「ふくしま再生の会」を村民と立ち上げた縁で高校時代から飯舘村に通うようになった。

東京藝術大学を2020年に卒業後、飯舘村と東京の二拠点で活動している。「図図倉庫」は震災以降放置されていたホームセンターを移住者が借りて、「未来の環境づくりの自由研究を行う秘密基地を作ろう」と始めたものだ。
世界最先端の環境課題を抱える飯舘村
「図図倉庫」のキーワードは「飯舘村で世界に触れる」だ。その理由を矢野さんはこう語る。
「震災以降の飯舘村には環境に関する研究者たちが集まってきたので、図図倉庫では研究者と村人、ボランティアをつなぎながら、放射能、放射線を起点にした様々な環境問題を調べています。世界の最先端の環境課題を抱えている飯舘村に、最先端の実験や環境づくりをしている人たちが集まる場所になっていると思います」

「図図倉庫」ではコワーキングスペースやシェアオフィスを運営し、環境に関わる企業や大学が活動をしている。イベントスペースや地域のハブとなるような交流スペース、カフェの運営も行うほか、村内でスタディツアーも行っている。

基本的な運営は矢野さんら3人で行っているが、研究者や村民、地域協力隊や学生、さらにデザイナーやアーティストも運営に加わっている。
放射能と放射線の違いが分かりますか?
飯舘村、浜通りの環境のいまを伝える常設展示もあり、高校・大学生のほか、最近は中学生も学びに訪れるという。
「そもそも放射能と放射線の違いが分かりますか?と言われて分かる人はほとんどいないんです。放射線、放射能とは何なのか、それがどういう影響を与えてどういった循環が生まれるのか、研究者の話を中学生にも伝わるレベルに翻訳して解説しています。子どもたちが自分たちで好奇心を持って知りたいと思ってもらえるといいなと思います」

今後矢野さんは、研究者たちと一緒に飯舘村の土壌問題を考えながら、種や土壌、肥料などの園芸ブランドを販売するショップを開設予定だ。
「飯舘村では除染による土壌問題に対して、研究者や村民、企業、大学が豊かな土壌を再構築する実験を行っています。こうして作り上げた園芸ブランドは、美術やデザイン、マーケティング、農学部の学生がつながって企画から立案しています」

まさにピンチをチャンスに変え、つながりを再生する。飯舘村から世界が抱える環境問題に変革をもたらすのだ。






