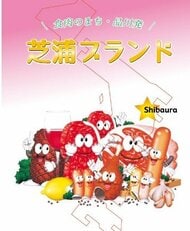日本で罪を犯した人が再び犯罪に手を染めてしまう再犯率は、2022年で47.9%となった。
(令和5年の犯罪白書より)
罪を犯した人のうち、まさに2人に1人が再犯していることになる。受刑者の社会復帰をめぐっては、再犯をいかに防ぐかが課題だ。この再犯率を下げるため、北欧のノルウェーのあるデータに注目が集まっている。

実はノルウェーでは、2010年ごろから受刑者の自由度が高い開放型刑務所制度が取り入れられいて、厳しく処遇が行われていた時より再犯率が3分の1近くに低下したというのだ。
こうした現状を受け、日本財団は日本における開放型刑務所の整備に向けた研究会を立ち上げた。この記事ではその研究会で取り上げられている事例を紹介する。
”塀のない刑務所”でなぜ再犯率が低下?
開放型刑務所は、高い塀に囲まれた刑務所と違い、料理や掃除洗濯を自分で行うなど、自立した生活を送れるような環境が用意されている。
こうした環境により、受刑者が社会復帰に向けた準備ができるようになり、再犯率の減少につながったとみられている。

これについて日本財団公益事業部福田英夫部長は、「行動が管理され、指示待ちの環境では思考が停止する。社会と同じような環境を整え、自ら考え行動することが更生の一歩となる。」としている。
”塀のない刑務所”では逃走事件相次ぐ 保安・安全面の対策は?
一方で、開放型刑務所には受刑者が逃走するという問題がつきまとう。開放型刑務所制度はノルウェーなど北欧で導入されえているが、スウェーデンでは2017年、従来の刑務所では2件、開放型刑務所では24件の逃走事件が発生した。
また、フィンランドでは従来型で5件、開放型刑務所では63件の逃走事件発生している。開放型刑務所では明らかに逃走事件が多発するのだ。

この問題について、日本の法務省・矯正局成人矯正課の森田裕一郎課長は、受刑者に無線タグやICタグをつけ、受刑者の位置情報をリアルタイムで確認できる刑務所にすれば、塀を作らない開放型刑務所の安全性を高められるのではと述べた。
「犯罪者」は支援対象との考え方
元裁判官で、早稲田大学社会安全政策研究所の廣瀬健二研究員は、「スウェーデンでは犯罪者に対して人道的に接すること、犯罪には敬意を払わないが、犯罪者には敬意を払い人格を尊重することが原則となっている」と指摘する。
犯罪者は“問題を抱える人”ととらえて支援の対象とし、社会復帰目標を策定して目標に向けて訓練を積んでいくシステムだという。
こうした犯罪者に対する考え方が社会に根付いていることから、開放型刑務所から逃走事件が相次いでも、社会が許容することができているのだろう。
日本で開放型刑務所を作れるか。そのハードルはまだまだ高いと言えるとしている。日本財団の研究会では、こうした課題についても検討した上で、近く提言をまとめ法相に提出する。