少子高齢化の中、増え続ける医療費、8割ともいわれる経営難の医療機関、労働力不足による医療崩壊の危機。
そんな日本の医療業界が直面する困難な課題に、真正面から切り込む医療ベンチャー“株式会社シーユーシー(以下、CUC)”の勢いが、止まらない。

CUCは主に、医療機関向けの経営支援事業、居宅訪問看護事業、ホスピス事業を展開している。
2014年に社長の濵口慶太さんがたったひとりで創業してから、毎年売り上げを伸ばし、2023年3月期は352億円を達成。同年6月、東証グロース市場に上場を果たし、注目を集めている。
そんなCUCには、様々なバックボーンを持つ有能な“事業家社員”が集まり、活躍している。そして彼らの活躍がまた若手を引き付けているという。
CUCにはどんな可能性と魅力があるのだろうか。
コロナ禍も迅速な支援を展開
CUCとは一体何をしている企業なのか。新卒採用担当の福島里咲さんからはこんな答えが返ってきた。
「“こういうことをしている会社”というよりも、医療の課題を解決し、“医療という希望を創る。”というミッションに関わることであれば、全てやる会社です。例えばコロナ禍中も様々な課題に挑戦してきました」

PCR検査ラボの開設支援から、Jリーグ関係者向けの大規模PCR検査体制の構築、多くの自治体で医療体制がひっ迫する中で、いち早く自宅療養をする新型コロナウイルスの患者の見守り支援、自宅にいながらにして治験を受けられる在宅治験を実行するなど、次々とソリューションを展開してきたCUC。
中でも多くの人に貢献したのは、2021年春頃の新型コロナ「第4波」と時期を同じくしてスタートした自治体・職域の大規模ワクチン接種会場運営支援だ。
国を挙げてワクチン接種が急がれるなか、当時、各自治体では職員の長時間労働や接種会場の運営負担などの課題があり、接種準備がスムーズに進まなかった。
そこで、CUCはワクチン接種会場のオペレーション支援を開始。支援した自治体は全国22にのぼる。
福島さんは言う。
「取り組む課題の幅広さとスピード感、そして、社名の由来ともなっている“Change Until Change=変わるまで、変える。”の精神で、泥臭く医療現場の課題に向き合っていくことがCUCの魅力であり強みだと思っています」
CUCは2014年、診療報酬の改定により経営難に陥った医療機関の経営支援から事業をスタートして以来、一貫して「医療の課題」に取り組み続けている。
現在はベトナムやインドネシア、アメリカにも事業を拡大。今後は、不妊治療や海外からの医療ツーリズムへも事業領域を広げていく予定だという。
入社2年目から新規事業にアサイン
驚くべきフットワークの軽さと柔軟さで事業領域を広げるCUC。
そのため、入社間もない若手にもどんどん活躍の場が回ってくるという。
「入社2年目の時に、部長から『新しい事業やるけど興味ある?』と、ものすごくカジュアルに聞かれたところから始まっておりまして…」
こう話すのは、現在入社5年目の金川和弓さん。
訪問診療クリニックでの運営支援を経て、2020年に新規事業である“在宅治験”を担当することに。現在はリーダーに昇格した。

治験とは、新薬の効き目や安全性などを確認して厚生労働省に承認してもらうための、ヒトを対象とした臨床試験のこと。
従来、治験は医療機関でのみ行うものだったが、自宅にいながらにして治験への参加が可能になるのが在宅治験だ。
金川さんによれば、「治験の8割は遅れると言われている」という。
その理由は、参加してくれる患者が集まりにくいことも大きな要因である。
治験を受けるためには基本的に毎回医療機関に通わなければならない。そのために学校や会社を休まなければいけなくなることや、遠隔地に住まわれている方の通院の負担などが参加のハードルを上げていた。
治験参加を希望する方が少なければ、たくさんの医療機関が参加者を募らなければならないためコストを要したり、募集期間が長引いたりして、試験が遅れるのだ。
在宅治験の導入によって、参加者の負担が減ることで治験への参加難度が低くなり、治験のスピード向上も期待される。

「規制が強い業界で新規事業を進めていくことへの難しさはありました」
しかし、その分の手ごたえも大きかった。
「ある在宅治験を導入した試験が終わった時、製薬会社の方から『この治験は日本の治験の歴史に残るレベルだった』と言っていただきました。
また、小児の難病の患者様が、下校後に友達と遊ぶ時間の隙間をぬって参加できる治験を支援できたときは本当にうれしかったです」
入社を決めたのは社長のひとこと
事業を推し進める金川さんだが、実はもともと医療業界を志していたわけではなかった。
「学生時代に自分の頑張りだけではどうにもならない機会の格差を経験し、当初は教育という枠組みの中で、子どもたちの機会の格差を解決していければと考えていました」
就職活動の際、他の企業からも内定をもらっていた金川さんだったが、社長の濵口さんの言葉で入社を決めたと明かす。
「『自分の子どもたちの世代のためにもっといい医療を日本に残したい』という言葉が決め手になりました。
自分たちが普通に暮らしていたら、だんだんと悪くなってしまう状況を自分たちでなんとか良い方向に変えていく。それが結果的に子どもたちにいい環境を提供することに繋がってゆくと思ったのです」
事業家社員たちの活躍から学ぶ“アントレ荘”

CUCでは、金川さんのように、医療資格をもたない社員たちも活躍している。
理系学部出身者もいれば文系学部出身者もいて、中途社員では前職は商社パーソンだったりコンサルタントだったりと、バックボーンはバラバラだ。
それでも共通点はあると金川さんは言う。
「共通しているのは、みんな挑戦に意欲的だという点です」
CUCでは、自身の信念で事業を行う社員のことを、“事業家社員”と呼んでいる。
患者が自分らしく過ごせるように、生き方の選択肢を増やしたいという信念で訪問看護に取り組むソフィアメディ代表取締役社長兼CEOの伊藤綾さん。
重い病がある方に安心して自分らしい療養生活を送っていただきたいというCUCホスピス経営企画部長の大橋悠介さんなど。
そんなユニークな“事業家社員”たちの仕事ぶりやマインドは、2023年に実施した“アントレ荘”というイベントを記録したミニドキュメンタリーの中で触れることができる。

“アントレ荘”とは、学生とCUCの事業家社員たち6名がマンツーマンのペアを組み、5日間一緒に過ごすというちょっと変わったインターンシップだ。
学生は、事業家社員の会議や仕事の現場に同行し、リアルな現場を体感する中で、事業家が周囲や社会にとってどんな存在なのかを言葉にし、自らが事業家になるためには何が必要か真剣に向き合った。

新卒採用担当の福島さんによれば、この“アントレ荘”に参加して事業家社員と過ごした学生の中には、すでにCUCへの内定が決まっている人もいるという。
「新卒の学生さんからは『知識がないけど医療業界に入って大丈夫でしょうか』と聞かれることが多いのですが、そこは安心してください。
CUCは、医療業界にないノウハウを持ち寄って効率化や課題解決をしていくことが強み。入社時点での医療の知識よりも、事業を創り、課題を解決していくことに興味を強く持っていることが大切です」
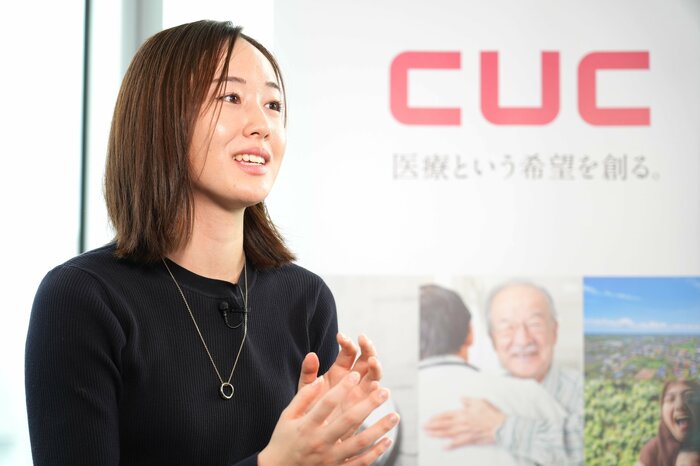
入社2年目だという福島さんも、これからの社会を変えていきたいという思いからCUCに入社した。
「少子高齢化が進み多死社会になっていく中で、亡くなる場所がない人が増えていっていることは大きな課題だと思っています。
生死に関わるすごく重たいテーマかもしれないけれど、だからこそ解決し甲斐がある課題ですし、CUCならそれができると思いました」
福島さんは、社長の濵口さんに「最近失敗しているか?」とよく聞かれるという。
そして「失敗してない」と答えると、「それはチャレンジしてないってことだ」と言われるのだとか。
「そんなふうに、 CUCは挑戦する人の背中を押してくれる風土です。医療の現場で新しいことにチャレンジをしてみたいという学生さんは、ぜひ興味を持っていただければと思います」
<動画を見る>
