羽田空港で、日本航空と海上保安庁の航空機が衝突・炎上した事故から、2日で1カ月を迎えた。

鎮火まで8時間を要した前代未聞の航空機事故の消火活動では水が不足し、東京湾から「海水」をくみ上げて放水を続けていたことがFNNの取材でわかった。
東京湾から海水くみ上げ消火活動
1月2日午後6時前に発生した事故のあと、消火活動には国直轄の消防部隊のほか、東京消防庁から115台の車両が出動したが、FNNの取材でその活動の詳細が判明した。

当初は、消火栓からの水に加え、空港地下の貯水プール「防火水槽」から約300トンの水が使われたが、午後7時半ごろ、その残量が低下したため、10トンの水槽車が2台出動した。

さらに水の不足が続いたため、大量の水を送ることができる「スーパーポンパー」という車を出動させ、午後10時頃から東京湾の海水をくみ上げて事故機への放水を続けていたことがわかった。
そして、事故発生から8時間がたった翌日の午前2時過ぎに鎮火したという。

機動救急救援隊員・田初晋太郎さんは 「こちらの車両はスーパーポンパーという車両になります。(先月2日)当日もここの機動部隊からこの車両が出動しています。東京湾の運河から水を吸い上げて、他隊に大量送水を実施しています」と説明してくれた。
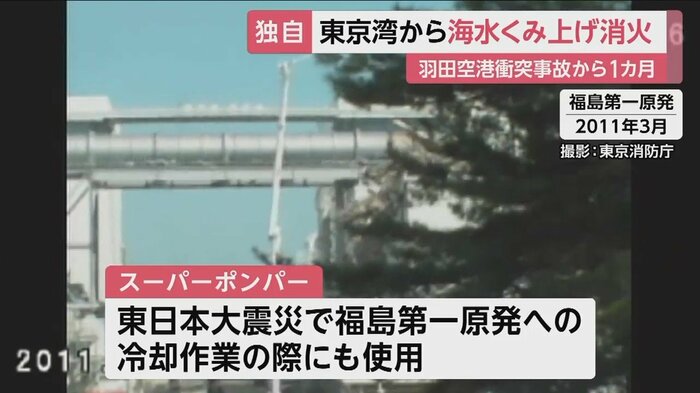
「スーパーポンパー」は、東日本大震災で福島第一原発への冷却作業の際にも使われたという。
東京消防庁は引き続き、今回の消火活動について検証を行うとしている。
複数の人的ミスが重なって事故が発生か
今回の事故をめぐっては、複数の人的ミスが重なって起きたとの見方が強まっている。
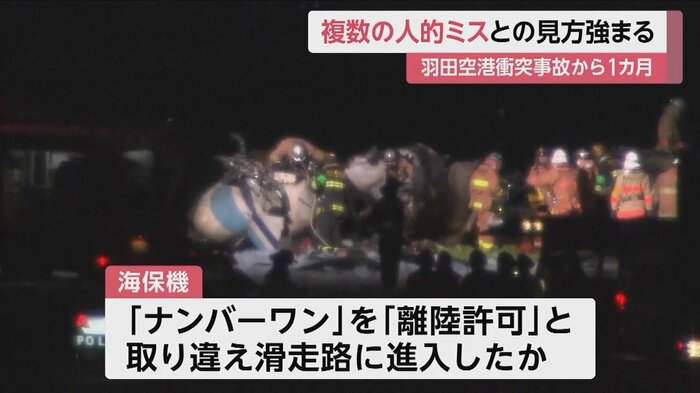
海保機は、管制官が伝えた出発の順番を意味する「ナンバーワン」という言葉を「離陸許可」と取り違え、滑走路に進入したとみられている。
海保機は、40秒滑走路上に停止していたが、日航機のパイロットは、3人全員が海保機を「視認できなかった」と説明している。

また、管制官も「気づかなかった」と証言していて、誤進入を知らせるシステムを見落とした可能性も指摘されている。
国の運輸安全委員会は、事故原因の究明に向け、関係者からの聞き取りやボイスレコーダーの解析などを本格的に進めている。
(「Live News days」2月2日放送より)





