9月9日と10日にインドで開催されたG20(主要20カ国・地域首脳会議)に中国の習近平国家主席は欠席した。この両日の習主席の姿は、その動静を詳細に伝える中国中央テレビ「新聞聯播」でも報じられなかった。

開幕日の9日に伝えられたのは7日午後に黒竜江省で中国東北部の経済振興を促したことと「建国75周年」を迎えた北朝鮮への祝電、モロッコ地震へのお見舞いなどだ。
日本では2日前の首相動静がニュースになることははまずない。祝電やお見舞いは映像がなく、キャスターがスタジオで話すのみだった。G20の2日目、10日になっても習主席の動静は軍を視察した(8日)というだけで、結局G20 の期間中、習主席がどこに居て、何をしていたのかが映像で伝えられることはなかった。

係争地を抱える議長国・インドとの関係、経済をはじめ山積する国内の問題、アメリカ主導の国際会議への不信等々、欠席した理由が憶測を呼ぶが、その複雑な事情と国内の現状を探ってみたい。
メディアに見られる”本音”
習主席欠席の理由を探るひとつのヒントが国内メディアの報道だ。中国共産党系の新聞「環球時報」の9日の社説には「G20を邪魔しているのはいったい誰なのか」というタイトルの記事が掲載された。
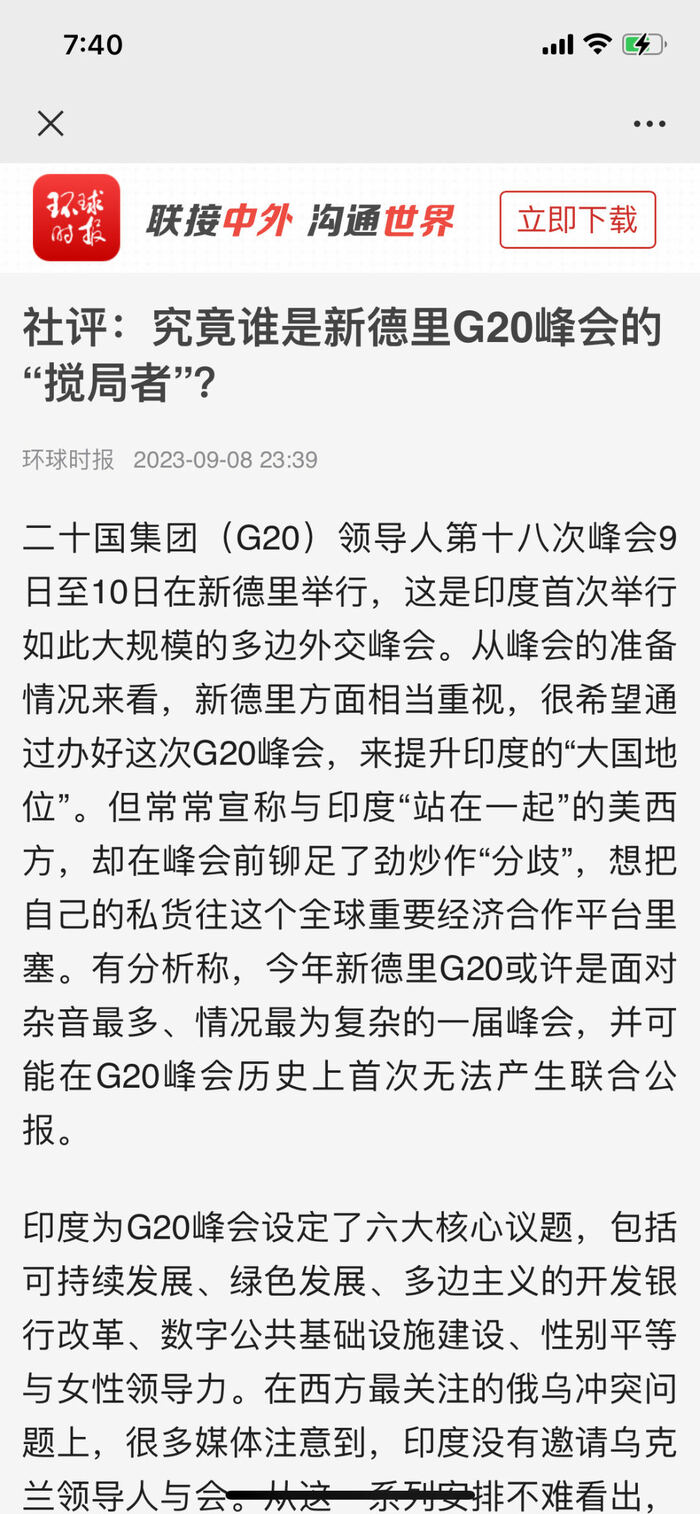
中身は「G20をまとめようとするインドに対し、アメリカや西側諸国はインドを支えるどころかそれを壊そうとしている。中国とインドの問題にも火を付けようとしている」といったものだ。
中国の海外批判は矛先をアメリカに向けたものが多いが、今回もその傾向が顕著に見られる。「中国は自分たちが常に被害者だと思っている」(日中外交筋)という指摘の通り、アメリカ主導の会議への不満であり反発であることがメディアの論調からうかがえる。もちろん、インドへの理解を強調することで、中印関係を維持しようという思惑も垣間見える。同じ時期にベネズエラとザンビアの大統領の中国訪問が発表されたのも、アメリカ中心の枠組みには与しない“意趣返し”なのだろう。
深刻な国内経済
一方で中国の国内経済は深刻だ。不動産不況は改善の兆しが見られず、経済全体の回復の見通しは厳しいままだと言われている。20%を超える若者の失業率は当局が発表をやめてしまった。「実態は40%を超える」(同)とも言われる。人口減少と少子高齢化は進み、将来への不安は増すばかりだ。

経済不安は人々の暮らしに直結し、何より優先する「中国国内の安定」が揺らいでしまう。李強首相がASEAN(東南アジア諸国連合)やG20に対して協力や連携を繰り返し訴えたのも、処理水で反発する日本に関係改善を期待したのも、こうした事情が背景のひとつにあるとみられる。

前述したベネズエラとザンビアの大統領が最初に訪問したのが首都・北京ではなく、広東省の経済都市、深圳市だったことも中国経済の現状と無縁ではないだろう。
習主席のG20欠席と直接結びつくかどうかは別にしても、国内経済はそれだけ深刻だ。ただ、今の政権運営について「習主席はうまくいっていないとは思っていない」(同)という分析もある。正確な情報を元に指導部が適正な判断を出来るのかどうかが中国の今後を占うことになる。
高まる中国の不透明性
誰しも1日は24時間であり、考えられること、出来ることには自ずと限界がある。それは国家指導者も例外ではない。広大な国土に住む14億の国民を治めるだけでも大変だと思うが、同時に諸外国との関係を維持していくことも難しいだろう。考え方や価値観が違う国が相手であればなおさらだ。

ただ、同様の事情を背負った首脳らが参加する国際会議は「国益対国益」のぶつかり合いでもあり、全てが思い通りにいくわけではない。自らの正しさのみを主張し、異論に耳を傾けず、内向きになるばかりでは周囲の不信と不安は増すばかりだろう。

特に今の中国は改正反スパイ法に代表されるように国家の統制がさらに強まっている。そんな時だからこそトップ同士が直接意見を交わし、対話のチャンネルを維持することが中国にとってはもちろん、日本にとってもより重要になる。

そのような現状を踏まえると、絶対的な権力を持つ習主席が理由を明らかにしないままG20を欠席し、何も発信しなかったことで、中国の不透明性をさらに高めることにならないかが懸念される。
李強首相が強調した「対抗ではなく団結」を実現させる気が中国にあるのかは甚だ心許ない。
(FNN北京支局長 山崎文博)






