ビジネスを取り巻く環境は刻々と変化し、世界は「VUCA」と言われる、見通しの立たない時代に突入している。そんな世界において、いま、シリコンバレーも注目する中国の最先端企業はどんなビジネスを展開しているのか。
テック企業に共通するビジネスモデルや変革について、中国のテック企業の事例を中心に取り上げている『世界を変える「とがった会社」の常識外れな成長戦略 GAFAも学ぶ!最先端のテック企業はいま何をしているのか』(東洋経済新報社)から一部抜粋・再編集して紹介する。
著者は一般社団法人深圳市越境EC協会日本支部代表理事の成嶋祐介さん。
実家が日本の伝統工芸品を製造・販売する「株式会社成島」。その販路拡大のため、世界中のテック企業との関係を築く中、気づけば1800社以上の中国企業とのネットワークを築いていたという。
ECビジネスを通じて中国のテック企業の動向に触れていくと「世界のテック企業は、日本人が想像しているよりはるかに先を行っているぞ…」と思ったようだ。
その世界のテック企業が、これまでのビジネスの「常識」にとらわれずにどんな発想をし、どれだけのスピード感でアクションを起こしているのか。
「食」を扱う企業に注目し、24時間365日空白をつくらない、需要と供給のマッチングをどう築いたのか、中国のコーヒーチェーン「ラッキンコーヒー」の事例を取り上げていく。
破竹の勢いで規模を拡大した「スタバキラー」
中国の最大手グルメサイトでありフードデリバリーの「メイトゥアン」と、追随する中国ナンバー2のフードデリバリーサービスを展開する「ウーラマ」。
この2社はさまざまな商品を取り扱う、いわば「食のプラットフォーム」です。一方で「ラッキンコーヒー(瑞幸珈琲/Luckin Coffee))はひとつの商品にこだわりつつも、同じように「空白」を埋める戦略をとっています。
ラッキンコーヒーは中国最大のコーヒーチェーンで2017年にサービス開始。年間売上は1500億円(2021年)、店舗数は6500店を超えています(2022年3月)。

「上海が、世界でもっともコーヒーショップの軒数が多い都市になった」
2021年11月5日、こんなネットニュースが中国のネットメディアでトレンド入りしました。
同日の『人民網日本語版ⅵ』は、「上海市には現在、コーヒーショップが6913軒もある。その数はニューヨークやロンドン、東京にくらべてもはるかに多く、世界でコーヒーショップがもっとも多い都市となっている」と報じています。
中国でもっともポピュラーな飲み物といえば中国茶で、ひと昔前にはコーヒーを飲む習慣はほとんどありませんでした。
それが、今日ではスターバックスが5000店舗以上を構えるなど、中国でもカフェ文化が広まりつつあります。
日系企業もプロント、コメダ珈琲店、ドトールなどが中国に進出しています。
その中で、2017年に突如登場し、破竹の勢いで規模を拡大していった中国の新興コーヒーチェーンが「ラッキンコーヒー」です。
上場廃止の危機を乗り越えて1年で黒字へ
スターバックスと同じ品質のコーヒーを、スターバックスの半額で提供する。
トナカイのイラストがトレードマークのラッキンコーヒーの戦略コンセプトは、実に単純明快です。
スターバックスは、職場でも家庭でもない「第三の場所(サードプレイス)」の提供がコンセプトです。それに対抗して、テイクアウトに絞って店舗面積と人件費を最小限に抑えることで、高品質・低価格のコーヒーサービスを実現しました。
スターバックスへの対抗軸であるこのローコスト戦略が的中し、ラッキンコーヒーは創業して1年あまりで2000店舗を突破し、当時の中国企業としては最速でユニコーンの仲間入りを果たしました。
そして2019年5月、設立わずか18カ月で米ナスダックへの上場を実現しますが、2020年4月に売上を水増し計上していた不正会計が発覚。
同年6月にはナスダックでの上場廃止、当時のCEO(最高経営責任者)とCOO(最高執行責任者)も解任され、アメリカで破産申請するという事態にまで追い込まれました。
ところが、刷新された経営陣のもとで不正会計を処理し、わずか1年で黒字転換を果たします。
そして、2021年時点での店舗数が6024店舗と、スターバックスの5557店舗を上回りました。
創業当初に「スターバックスを追い抜く」と宣言したラッキンコーヒーは、創業からわずか4年で見事にそれを有言実行し、名実ともに中国最大のコーヒーチェーン・ブランドとなったのです。
ユーザーデータを取得して割引率をカスタマイズ
このラッキンコーヒーの復活劇は、当初のビジネスモデルが消費者の支持を失っていなかったことを表しているといえるでしょう。価格に敏感な中国の国民性にもマッチしたともいえます。
そして、ラッキンコーヒーもたんなるコーヒーチェーンではなく、その実態はまぎれもない「テック企業」です。
ラッキンコーヒーの注文はすべてスマートフォンアプリから。メニューを選択して注文し、できあがる頃に店舗まで受け取りに行くか、宅配を選びます。
このスマホアプリこそ、ラッキンコーヒーのビジネスの要です。アプリを通して大量のユーザーデータを取得し、AIのアルゴリズムを裏側で回しています。

それによって、同じ商品でもユーザーによって半額になったり、3分の2になったり、店舗やユーザーに応じてパーソナライズされた異なる価格をプッシュ通知で呼びかけています。
「2人で買うと割引」「5000円分のチケットを購入したら半額」など、さまざまなパターンの割引サービスもあります。
さらに、稼働率が悪い店舗があったら、その周辺にいるユーザーに、しかも、割引に敏感なユーザーをセグメントして、割引のクーポンをプッシュ通知で送るなど「空白をつくらない」需要と供給のマッチングが常に行われているのです。
ユーザーデータから「このユーザーはこのくらい割引しないと買ってくれない」というミクロレベルまで消費行動を把握できているので、プッシュ通知の内容も常に最適化されているのです。
ある意味、ダイナミック・プライシング(変動料金制)にも近いシステムといえます。
ユーザーの情報が常に「見える化」
さらに、ラッキンコーヒーではユーザーの位置情報も、スマホのGPSから常にリアルタイムで「見える化」されています。
その情報を表示するBIツールも非常に優れものです。ちなみにBIツールとは、Business Intelligenceの略で、企業活動における、あらゆるデータを集積・分析・加工するツールです。
ラッキンコーヒーでは、たとえば、「赤いドットは20代女性」「青のドットは10代男性」などと視覚化され、ダッシュボードに表示されています。
どの属性の人が、どの場所で、どのくらいコーヒーを買っているのかがヒートマップで、一目でわかるようになっているのです。
このBIツールなら、データ分析の専門家でなくても「どのエリアでコーヒーが売れている・売れていない」というのが一目瞭然です。その結果、データに強くない社員からも多くのアイデアが生まれ、採用されることもあるそうです。
このように、データの収集やAIによる解析というテクノロジーに目が行きがちですが、その結果を視覚的に伝え、共有するシステムにも、世界のテック企業にはおおいに学ぶべきものがあります。
アメリカでの上場廃止のピンチを乗り越え、短期間で「打倒スタバ」を果たしたラッキンコーヒーは、中国国内の新興企業にとっても優良なロールモデルとなり、同社の成功を模倣したさまざまな飲料サービスが生まれています。
チーズティー専門店の「ヘイティー(喜茶/HEYTEA)」はその代表です。
「ヘイティー」は2012年に創業した中国茶チェーンで、チーズティーが人気を博しています。
中国茶にフルーツとクリームチーズをトッピングした独自のフレーバーで、健康志向の高い若者を中心に大人気の喜茶は、スマホプリで注文したドリンクを専用のロッカーで受け取る「喜茶GO」というサービスを2018年から展開しています。
スマホを通じてユーザーのペルソナ、購入履歴、地域分布、消費ピーク時間帯などのデータを取得し、AIが解析して購買体験の向上につなげるモデルは、まさしくラッキンコーヒーが築いた常道といえるでしょう。
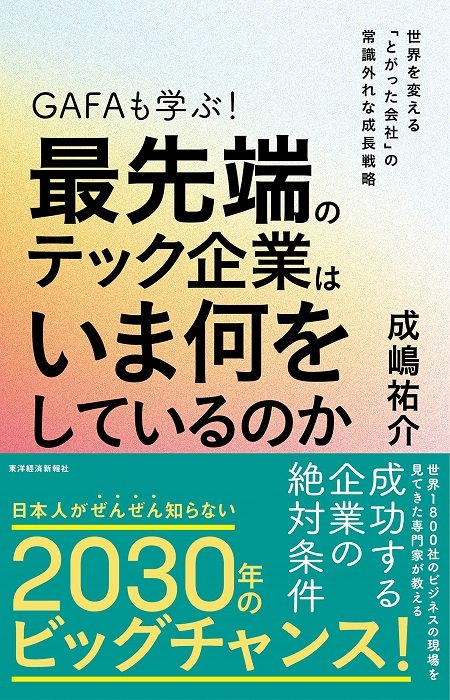
成嶋祐介
一般社団法人深圳市越境EC協会日本支部代表理事。株式会社成島代表取締役。世界の最先端企業1800社とのネットワークを持つ中国テックビジネスのスペシャリスト







