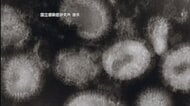新型コロナウイルス、特に、現在のオミクロン株「BA.5」による急激な感染拡大で、全国的に医療提供体制のひっ迫が指摘されている。 発熱外来はパンク状態のため、症状が出た場合でも「受診前にまず電話で相談を!」と呼びかけられている。
自分の症状を、どう見極めるのか。電話相談で伝えるべきポイントを、東京都における新型コロナウイルス対策の「キーマン」で、国立国際医療研究センターの大曲貴夫国際感染症センター長に聞いた。
病院に電話 伝えるべき事は
「見ていると、若い人でも、結構、苦痛は強い。例えば、のどの痛みが強いとか」 。大曲氏によると、若い人や子供でも「のどの痛みが強く食事が取れない」などと訴える人が多いという。
「これだけ流行すると、やはり、そういう強い症状の人は、実数としては増えますよね」。 第6波でも、のどの痛みを訴える患者はいたものの、第7波では、さらに増えたという。そして、のどの痛みだから「大丈夫だろう」と高をくくっていたところ、実際に検査を受けた結果、「空気の通り道が狭くなっていた」ケースもあるとのこと。
このため、医療機関に電話相談する場合は、特に「のどの痛み」「息苦しさ」を伝えるべきだという。
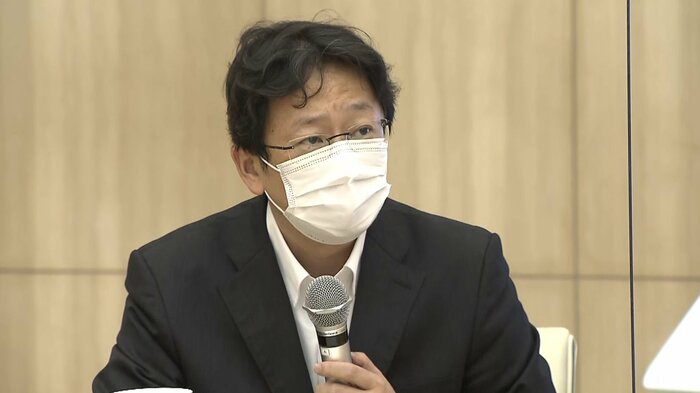
自宅で安静 目安は「これまでの経験」
「自分が経験したことのある”程度”の風邪症状だったら、自宅で安静にすればいいと思います」。 一方で、受診するかしないかの目安は「自分の経験」だという。 これまで、風邪をひいた時と同様の症状なら、自宅で安静にしていれば良いとのこと。
第1波と第7波の違いとは
「純粋に肺炎がひどくて、『酸素が要る』という人は減りました」。 第1波では、病状が悪化し、酸素投与が必要な人は、全体のおよそ20%を占めた。ところが、今年に入ってからの第6波、第7波では、全体の1%に満たないとのこと。 確かに、第1波のころには、血中酸素飽和度を測る機器の売り切れが目立ったが、現在は、簡単に手に入る。
しかし、大曲氏は、「高齢者の方がかかると、やはり弱り具合は尋常じゃないんです。持病があると、それも悪化して、結局、入院が必要となります」 と述べ、油断は禁物だとクギを刺す。やはり、高齢者や基礎疾患のある人の感染リスクは、忘れてはいけないのだろう。

“風邪”症状でも病院に来るワケ
「休業の届けをしなければいけないので、手続きをして欲しいという人はいる訳ですね」 。医療提供体制のひっ迫が叫ばれる中、”風邪”程度の症状であっても、病院を訪れるは多いという。
なぜならば、会社を休むためには「罹患証明書」を入手する必要があるからだ。大曲氏は「書類をもらうために、職場に届けを出すために、『病院に行かなきゃ』という人が減れば、病院・診療所では、多少、外来患者を診る余裕ができると思います」 と訴える。
コロナ感染者数「世界一」となった日本だが、一方で、死亡する人の数は、依然、低い水準だ。医療機関の負担を減らし、必要な人に、確実に、医療を提供できるようにするためには、まずは、自分の症状を、冷静に、かつポイントを外さずに見極めることが重要だろう。
(フジテレビ社会部・都庁担当 小川美那)