フジテレビ系列(FNN)の衆院選特番「Live選挙サンデー」とYahoo!ニュースは、18歳以上を対象に「10月31日に投開票される衆議院選挙の投票に行くか(期日前投票含む)」について、アンケートを実施した。
その結果、「行く」との回答が76.7%となった(前回の衆院選の投票率は53.7%)。本アンケートに答えた層での数字なので、ここまで高い投票率になることはないだろうが、この衆議院選挙に向けては、様々な団体が投票を呼びかけるキャンペーンを展開している。人々の選挙への参加意識はどこまで高まっていくだろうか。
タブーを乗り越えて芸能人が投票を呼びかけ
「これは広告でも政府の放送でもなく、僕たちが僕たちの意思で作った映像です。僕たちの投票への思いを話します」
16日に公開された俳優やミュージシャンによるネット動画「VOICE PROJECT(以下ボイスプロジェクト)。再生回数は24日現在で56万回を超え、各メディアに取り上げられるなど大きな話題となっている。

これまで芸能人が政治的な発言をすることはタブーとされてきた。しかしこのプロジェクトはこうした壁を乗り越え、若手ミュージシャンからベテラン俳優まで登場し、それぞれが投票への想いを語っている。
「この映像が成熟した社会への扉を開けるか」
こうした芸能人の取り組みについて俳優の東ちづるさんはこう語る。
「私は『政治は生活、日常なので自分の人生を大切に生きるには、選挙に行くしかないです』と言って、煙たがられてきました」
東さんは社会貢献活動や発言を長年続けてきたが、「なんか真面目」「選挙に出たら」「芸能人は影響あるから黙っていて」と言われたことがあったという。
(関連記事:芸能人の政治・社会的発言や活動はなぜバッシングされるのか?)

そして東さんはこのプロジェクトにこう期待を寄せる。
「たとえ間違えた発信をしても、攻撃ではなく寛容に受け止め正せる社会、そして職業や肩書きに関係なくのびのびと発言できる社会は、すべての人に生きやすい社会だと思います。そして芸能人の発言に簡単に影響を受けないよう、皆が自分の考えを持つようになるといいなあと思っています。この映像がそんな成熟した社会への扉を開けるのではないかと期待しています」
「いままでの投票キャンペーンと違いを感じる」
また、投票に行く若者世代を増やそうと政治や社会のニュースをわかりやすく発信する「NO YOUTH NO JAPAN(ノーユースノージャパン)」代表理事の能條桃子さんは、このプロジェクトについてこう語る。
「これまで(投票を)呼びかける活動をしていて、今回はより多くの層に届くようなことがされていると思っています。このボイスプロジェクトは、投票に全く関心がない人にもちゃんと届いているなという実感があります」

一方で能條さんは、今回の投票キャンペーンは「これまでとの違いを感じる」と言う。
「いままでは自分の意見は言わない上で、ただ選挙に行こうという呼びかけがすごく多かったと思います。ただ今回は『国民の義務だから投票に行こう』だけでなく、『私たちが生きる社会だからこそ私の問題として捉えようよ』というメッセージが加わっているような気がします。そこに私は今までの選挙との違いを感じているし、希望だなと思っています」
「投票で社会を変えられると感じて欲しい」
今回の選挙では、私事として政治を捉えようと呼びかける様々な取り組みが行われている。その1つがNPO法人キッズドアや学生らによるプロジェクト「目指せ!投票率75%」だ。このプロジェクトでは、4万人以上に次の衆議院選挙で重視する政策についてアンケートを行い、「みんなの争点」としてネット上で公開している。
プロジェクトに参加している関西学院大学4年生の尾上瑠菜さんはこう語る。
「若者世代の投票率を75%まで上げようというのが最終ゴールですが、何よりも『投票に行くことで社会を変えられるんだよ』と多くの同世代に感じて欲しいなと思っています」
(関連記事:「“意識高い系”という言葉が若者の政治参加を阻んでいる」大学生が目指す“若者投票率75%”)
選択的夫婦別姓で「ヤシノミ作戦」展開
また“一点突破”で投票を促す新たな取り組みもある。ソフトウェア開発会社「サイボウズ」社長の青野慶久さんは、選択的夫婦別姓に反対する候補者リストをネット上に公開し、ヤシの実を落とすように、その候補者を当選させずに落とす「ヤシノミ作戦」を展開している。
青野さんは20年前に結婚した際、自身が名字を変えたことをきっかけに選択的夫婦別姓の導入を主張するようになった。
「様々な手続きが大変で、いまもハンコを2つ持ちサインは書き分けながら働くという理不尽な環境にあります。明らかにおかしいので国会議員が何とかしてくれないかと20年も待っているんですけど、なかなか進まない。いまアンケート調査では選択的夫婦別姓にほぼ7割が賛成、3割が反対または分からないとなっています。ですからいま反対する候補者はおかしい、落選してもらおうとこの運動を始めました」

「新しい考え方を受け入れるのが経済政策」
また青野さんは、「選挙ではこの問題より経済を優先するべきだ」という声についてこう反論する。
「東証一部上場企業の社長として、そして日本のデジタル化や働き方改革をリードしてきた立場として、選択的夫婦別姓の導入もできない国が経済成長するはずがないと思っています。反対する人たちはハンコを止められないのと全く同じで、新しいやり方や考え方を受け入れられないし、取り込もうとしない。これを進めることが実は日本の経済政策にとって一番大事なことだと断言します」
「投票に行く」76.7%が意味するのは
前回、2017年10月の衆院選の投票率は全年代で53.7%だった。中でも若者世代は10歳代が40.5%、20歳代が33.9%と低投票率となっている。
一方、今回フジテレビとYahoo!ニュースが行ったアンケート調査では、投票に「行く」と回答したのが76.7%と高い数字になっている。これはアンケートに回答した人の特性なのか、様々なキャンペーンの効果なのか。そして今回の投票率はこの数字にどこまで近づくのか。

若者の低投票率には根本的な問題がある
前述の能條さんは「キャンペーンで少しは投票率が上がるかもしれません」としたうえで、「これをメディアが『いい解決策になる』と思って欲しくない」と語る。
「若い人の投票率が低いのは根本的な問題があると思っていて、外国では18歳や21歳で選挙に出られて同世代の政治家がいるのに、日本は選挙に出られる年齢が25歳、30歳以上です。また若い世代は居住地域に住民票がない人も多いから、選挙に行くハードルが高いのです。そういう制度も含めて変わっていかないと、投票率が上がるのは難しいかなと思っています」
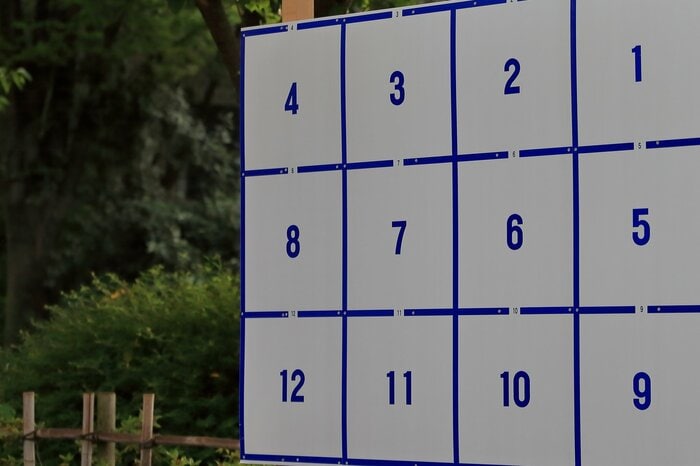
コロナ禍はこの国の様々な問題をあぶり出し、人々は政治が自分の生活や日常に直結することを実感した。私たちの社会や日常をよくしたい、変えたいと思うならまずは投票に向かうことだ。1人1人の投票行動が社会と日常を変えることができるのだ。
(フジテレビ報道局 解説委員 鈴木款)
※この記事はフジテレビ「Live選挙サンデー」と Yahoo! ニュースによる共同企画記事です。記事内ではYahoo!ニュースが実施したアンケート調査を活用しています。アンケートは10月15日にネット上で実施。有効回答は2000人。回答者の性別は男性が61%、女性が37%。回答者の年代は18・19歳が1%、20代が6%、30代が19%、40代が35%、50代が26%、60代以上が12%。





