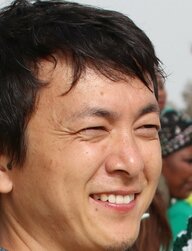ワインを選ぶ基準は味、値段、それとも産地?
今、欧米の消費者がワインを選ぶときの大きな関心は、ワイナリーの取り組みにも注目し、CO2をどのぐらい削減しているのか、自然と共生しているのかなど“サステナブル”なワインかどうかだという。
イギリスにはサステナブルワイン専門店
世界のトップワインが集まる街イギリス・ロンドンには、環境に配慮して作られたワインのみが並ぶサステナブルワイン専門店まである。

専門店の店員は、「どのワインがサステナブルか、なぜそれがサステナブルなのかといった質問をよく受ける。今、イギリスの人たちはますます環境問題に関心を持ち、人類が地球に与える影響を軽減したいと考えている。これは一過性のブームでは終わらず今後も継続して求められていくものになる」と話す。
イギリスの調査会社によると、レストランのワインメニューに産地などだけでなくサステナブルかどうかの記載を希望する人が74%にのぼるという。
チリではCO2を50%削減のワイナリーも
消費者の関心が高い中、グローバルなワイナリーでは10年以上前から環境に配慮したワイン作りをしている。

日本でも人気のチリワイン。そのチリでNO.1の輸出量を誇る「コンチャ・イ・トロ」ワイナリーでは2011年からの10年間でCO2削減50%を達成したということだ。
輸出担当者は、「特に若い世代はサステナブルかどうかを意識している。我々としても地球に対する責任だけでなくビジネスアプローチとして必要だ」と市場の成長につなげるためにもサステナブルな取り組みは必須であるという。
世界を見据えた日本のワイナリーの取り組み
日本のワイナリーも世界を見据えての取り組みをすでに始めている。長野県上田市にあるシャトー・メルシャン椀子ワイナリー。

ピノノワールやシラーなど8品種のブドウを栽培し、日本を代表する赤ワイン「オムニス」などを造っている。この「オムニス」は政府主催の晩餐会で国賓にも提供されており、エレガントな香りと力強い味が特徴だ。

取材に訪れた10月中旬、ブドウが収穫時期を迎え赤ワインの仕込み作業が最盛期を迎えていた。作業台の下をのぞくと、仕込みの過程で出た茎や皮、種などが散乱している。ゴミに見えるがこれらは捨てずに、一カ所に集め堆肥にするということだ。
ワイナリー長の小林弘憲さんはこの取り組みを「畑から出たものを産業廃棄物として捨てるのではなく、畑に戻してあげる。循環農業の一環として価値がある」という。

現在は、その堆肥がまかれたブドウ畑には草原が広がり多くの鳥や昆虫が生息し、景色の美しさに魅了されるが、以前は人も入れないような荒れた場所だったという。
荒廃地をブドウ畑に 思わぬ効果も
ここ上田市は日照時間や通気性の良さなどからぶどうの栽培に適していることがわかっていた。こうした中で、あえて荒廃地をブドウ畑に生まれ変わらせたのは地元住民の要望もあったからだったが、小林さんは思わぬ効果に驚いたという。

「ブドウを栽培するために、年間を通じて下草を管理する。そしてブドウの栽培を管理する。これを普通にやっていたら、遊休荒廃地でいなくなっていた植物や昆虫が帰ってきた。昆虫が帰ってくると鳥が帰ってきて、生態系が豊かになっている」
なんと現在では、絶滅危惧種の蝶など毎年10種から20種類の生物が戻ってきている。
今後はさらに“自然との共生”をテーマにブドウ畑を維持・管理していくということだ。
“サステナブル”のためにワインを軽量化
雨が多い日本ならではの取り組みもある。雨水をためる仕組みを構築し、常時20キロリットルの水をため農業用水に使用、ワイナリー全体の水の使用量の3割程度をまかなっている。
また、製造過程でもサステナブルを意識した取り組みがある。輸送した際に排出されるCO2量を抑えるため、量は変えずに瓶のみを軽量化したのだ。欧米では“重い”というだけで消費者から避けられる傾向にあるという。

このワイナリーを作った神藤亜矢さんは、「一つ一つ取り組んでいることで共感を呼び、飲んでみたい!につなげたい。サステナブルな取り組みと品質向上、両方取り組んでいくことが世界で勝っていく基準になるので、そのためにもグローバルワイナリーの取り組みを学び、日本のワイナリーもさらにレベルアップさせていく必要がある」と意気込む。

また、サステナブルな取り組みを経営の中心に置くワイナリーが多くなっていて、“やっている!”が当たり前の今、いかに消費者にアピールしていくかも重要になるという。
「海外のワイナリーではラベルに認証をつけることを率先しているところもあり、我々もボトルを軽量化したなど環境に配慮しているということを、SNSなどを通じで発信していく」
日本を世界の銘醸地にしていく、日本ワインを世界でさらに認めてもらうための挑戦はまだまだ続く。
今回取材し、サステナブルワインの波は必ず日本にもやってくることを予感させた。
(フジテレビ撮影中継取材部 小堀孝政)