大分市で起きた大規模火災でTKUは発生の翌日、大分の系列局の応援として記者が現地に入った。現場でいったい何が起きていたのか、防災の専門家への取材を交え『火災への備え』について考える。
TKU記者が大分市の大規模火災を取材
11月18日の夕方、大分市佐賀関で発生した大規模火災。大量の黒煙とともに激しく燃え上がる炎。懸命な消火活動によっても火の手は収まらず、さらに勢いを増し周辺の山林などにも燃え広がった。

『関アジ』や『関サバ』が水揚げされる漁港としても知られる佐賀関。この港町を大火が飲み込んだ。火災の発生の翌日、TKUの堂前泉紀記者が大分市佐賀関の火災現場を訪れ、記者として現地取材を行った。

住民は「一気に火が回った。燃え上がって山の方に行くまでどれくらいあったか、5分もないくらい」と話す。空き家も点在する住宅密集地で起きた今回の火災。防災システム研究所の山村武彦所長は、「いくつもの悪条件が重なった」と指摘する。
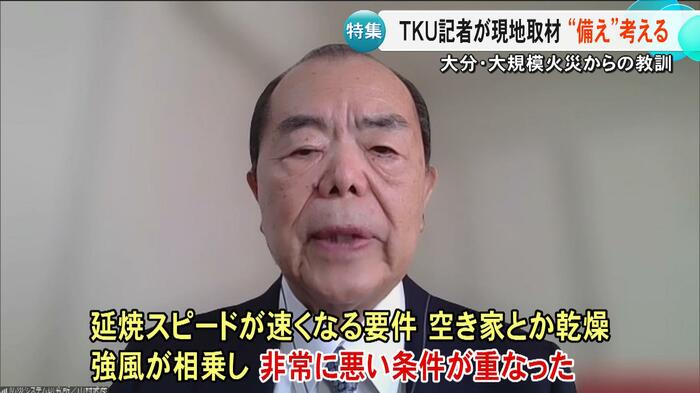
山村所長は「一番の問題は、乾燥していること。そして強風が吹いているので延焼拡大しやすい状態。空き家だと、壁や屋根が荒れていれば、そこに火が着火しやすい。延焼スピードが速くなる要件を、空き家とか乾燥、強風が相乗して非常に悪い条件が重なった」と話す。
約170棟が燃える 狭い道路環境が原因か
堂前記者は現地で「あちらが火元の住宅街です。現在、この場所から煙のようなものは確認できません。しかし、反対側に目をやると、離島から現在も白煙が上がっています」とリポートする。

また、現場から海を挟んで約1.4キロ離れた離島でも火災が発生。山村所長は「強風による飛び火が原因ではないか」と分析する。

発生から1週間がたった今も鎮火に至っていない今回の火災。大分市によると、焼け跡から76歳の男性が遺体で見つかったほか、住宅など約170棟が焼け、焼損面積は、少なくとも4.9ヘクタールに上っている。

なぜここまで被害が拡大してしまったのか。地元の住民は、「条件が悪い。一番悪いのは道路。道路が狭い。今の消防車では通れないのではないか」と証言する。狭い路地が入り組む住宅密集地が消火活動の足かせになったとみられている。

山村所長は「消防車が入れないということは(火元に)近づくことが大変困難なのと、限られた方向からしか、消火活動ができない可能性がある。消火作戦がなかなか取りづらい状態にあったのではないかと思う」と分析する。
「手本にすべき」地域住民の行動
避難所となっている佐賀関市民センターには、家を失った多くの人が身を寄せていた。被災した集落の一つ、田中地区の自治会長、山田二三夫さんは「私(の体)だけ燃えなかった。実家も全部燃えて、どうしようかなと」と話す。
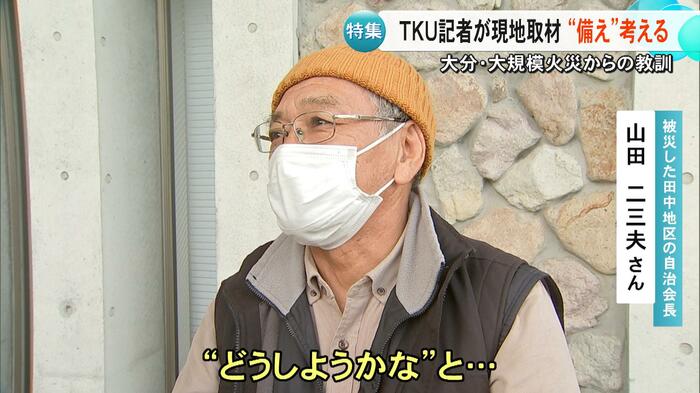
田中地区では、住民同士の『日頃からの声かけ』によって一人の犠牲者も出さずに避難できたという。山田自治会長は「高齢者地区で平均年齢が72歳。足腰が弱い人もかなりいるが、(地域の)班が連携して連れてくる。それが自然に形づいているので、『これはやばいぞ。(住民同士で)避難しよう』と」と当時を振り返る。
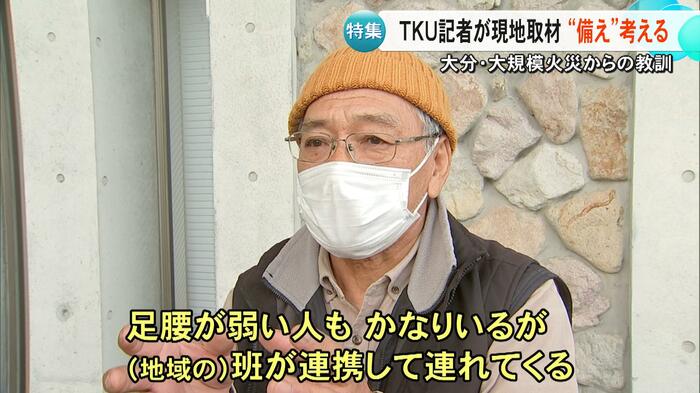
山村所長は、この田中地区での避難行動について「災害時の手本にすべき」と評価する。「大規模災害発生時には、全ての家に消防、警察、自衛隊、防災関係機関がすぐに駆け付けることができない。互いに近くで助け合うことが非常に重要」と話した。
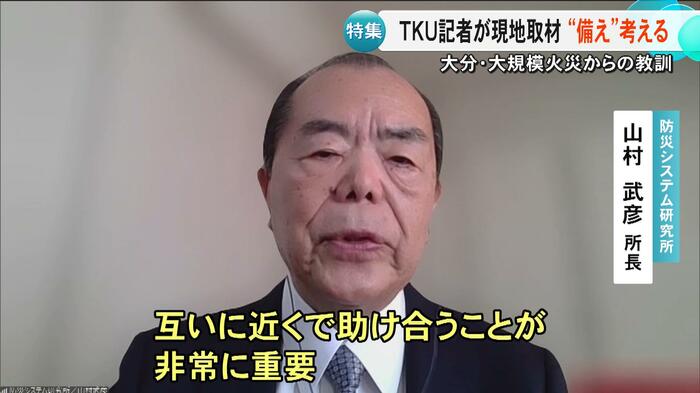
ストーブなどの暖房器具を使用することが多くなるこれからの時季。山村所長は、大分で起きた今回の火災を「『対岸の火事』と捉えず『自分の事』として備えてほしい』と呼び掛ける。
堂前記者「『共助』の大切さ感じた」
--今回、現地に入ってどんな印象を受けたか
堂前記者:私は火災が発生した翌日の19日に現地入りし、その翌日、20日まで取材を行った。住宅など約170棟が燃えていて、その焼損面積の広さに衝撃を受けた。消火活動が続けられていたため、広い範囲に規制線が張られていて、現場に近づけない状況だった。

--避難所の取材では住民からどんな声が聞かれたか
堂前記者:多くの住民が家を失い落胆した様子だった。しかし、皆さんが「命が助かったことがなによりも良かった」と、話されていたことが印象に残っている。港町の大分市佐賀関は南海トラフ巨大地震が発生した場合、9メートルの津波が押し寄せるとされている。そのため、この地域の住民は定期的に津波の避難訓練を行っていた。住民同士が声を掛け合い、迅速に避難できたのは、こうした日頃からの災害への備えが実を結んだと言える。

--一方で避難する際に課題もあったようだが
堂前記者:住民からは「着の身、着のまま飛び出したので、通帳や持病の薬など大切なものを家に置いてきてしまった」という声が聞かれた。事前の準備が不足していたことを悔やむ住民も多くいた。これについて防災システム研究所の山村武彦所長は「いざというときに備え、玄関などすぐに持ち出せる場所に、持病の薬や貴重品などを入れた持ち出し袋を準備することが重要だ」と話していた。
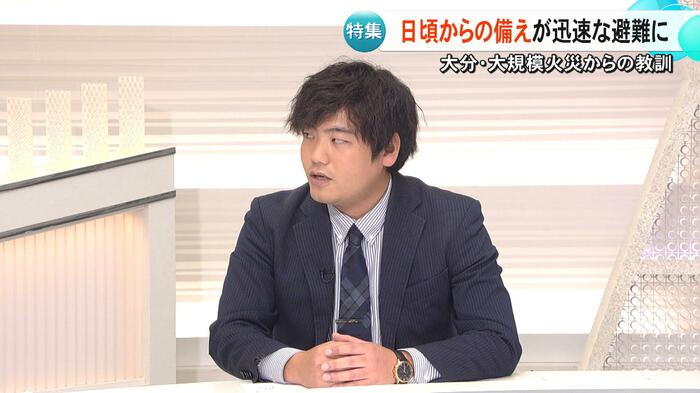
--今回の取材でどんなことを感じたか
堂前記者:住民同士で助け合う『共助』の大切さを感じた。この地域では日頃から住民同士が「顔が見える関係」を築いていた。今回の火災のように大規模な災害が発生した際にはこうした住民同士で助け合う『共助』、『地域の絆』が不可欠。〈日頃から隣近所と良好な関係を築き、災害に備えることが重要だ〉と感じた。
(テレビ熊本)






