輸出が難しい理由
「需要に応じた生産」がなぜ必要かというと、お米が余れば米価が安くなり、離農が加速する恐れがあるからです。「減産で食糧安保が脅かされる」という声もありますが、そもそもお米を作る人がいなくなってしまえば私たちはお米を食べることができません。
「たくさん作って余ったら輸出すればいい」という声もあります。たしかに輸出に取り組む生産者もいますが、販路開拓には相手との交渉や契約が必要です。売り先がない状態で主食用米を大量生産するという博打に手を出す農家がどれほどいるのでしょうか。

また、これまで輸出米の販路を切り開いてきた業者は、主食用米が高くなったことで契約農家が輸出米から主食用米に切り替えてしまうことに困惑していました。だからといって、「海外で日本米の価格が上がったら一気に市場性を失う」(お米の輸出に取り組む米卸)という声があるように、輸出米の買い取り価格を上げることは難しいと言えます。
輸出は販路あってのことですから、「余ったから出す」「足りないから出さない」といった自分本位な取引ができるほど簡単ではないでしょう。
増産には消費の増加も不可欠
お米が高いと言われていますが、以前のお米は安すぎました。兼業農家や高齢農家などの犠牲によって成り立ってきた価格で、持続可能ではありません。あらゆる物価が高騰している中、お米だけ価格を据え置きしろというのはおかしな話です。
ただ、お米の価格の上がり方は急激すぎました。お米は主食ですから、消費者側にとって持続可能な価格であることも大切です。さまざまな品種や規模、栽培方法などによって、お米の価格にバリエーションが生まれるのが理想だと感じます。
鈴木農相が言及している「お米券」の配布は、農家が犠牲にならずに消費者がお米を買い求めやすくなるためには有効と言えるでしょう。
先ほど「食糧安保が脅かされる」という意見を紹介しましたが、食糧安保のためには何よりも私たちが国産のお米を食べることが大切です。「増産」トレンドに向かわせるためには、需要も増える必要があります。需要の増加なき生産の増加は農家をつぶすことに等しいと感じます。最近のお米にまつわる報道は価格のことばかりですが、せっかくの新米の季節ですから、今年の収穫に感謝してお米を楽しみましょう!
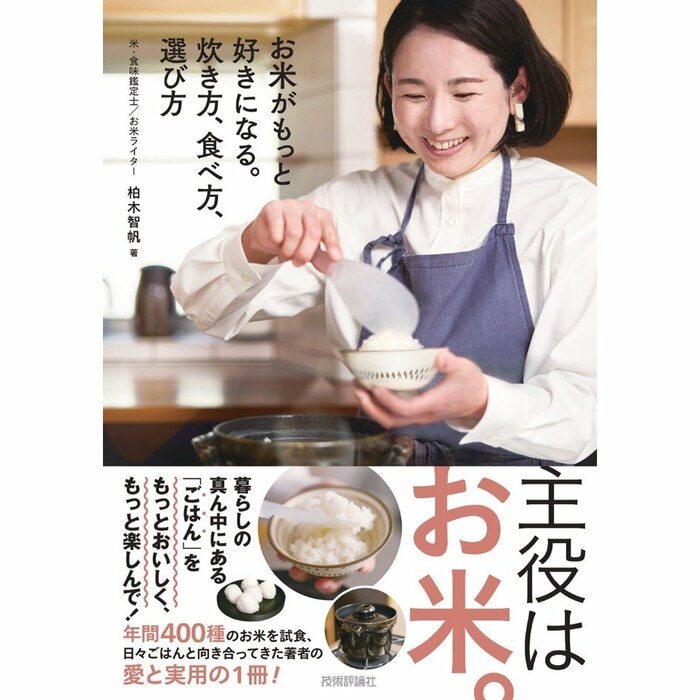
柏木智帆(かしわぎ・ちほ)
米・食味鑑定士、ごはんソムリエ、お米ライター。





