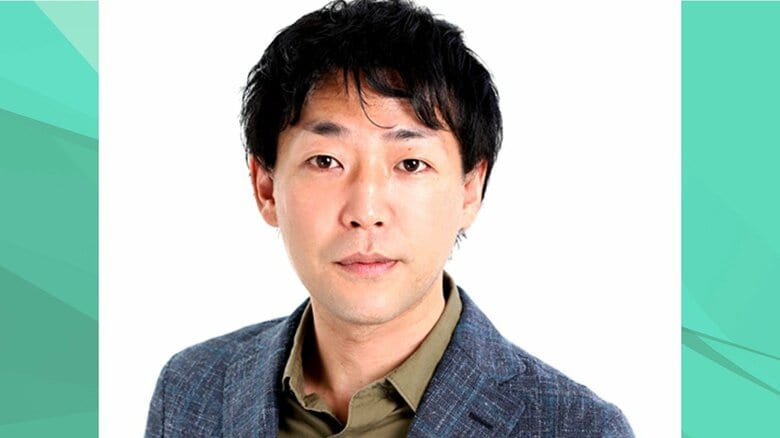サッカー元日本代表で、J3高知ユナイテッドの監督だった秋田豊氏による選手らへのパワハラが明らかになった。
けがで出場機会のない選手に「お前はこのチームの強度に合ってないんだよ。けがばかりしやがって。どうせ出られないんだ。だから早く移籍しろよ」と高圧的に話したことなど5つの事案が、弁護士らによる特別調査委員会でパワハラ認定された。

秋田氏は会見で「選手のためを思っての発言でしたが、嫌な思いをさせてしまったことは本当に申し訳なかった」と語ったが…。
「実はパワハラは“能力の高い人ほど要注意”なのです」
と話すのは「日本ハラスメント協会」の村嵜要代表理事。自身もかつてパワハラ被害を経験し、今はハラスメント撲滅のために様々な活動をしている。詳しく話を聞いた。
“できる人”ほど要注意
【日本ハラスメント協会 村嵜要代表理事】
秋田氏の“パワハラ”は、かなり典型的な例だと思います。
経験値や能力が高い人ほど、いろんなことに気づいてしまいます。「このまま続けていたら、この先、こんな風になってしまうリスクがある」と予測し、よかれと思って色々と言ってしまうのです。
これは管理職なども同じ。“できる人”ほど加害者になりやすい傾向があります。「能力が低い人を育てたい、自分の力でこうしてあげたい」といった一方的な愛情が、きつい発言につながり、パワハラになってしまうのです。
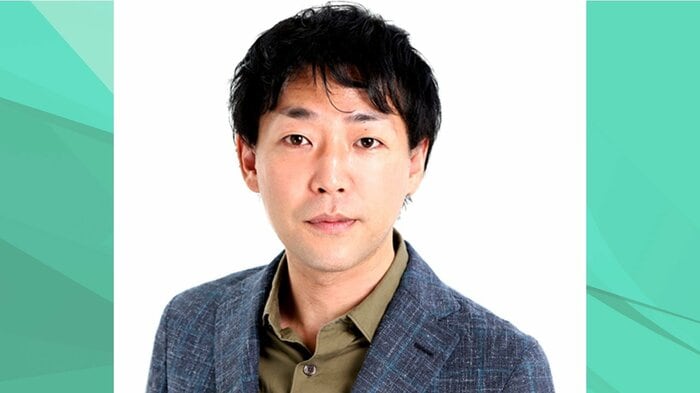
そして、パワハラ加害者の言い訳として多いのが「期待している人だから言う」。「言えば改善されるから言うのであって、ダメな人には言わない」と、本人は愛情を持って接しているつもり…良いことをしていると思っています。
しかし、部下に対する過度な介入は、相手に精神的苦痛を与え、パワハラにつながります。
さらに、見放した人に対して“無視”や“必要な情報を与えない”といったことが起こり、別のパワハラになっていきます。
寄りすぎても、離れすぎてもダメ。極端な行動はパワハラへの危険性が高くなるのです。
不機嫌がハラスメントに…上司たちは大変な時代
不機嫌な態度や表情で周囲に精神的苦痛を与える『フキハラ(不機嫌ハラスメント)』。やられた側が受けるダメージは、思っている以上に大きく、深刻な問題につながる心配があります。
ここ数年、フキハラの相談件数が増加しているのですが、理由の一つとして、2020年から施行された『パワハラ防止法』があると考えています。
今の上司たちは大変です。言いたいことを我慢し、言葉遣いに気をつけながら、新しいコミュニケーションスタイルを自分で生み出してなんとかやっていかなければいけない。
しかし、我慢している分、表情や態度に出てしまうことがあり、それが『フキハラ』という新たなハラスメントにつながってしまっているのです。
フキハラ加害者にならないために
誰に対しても笑顔というのは非常に難しいですし、無理な話です。一瞬、「えっ!」となったり、機嫌が悪くなることは仕方がありません。
そこからどうするのかが、今の時代の上司の腕の見せどころ。思うことがあっても切り替えて、できるだけ早く通常モードに戻して、冷静な態度で原因を確認していくことが大事です。
『誰もが完璧にはできない』ということを前提にしつつ、『なるべく“公平”に接する』という意識を強く持って下さい。
そして、叱り方は「余計なことを言わない。大声で言わない」。
業務上必要なこと、ミスした内容だけを伝えてください。
能力を否定するような発言や、他人と比較するような発言、過去のミスを繰り返し指摘するといったことを無くすだけで、ハラスメントはだいぶん防いでいけると思います。
これってフキハラ?被害者側の対処法
一方、自分が『フキハラ』の被害者かどうかの見極めは『他の人への態度と比べてどうなのか』です。他の人へはニコニコしてコミュニケーションをとっているのに、自分にだけすごく面倒くさそうにされる、など、他の人への対応と比べるのが一番わかりやすい見極め方です。
もし自分がフキハラの被害者だった場合は、第三者に相談しておくことが重要です。表情はなかなか証拠に残りません。問題になった時に証言してもらえるよう、第三者に状況を確認しておいてもらうことが大事です。
おせっかいがハラスメントに!「ちょっとした保険」が重要
“おいしいレストラン”や“素敵な旅先”の話をする…本来なら楽しい会話のはずですが、状況によってはハラスメントになるので注意が必要です。
『マチハラ=マッチングアプリ・ハラスメント』
「恋人がいないならマッチングアプリをしてみればどう?」
この会話に代表される、いわば「おせっかいによるハラスメント」です。
自分がマッチングアプリで素敵な人と知り合った。良い情報だから勧めたいという善意からくる発言でも、価値観はさまざま。こうした出会い方に抵抗がある人もいるでしょうし、積極的にパートナーを求めていない状態の人もいるでしょう。
ハラスメントという意識や気持ちはなく、ついうっかり相手に負担をかけてしまうのがこのケースです。
マチハラになる境界線は?
では『普通の会話』と『マチハラ』の境界線はどこにあるのか。
1回軽く勧めるぐらいなら、会話として問題ないでしょう。しかし、繰り返し強く勧めたり、複数人で勧めたりすると、相手にプレッシャーを与え、ハラスメントにつながっていきます。
また、上下関係がある場合、「上司に勧められたから行かなければいけない」と思ったり、「本当は興味がなくても、興味があるように合わせた会話をしなければいけない」となることがあります。
「●●しなければいけない」
勧められた側に『強制感』が出るようなケースは、ハラスメントになってしまいます。
ではどうすれば良いのかー。
上の立場から何かを勧めるような会話の場合は、“保険をかける”ことが大事です。
「自分は好みの味だったけど、人によって違うからねぇ」とか「無理して行く必要はないよ」など、ちょっとした一言を添えるのが大切なのです。
相手が「楽しそうだな、興味がありそうだな」なのか「引いてるな」なのか、その辺りの雰囲気を感じながら会話するとハラスメント防止につながっていきます。
『ハラスメント十カ条』を意識して!
私が提唱している【ハラスメント防止十カ条】があります。これはパワハラやセクハラなど、さまざまなハラスメントの防止に繋がります。
一、外見をほめない、けなさない、努力をほめよ
二、人と比較した発言をしない
三、あだ名をつけない、あだ名で呼ばない
四、個を尊重する意識を持つ
五、プライベートに介入しない、干渉しない
六、励ますつもりでも、体に触れるな
七、押しつけるアドバイスはしない
八、性別にとらわれない
九、職場での関係だから許されると甘えない
十、上司と部下の立場は業務に関係することだけと知れ
〈出典:日本ハラスメント協会〉
ハラスメントは人の心を殺すとともに、人生を狂わせます。ハラスメントで自殺する人もいます。ハラスメントをなくし、誰もが本来持っている能力や才能を発揮できる世の中になってほしいと強く願います。
(日本ハラスメント協会 村嵜要 代表理事)
取材:高知さんさんテレビ