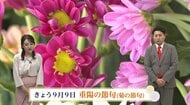霧島連山の麓・高原町。雄大な山々が作り出す天然のろ過装置によって、町には枯れることのない美しい湧水が流れ続けています。
今年2月、この豊かな水資源を活用したある挑戦が始まりました。
(高原町役場産業創生課 野田真也さん)
「こちらはワサビを実験で栽培しているところです」
小林市出身の野田真也さん39歳。去年、東京の不動産会社から企業版ふるさと納税の人材派遣で高原町役場にやってきました。
その傍ら今年2月から個人で約40株のワサビ栽培をスタート。でも、なぜ「ワサビ」だったのでしょうか?
(高原町役場 野田真也さん)
「ワサビは基本的には水だけで育てていく。水質が良いか悪いかが左右している。高原町は畜産とか農業がすごく盛んなんですが、特に水がきれいで、それを利用した特産品の開発ができたらいいなと思って栽培に取り組んでいます」
清らかで豊富な水資源があるからこそできるこの取り組み。しかし、ただきれいな水があればいいというものでもないようです。
(高原町役場 野田真也さん)
「年間通して16℃以下の水温がよくて、ここが湧水を引いてきていて、年間通して一定の16℃。ぎりぎりのラインなんですけどもそこの部分で栽培が可能なんじゃないかということで取り組んでいる」
年間の平均気温や標高など、ワサビの栽培にはいくつもの厳しい条件があるとされています。
高原町の環境はその条件に近いことから、野田さんはワサビ栽培を決意しました。
カメラスタッフが「すりおろし器」を持っていき、味見できないか聞いてみると…
(野田さん)
「いやいや、まだ人間でいったら赤ん坊なのでまだ食べられないです。あと、1年から1年半待っていただければ・・・」
豊かな自然に後押しされて始まったワサビ栽培。しかし、目の前に立ちはだかったのも自然でした。
(高原町役場 野田真也さん)
「(新燃岳の)噴火によって、葉っぱの表面とかに灰が付着したりして光合成とかが出来なくなるので灰を洗い流したりしている。新燃岳の噴火が続いていて、どうしても町にとってマイナスのイメージを与えがちなのですが、こういった水の資源というのは山の恩恵があるものなので、マイナスのイメージではなくてプラスのイメージで皆さんに伝えていけたら。この環境で育つのであれば『宮崎わさび』みたいなブランドにしていきたい」
自然に感謝し自然と共に作る野田さんのワサビ栽培への挑戦は、まだ始まったばかりです。