大学生の就職活動が、コロナによって様変わりとなっている。インターンは中止され、対面の面接の多くがオンラインに代わった。
こうした中、ブロックチェーン技術を活用した新たな就活システムをつくる動きも始まった。実証実験を行っている慶應義塾大学を取材した。
ブロックチェーンで学生の個人情報を保護
「ゼミ生の4年生の就活は終わりましたが、最終面接までZoomだった学生がいました。いまの3年生は大変でインターンが出来ない学生も多いです」
新たな就活システムの実証実験を行うのは、慶應義塾大学経済学部の中妻照雄教授だ。

この就活システムでは、学生がスマホなどを通じて自身の成績やサークル活動など校内外の活動情報を入力する。企業は学生が入力した情報を閲覧するのだが、これまでの就活情報サイトと違うのはブロックチェーンを活用することだ。
昨年就職情報サイト「リクナビ」が、学生の内定辞退率の予測データを学生に無断で企業に販売していた問題が起きたのは記憶に新しい。
しかし新たな就活システムでは、ブロックチェーンを活用して学生の個人情報をネット上に分散・保管し、データ追跡の機能や暗号技術によって保護する。
エントリーシートが要らなくなる就活
しかし中妻氏は、「リクナビの事件があったので個人情報保護が狙いと思われるのですが、基本的には学生が成長するためのツールを作りたいというのが私の考えです」と語る。
「欧米の学生は就活にあたって、自身の“ポートフォリオ”をつくります。つまり学生時代の成績だけで無く、校内外でどんな活動をしてきたかをデータとして企業側に提示するわけです。しかし日本の学生は学生時代に何をしたかデータに残していないんですね。こうしたデータがあれば、企業とより良いマッチングにつながるのです」(中妻氏)
「学生が校内外の活動データを残す」とはどういうことか。
このシステムの開発を手がけている教育ベンチャーのIGS=Institution for a Global Society株式会社の代表取締役社長・福原正大氏はこう語る。
「このシステムの究極の目標は、学生時代の活動がすべてログ(※)として残っているということです。そのログを就職希望の企業に送り、企業がログを見て気に入ればマッチングが行われる。これがあればES=エントリーシートを書く必要が無くなります」
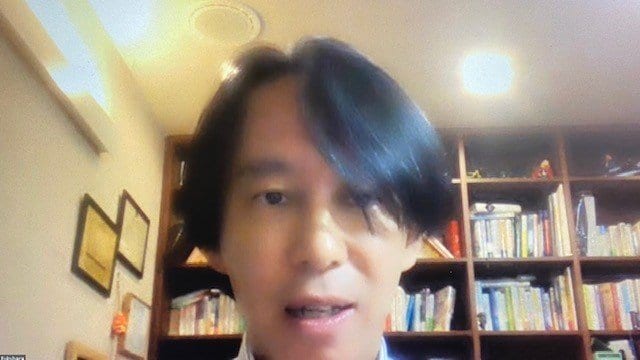
(※)コンピュータの利用状況やデータ通信など履歴や情報の記録
授業態度もログをとって可視化する
中妻氏はこのシステムを使って、授業中の学生の活動をデータ化することも検討中だ。
たとえば、授業で使うコミュニケーションツールによって、学生の授業中の活動ログをとる。これによって、学生が普段の授業の中でどういう活動をしているか分かるのだ。
「単に学校の成績だけでなく、たとえば学生が普段の授業の中でどんな質問を何回したかまで活動ログをとります。これを就活に結びつけるのは、これまでなかったと思います」(中妻氏)
こうなると、これまで企業から見えなかった学生の授業態度が可視化されることになる。授業中の一挙一動がログになれば、学生は居眠りなどしていられない。これは学生にとって相当なプレッシャーとなるのでは無いか?との筆者の問いに、中妻氏はこう答える。
「普段から普通に勉強してればいいわけで(苦笑)。授業の記録がまったく無いのは問題ですし、へんなことを書くと記録があるから抑止力になりますね。システムが普及すれば、みんな授業を真面目にやるようになるということです」
ただし学生が望まなければ、大学や企業は一切情報を見られない仕組みとなっている。あくまで開示情報と情報の送り先を決めるのは学生だ。
学生は就活に囚われず学業に専念できる
慶應義塾大学ではことし12月から5千人の学生が情報入力を開始する。このシステムには銀行や生損保など数社がすでに参加を表明しているが、今後は他企業、他大学にも広げていく計画だ。
中妻氏は「このシステムを活用すれば、学生は就活に時間をとられること無く学業に専念できる」と語る。
「いま大学では就活があるからゼミや授業を休むということが平気で行われています。これを何とか変えたいのです。授業のログがとれてどんな発言をしているのかわかり、活動ログを見れば学生の適性がわかるようになれば、企業は面接で何度も学生を呼びつける必要が無くなるでしょう。このシステムによって、企業が学業を邪魔せずに採用活動できる状態をつくるのが理想ですね」(中妻氏)

昭和の学生は履歴書片手に企業訪問したが、平成ではESをネットで送るようになり、令和ではオンラインで面接する時代となった。ポストコロナの就活はブロックチェーンを活用し、自身の活動ログを企業に送るだけで面接さえ無くなるかもしれない。
【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】





