以前筆者のもとに来られた依頼者の方で、専門家に頼む予定だったところを費用の関係で諦めて、途中までご自身で手続きを行っていた方がいました。途中からどう進めたらよいのか分からなくなってしまったということです。

やけに費用のことを心配されるので、事情をお聞きすると、葬儀社から派遣された専門家がご自宅を訪問し、そこで「最低でも20万円かかる。この難しい手続きを行うツワモノはいない!」と言われ、びっくりされたというのです。
一概には言えませんが、法定相続人が依頼者1人だけだったため、そこまで手続きに時間と手間がかかるものではありませんでした。また、資料はある程度ご自身で集めて来られ、相続人の方ご自身で進めることは十分可能なケースでした。
活用したい「生命保険契約照会制度」
最後に、活用できる制度について述べます。多死社会となり現在多くの制度が創設されつつあります。
まず、生命保険加入の有無を調べる制度です。相続が起こった場合に、生命保険契約に入っていたかよく分からない場合は、保険加入状況を照会できます。
生命保険協会が提供する制度で、「生命保険契約照会制度」と呼ばれています。
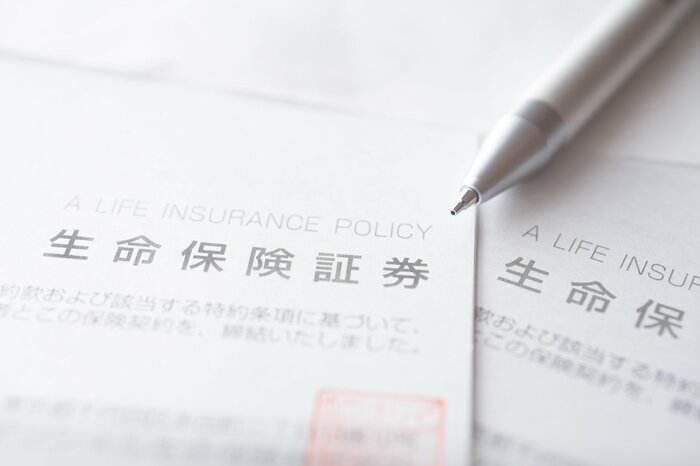
請求する際は相続人であることの証明が必要となります。
照会申請後は、生命保険会社ごとの「契約の有無」及び照会者が保険金等を請求できると判断された場合には「請求可能契約あり」と開示されます。
詳細を知るには開示された情報から、加入中の各保険会社に問い合わせを行うことになります。
26年から「所有不動産記録証明制度」も
2026年2月にスタートする予定なのが「所有不動産記録証明制度」と呼ばれる新たな制度です。これが運用されれば、亡くなられた方が所有していた不動産を一括して照会できることになります。





