男なんだから「泣くな、おごるべき、言い訳するな、失敗するな、酒を飲め」、女は「育児・家事は当たり前、結婚したら氏は夫に」など、多様性やジェンダーレスが言われる時代でも「男らしさ」「女らしさ」を求められる場面や風潮はまだまだある。性別に囚われることなく、誰もが自分らしく生きられるためにはどうすればいいのか。長崎市で行われたジェンダーフリーをテーマにした講座から考える。
"男性優位社会”は男性にとって本当に幸せか
2025年1月、長崎市内で「生きづらさを感じる大人のためのジェンダー」をテーマにした講座が開かれた。医師であり、性教育認定講師の岡田恭子さんは「男は仕事、女は家を守れ、男がリーダー、女がサポートと言われる。このことで女性の能力が過小評価されている。その一方で男性に対しても社会がプレッシャーをかけている」とし、「男は稼がないといけない、弱音を吐いてはいけない」と男性優位社会こそが自らを追い詰めてしまい、生きづらくなってしまう原因だと指摘する。
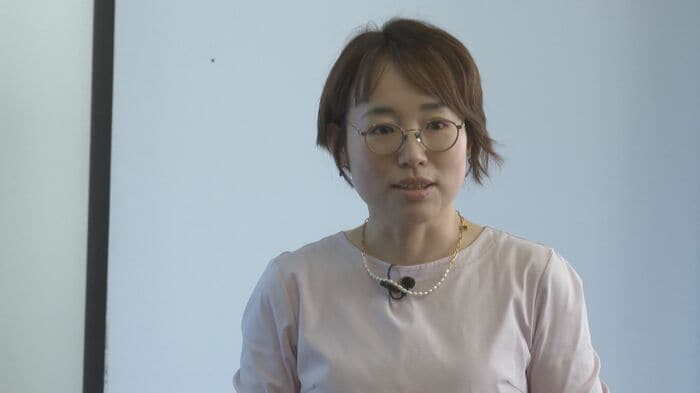
さらに岡田さんは「男性の多くは長時間労働、成果主義という名の減点人事、配置転換、転勤を断れば降格、育休パワハラ、リストラ、休職による離婚、妻からのプレッシャー、両親の介護、妻子のために仕事を頑張れば頑張るほど家庭に居場所がなくなる、男はこうあるべき、弱音を吐ける場所が少ないことで苦しみと絶望の果てに追い詰められる男性もいる」と話している。
男たるもの呪縛に囚われすぎてはいませんか
「男たるもの強くあれ」という父親を見てきた世代は、その呪縛に囚われている人も多いのかもしれない。
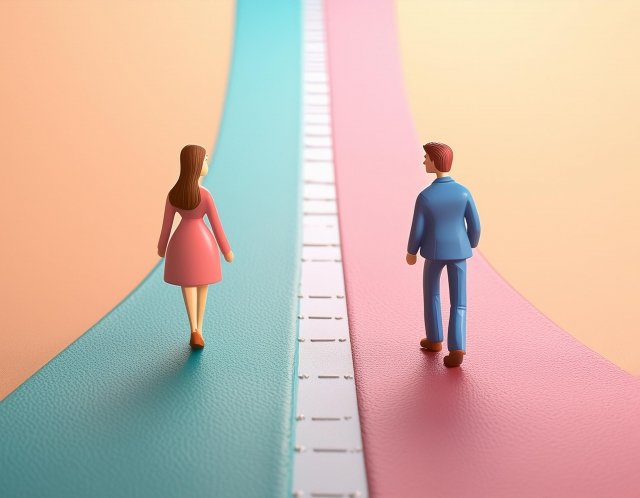
岡田さんは「男らしさにこだわる人は、うつや自殺願望を抱えるリスクが大きいとされている」とし、長崎県の自殺者は交通死亡事故者の約6~7倍で、男性は女性の約2~3倍というデータもある。
「男性はセルフケアができない人が多い、弱音を吐けない、気持ちを口に出さず悩むので悩みがどんどん深まっていく」と、男性らしさが逆に追い詰めてしまう結果にもつながりかねないという。
世界から大きく遅れをとる日本の「ジェンダーギャップ」
そもそも「ジェンダー」とは、社会的、文化的に作られた性で、「ジェンダーバイアス」は性による評価や扱いが差別的であることを指す。国は「社会全体における男女の地位の平等感」について、「男女平等だ」と感じる人の割合を2025年度までに50%にする目標を掲げているが、2022年度は21.2%と目指す数値の半分以下に留まっている。(2022年度内閣府男女共同参画局)

また男女平等を示す「ジェンダーギャップ」について日本は146か国中118位と、国会議員の男女比・労働参加率や就労所得などの男女比によって、特に「政治」「経済」の分野で低迷が続いていて、世界から見ても遅れをとっていることがわかる。(世界経済フォーラム「ジェンダーギャップ報告書2024」より)G7では最下位となっていて、韓国や中国を下回っている。数値を見ると、性別間の差をなくし、男女関係なく活躍できる社会の実現には程遠いのが印象だ。
年間で250万円の差…日本の男女での経済格差 女性の貧困問題
社会的評価の男女間での差は、経済格差も生んでいる現実もあるという。国税庁が調査したデータでは男女間で平均年収は男性が569万円なのに対し、女性は316万円と250万円以上の差があった(国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」より)女性は結婚後に夫の転勤などで退職を選択するケースも多く、パートや派遣社員として働くことも経済格差を生んでいる要因だ。

さらに離婚による母子世帯はここ30年で約1.5倍となり、母子世帯のひとり親の貧困も問題になっている。養育費が支払われているのは全体のわずか4分の1になっていることも貧困に拍車をかける。
男女間格差は学歴にも 親によるジェンダーバイアスも
男女間での格差は県外への大学進学率にも表れている。文科省の調査によると、大学進学率は男女ともに過去最高を更新しているが、東京大学や京都大学、早稲田大学などへの女子の進学率は全体の2~3割となっていて、「女の子を県外に出すのは心配」「地元の大学でいいじゃない」などと、ここにジェンダーバイアスがかかっている可能性があることは否定できない。

また岡田さんは様々な色のランドセルの写真を見せながら、「男の子がピンクを選ぶと子供が学校でいじめられるかもしれないと心配になるので『やめなさい』という、女の子が黒を選ぶと『女の子らしい色にしなさい』と、性別で無自覚に色や役割を結びつける固定観念に大人が囚われすぎてはいないか」と参加した市民に呼びかけた。
自分らしく生きられる社会へ 私たちができること
「家事や育児、親の介護がまだ女性の仕事、逆に男は仕事でお金を稼がなければいけない」という風潮は、いまだ残っている。社会的な風潮だけでなく、そうした環境のもとで育ってきた世代は、誰に言われるわけでもなく自分自身がその考え方に囚われしまい、自分や相手を追い詰めてしまうこともあるだろう。

講座に参加した人は「甥っ子が保育園で“赤ずきんちゃんの役をやりたい”と言ったことがあり、私自身も“赤ずきんちゃんは女の子の役でしょ”と思った。普段、気にしてなかったが、気づかないうちにバイアスをかけているところがあるなと思った。社会を変えるのは難しいが、きょうのような話を小学校など教育の現場で伝えることができれば少しずつ変わっていくのかな」と、教育の大切さを感じたようだ。
また、4人の子供を持つ保育士である女性は、いかに自分が固定観念に囚われていたかを実感することも多いと話す。

4人の子供の母親:子供がバスにひとりで乗る時『何かあったらバスのおじちゃんに言いなさいよ』と言ったら、子供から『お母さん、今は運転手さんだって女の人もいるのに、おじさんて決めつけたらだめだよ』と言われた。何の偏見もない子供たちが逆に大人に教えてくれるなと。日々の子育ての中で勉強になっている。
また女性は、男女間で「不平等感にならないための家庭での実践方法」も教えてくれた。
4人の母親(保育士):夫は料理が全くダメ。 それは私がパソコン、電子機器が触れないのと同じぐらいに、夫は包丁を触れない。作れないんだったら作れないでいいから、その他のことをやってほしい。うちは6人家族だから、みんなで洗濯物を干せば早く終わるし、残りの時間でカードゲームができるねって。家族みんなで家のことをする意識が大切。どうせ言っても無駄だと思ってあきらめるのではなく、とりあえず言って相手の考えや意見を知って考えて行動する。その繰り返しかなと思う。

誰もが平等に自分らしく生きられる、ジェンダーフリーの世の中へ。
性別で「できること、すること」を決めつけるのではなく、まずは一人の人間としてお互いを知り、自分を知ること。そして一方だけに負担がかからないようにお互いに助け合うこと。“知らず知らずのうちに自分も性への固定観念に囚われていないか”いま一度思い返すことも、ジェンダーフリーの社会に向けた第一歩となるのかもしれない。
(テレビ長崎)






