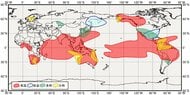6月は例年、多くの地域で梅雨入りし、曇りや雨のすっきりしない天気が増える。真夏に向けて気温が上昇し、湿度も高くなるため、じめじめと蒸し暑くなってくる。
そのような時期、特に気をつけていきたいのが食中毒だ。食中毒は、細菌やウイルスが付着した食品や飲料を摂取することによって引き起こされる病気のことだ。
食中毒の原因
食中毒の原因には、細菌、ウイルス、寄生虫、自然毒、化学物質などがある。
2019年~2023年に発生した食中毒の主な原因は、細菌、ウイルス、寄生虫となっている。他には、自然毒や化学物質などによる食中毒も一定数発生しているようだ。このように、食中毒の原因は様々であり病因物質に応じた対策が重要である。
6月に多い“細菌”による食中毒
食中毒は年間を通して発生しているが、暖かくなるにつれて徐々に増えてくる。5月~6月の梅雨の時期と、7月~9月は気温や湿度が高くなるため細菌が増えやすい。
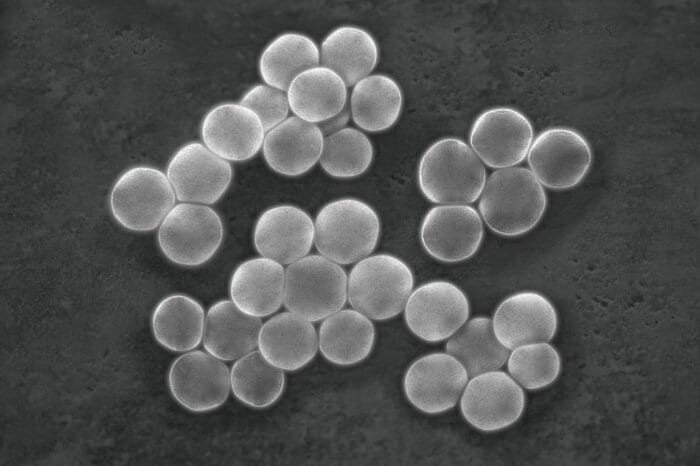
特に6月は過去数年間の平均で見ても、細菌による食中毒件数が顕著に多くなっている。
細菌の種類と対策
食中毒の原因となる細菌には、黄色ブドウ球菌、カンピロバクター、ウェルシュ菌、腸炎ビブリオ菌、サルモネラ菌など種類がたくさんある。
その中でも発生件数が多く、また乳児の重症化した事例が起きたのがO-157やO-111で知られる腸管出血性大腸菌やカンピロバクターである。抵抗力の弱い子どもや妊婦、高齢者の人は重症化する場合もある。

これらの細菌は熱に弱く、食品を十分加熱していれば食中毒を防げるそうだ。加熱が不十分な肉類を食べないことや、手指や調理器具に残った菌が野菜などに付着している可能性がある場合、その野菜を生では食べないようにすることが重要である。

魚介類から検出されることが多いのは腸炎ビブリオ菌である。この菌による食中毒は夏場に集中する。他の食中毒菌よりも速く増殖するという特徴があるが、真水や熱に弱いため、よく水洗いをする、十分に加熱をする、冷蔵庫に保管するなどのことを守れば防げる。

サルモネラ菌も気温や湿度が高くなる初夏から注意が必要である。食肉や卵、乳製品などを介して食中毒や感染症を引き起こす可能性がある。ネズミ以外ではペットから感染することもある。卵を食べるときは殻などの傷を確認し、新鮮なものを使い、加熱調理するのがおすすめだ。
屋外での食事も注意
アウトドアが楽しい季節だが、ピクニックやバーベキューなど屋外で食事をする際には、クーラーボックスなどを使用して食品を冷やし、食べる直前まで冷蔵状態を保つのが望ましい。

気温が25度を超えると食中毒が増えると言われている。ただ、天気予報で伝えられている気温は、芝生の上で日差しが当たらないようにして計られているものであり、実際にはそのような環境とは限らない。屋外では、日差しや照り返しなどの影響を受けて温度が高くなることがあるので注意したい。
家庭でできる食中毒予防
家庭でも食中毒対策をしっかりしていこう。
まず、食品の購入の際には消費期限などを確認し、新鮮なものを選ぶ。肉や魚などは汁が他の食品に付かないようにビニール袋に入れる。
購入後は速やかに冷蔵庫や冷凍庫に入れる。冷蔵庫は10℃以下、冷凍庫は-15℃以下に保つ。また、生鮮食品は他の食品と分けて保存する。

調理にあたって、石鹸やハンドソープを使い必ず手を洗おう。調理の前はもちろん、調理中に生肉・魚介類・卵を触ったときや、トイレに行った後、鼻をかんだ後も必ず手洗いをする。
手や指に傷がある場合、そこに黄色ブドウ球菌が多く付いている可能性がある。調理用や使い捨ての手袋などで手を覆うのは必須だ。この菌が作る毒素は熱に強く、一度毒素ができてしまうと、加熱しても食中毒を防げないので、しっかりと対策したい。

野菜や果実、魚介類は流水で良く洗う。一方で、肉は食中毒菌が飛び散るので洗ってはいけない。生肉や生魚を扱った後は、まな板や包丁をしっかり洗浄・消毒することが重要である。
食材は十分に加熱する(中心部の温度が75℃で1分以上)。そして、盛りつけには清潔な菜箸を用意しよう。

食事前にもきちんと手を洗うことが大切だ。調理後はなるべく早めに食べて、長時間置いたままにしない。残った食品はすぐに冷蔵保存し、再加熱する際は十分に加熱する。
お弁当作りでの対策
お弁当作りでの食中毒対策のポイントは、加熱をしっかりすること、水分のあるものは水気をしっかり落とすか、なるべく入れないことだ。
卵焼きやゆで卵などの卵料理は、半熟ではなく、完全に固まるまでしっかり加熱するようにしよう。ハムやかまぼこなども、できれば加熱すると安心だ。

細菌は水分があると増えやすいため、生野菜や果物はよく洗い、水気を切ってから詰める。このときに仕切りや盛りつけカップを活用しよう。特に梅雨の時期や夏場は、使い捨てカップを利用するのがおすすめだ。別の容器に入れるとより良い。
ご飯やおかずが温かいうちに盛りつけてしまうと蒸気がこもって水分となり、傷みの原因となるため、冷めてから詰めよう。
当日に調理するのが望ましいが、前日調理や昨晩の残り物を入れる場合は、詰める前に必ず十分に再加熱する。このときも冷ましてから詰めるようにしたい。揚げ物や焼き物など、水分が少ないものを入れるのも良い方法である。
また、お弁当を長時間持ち歩くときや食べる時間が未定の場合は、保冷剤や保冷バッグを利用しよう。

弁当箱を衛生的にしておくのも重要である。弁当箱を洗うときは、ふたのパッキンを外す。細かい部分は、泡スプレータイプの洗剤やブラシ等を利用して、隅々まで洗う。
洗った後は、十分乾かす。洗った直後に詰めるときは、清潔な布巾で水分をしっかりと拭き取り、なるべく乾いた状態のものを使おう。

もし嘔吐や下痢の症状が現れ、食中毒の疑いがある場合は、市販の下痢止めなどの薬を安易に服用せず、早めに医師の診断を受けることが重要だ。
梅雨の時期は蒸し暑さで疲労が蓄積しやすい。また、夏の時期は熱中症や夏バテ予防などの体調管理が重要で、バランスの良い食事をとることが大切である。様々な食材を取り入れ、食中毒に気をつけながら、暑い季節も元気に過ごしていきたいものだ。
【執筆:日本気象協会】