大きな大会を陰で支える小さな企業がある。主要なマラソンや駅伝の大会で、選手たちが身に着ける「ゼッケン」。実は、多くが信州製。長く陸上競技を支え、業界のトップランナーとも言える存在となった長野県中川村の企業を取材した。原点は「陸上競技への情熱」だ。
(※外部配信先では動画を閲覧できない場合があります。その際はFNNプライムオンライン内でお読みください)
全国高校駅伝、都道府県対抗駅伝も
佐久長聖駅伝部が6年ぶりの優勝を飾った2023年の全国高校駅伝。
長野県チームが10回目の優勝を果たした2024年1月の都道府県対抗駅伝。
実は、いずれの大会も、選手たちが着けていたゼッケンは「信州製」だ。

さらに、3月10日の名古屋ウィメンズマラソン。
1位の安藤友香選手が切った「フィニッシュテープ」も同じ企業が製作したもの。

手作業でコツコツ
所在地は長野県中川村。
1975年創業、来年で50年を迎えるシナノ体器。
工場では7000枚を超えるゼッケンの製作真っ只中だった。
全国の強豪校が競う春の高校伊那駅伝で選手たちがつけるゼッケンだ。(2024年3月24日開催)

印刷は手作業で、仕組みは至ってシンプル。
シナノ体器の小沢健司工場長は「数字の型というか、版というのがありまして、こういうものを使って印刷をしています」と説明してくれた。

布に印字されるのは1回につき一つの数字だけ。
一気には刷れないのだろうか。
小沢工場長は「たくさん作っているように見えるが、1人が着けるのは(前後)2枚しかないので、同じものが2枚しかないというところで、コツコツやらないといけない」と話す。

数字が変わる度に「版」を変えていては手間が掛かる。
そこで1から134までの「チーム番号」を印字したらー。
小沢工場長は「1区だったら1区ばかりに集める『拾い直し』をする作業、こういう時間をいかに早くやるかも大事」と話す。

選手が走る「区間番号」を区間ごとにまとめて印字していく。
従業員は「選手がみんな頑張っているので、きれいなものを届けたいと思って刷っています」と、一枚一枚、丁寧に作業している。
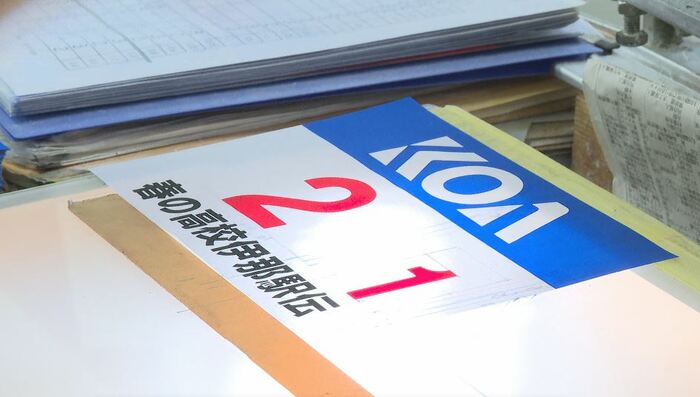
正月のあの駅伝大会も
大きな桁の数字やスポンサー名は「半自動」の機械を使う。
この機械は創業当時からほとんど変わっていないという。
最新のプリンターもあり、丈夫な「紙」のゼッケンにカラフルな印刷をすることもできるが、布製が根強い人気だという。

小沢工場長は「着け心地もあるとは思うんですけど、長い時間をかけて欠品を出さないとか、コツコツの積み重ねで、餅は餅屋じゃないですけど、あそこの会社にお願いすれば安心だよという雰囲気が長い時間をかけてつくられたと思う」と胸を張る。

信頼の厚さを物語るのが、これまでに作った「版」。
全て保存しているという。
「ここにお客さんの財産がある」と小沢工場長は話す。

正月、日本中が注目するあの駅伝用のゼッケンも20年程、ここで作っている。
また、主要な大会を始め長野マラソンなどの市民マラソン、さらには東京オリンピック、パラリンピックでも発注があった。

原点は「陸上競技への情熱」
フィニッシュテープなどの特注品にも応じている。
発注が舞い込む理由の一つが、ほぼ全ての工程を自社で行っていること。
枠に特殊な薬品を塗り、光を当てて作る「版」も自社製だ。

布をタスキに加工するミシン掛けもー。
納期にも柔軟に対応しているそうだ。
小沢工場長は「誰もが知ってるような大会のゼッケンを作ることもありますので、テレビで見かけるとそれだけでもモチベーションが上がる。やりがいにもなりなる」と話す。

小沢工場長も陸上競技の元選手。
「競技を支えてみないか」と30年前、創業者に誘われ入社した。
その創業者、米山正敏さんも若い頃は陸上の選手。競技の指導もしてきた。
その思い入れの強さが高じて開発したのがピストル。

孫の現社長・和希さんは、正敏さんが開発したスタート用ピストルを大切に保管している。
当時は、ゴール地点で、音を合図に計測していたがー。
米山和希社長は 「ヨーイドンでここ(先端)が光って向こうの方にわかるように。音だと時差が出てしまうので、ここに光るものを付けた」 と説明してくれた。

より正確な「光」で知らせるピストルを開発。
特許を取って生産を始めたのがシナノ体器の出発点だ。
米山社長は「(創業者は)陸上が好きで、陸上のことしか頭になかったと思う、ものづくりも好きだったので熱心に取り組んでいた。陸上のことが本当に好きだったんだと思いますね」と話す。

大会を陰で支える小さな企業
特許を大手メーカーに譲ってからはゼッケンの製造に軸足を置き2代目の社長・順さんが生産体制を強化した。
さらに2018年まで行われた「信州なかがわハーフマラソン」は会社が実行委員会の中心となって運営した。

初代、2代目と共に大会に携わってきた小沢工場長。
この経験がものづくりにも生かされているというのだ。
「大会を計画する側にもなったことがあるのでお客さんと(商品を)作る側というより、大会と同じスタッフの一員みたいな気持ちで(製作に)臨んでいるみたいなところがある。よりいいものを作って大会が成功できるといいなという気持ちで日々やってます」と小沢工場長は話す。

この3年の間に初代、2代目が亡くなり、2023年、別の仕事をしていた和希さんが社長に就任。
コロナ禍は注文が激減したが、イベントや大会が復活し2023年4月、過去最高の売り上げを記録した。
米山社長は「長野県のスポーツ選手には中川村、小さな村でこういう全国規模でゼッケンを作っている会社があるとわかってほしいかな」とほほ笑む。

大きな大会を陰で支える小さな企業。
原点は陸上競技への情熱だった。

(長野放送)





