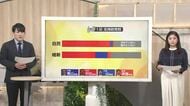「教室にずっといられないことは決して悪いことじゃない」。一人一人の子どもたちが抱える困りごとに寄り添う‟よつばすまいる”不登校などの子どもたちの相談支援に携わってきた校長が目指す、これからの学校のカタチとは。
どの子にとっても安心できる居場所を

富山県魚津市のよつば小学校。
2023年度に導入された校内教育支援センター「よつばすまいる」で、不登校の児童だけでなく、登校しづらかったり、教室に入りづらい子どもたちを支える取り組みが始まっている。

よつば小学校 森田美幸校長:
「学校に来ることが出来ないとか、教室にずっといられないことというのは決して悪いことじゃないので、みんなそれぞれ心持ち違うわけだから、そういうつらい子もよつばの子どもたちであることは間違いなくって、そういう子どもたちがどうしたら学校の中で過ごすことができるのかっていうのを考えて、だったら静かに過ごせる場所を作ってあげれば少しでも学校に足が向くのかなって思った」

2018年、少子化のなか4つの小学校が統合して誕生した、よつば小学校。
養護教諭が2022年度、困りごとを抱えた子どもたちのために居場所づくりをすすめ、2023年度、本格的に動き出した。

どの子どもにとっても‟安心できる居場所づくり”を目指している「よつばすまいる」は、毎週月曜日の午後、教員や元教員の指導員たちが子どもとともに活動したり、相談に乗ったりしている。
月曜日の午後以外は、登校はできるけれど、自分のクラスに入りづらいときや、少し気持ちを落ち着かせてリラックスしたいときに誰でも利用することができる。
現在は、校内で使っていない4つの部屋で、給食を食べたりする子どももいれば、オンラインで授業を受ける児童など、個々のペースで過ごしている。
森田校長は、よつば小学校に赴任する前、県の機関で、いじめや不登校などに悩む子どもたちの相談支援に携わってきた。

子どもにとって大事なこと、それは、一人一人違う「困りごと」に向き合うことだと言う。
よつば小学校 森田美幸校長:
「よつば小学校は500人以上の子どもたちがいる。子どもたちって500分の1ではなくて、1分の1。みんな一緒じゃない。だからよつばすまいるに来る子も一人一人が(求める)ニーズが違うので、どういう風に過ごしたいか何をしたいか、どれだけいたいか、その子と決める。もし今は来ることが出来なかったとしても、元気になったらあなたの居場所っていろいろあるよ。その中の一つとして、学校の中にも居場所があるということを知っていてもらうだけでも、随分違うかなって思うので、選択肢に加えてもらえたら嬉しい」
これから求められる学校のカタチ
魚津市教育委員会では2024年度、「よつばすまいる」のような居場所を、市内にある5つの小学校で設置し、一人一人に合った学びを通して夢や希望が持てるよう細やかな支援を目指す。
森田校長は、安心で魅力のある学校にしていきたいと話す。
よつば小学校 森田美幸校長:
「一人一人が違って当たり前。みんな自分と同じだと思って接するのではなくて、大勢の人が集まって学ぶ場所が学校であるから、その場所で自分とは違う人と関わることを感じて、自分が知らなかったことを誰々さんが知っている。自分と違う感覚で生きている仲間がすぐ近くにいる。それを拒否するのではなく、そうやって自分たちというのはこの世の中で生きていくんだってということを学ぶ場であればいいのかなって。そのために授業であるとか、その他の学校生活がどうあったらいいのか、アップデートしていかないといけないし、そういう場所、学びをこれから構築していきたい」
よつば小学校では、子どもたちの心の元気を取り戻せる居場所が確保できるよう、児童が進学する中学校とも子どもたちの困りごとを共有し、連携して対応に当たっている。
富山テレビではこどもの居場所や環境を考える年間キャンペーン「こどものミカタ」を展開。いじめや虐待、不登校、現状と課題についてみつめている。
2024年1月2日には、不登校の子どもたちが増加する中、これから求められる「学び」のカタチについて歌手でタレントの中川翔子さんや有識者たちとともに考える「こどものミカタ~学びの明日をみつめて~」を放送した。
(富山テレビ)