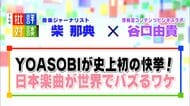映画「東京リベンジャーズ2 血のハロウィン編」が大ヒットしている。
4月21日に公開された前編「運命」と、7月9日に公開された後編「決戦」合わせて、興行収入は49億円を突破した(8月22日時点)。
本作は、さえないフリーターがヤンキーだった学生時代に付き合っていた彼女とその弟が殺されたことをニュースで知り、その翌日に自らも命を狙われるが、死の間際に10年前にタイムリープし、そこから未来を変えようと奮闘する物語。
そもそも“ヤンキー”なる若者が街に現れたのは1970年代から1980年代。
ダブダブの学ランを身にまとい、青春をおう歌する一方で、いじめや校内暴力が社会問題となっていた。
しかし、時代は変わりヤンキーの存在がなくなりつつある今、なぜヤンキー作品がヒットするのか。
映画評論家の前田有一さんと関西学院大学 社会学部 社会学科教授の難波功士さんがヤンキー作品がうけるワケを語った。
ヒットの要因(1)「原作に寄せた役作り」
――映画「東京リベンジャーズ2」が大ヒットしていますが、この現象はどのようにご覧になっていますか。
難波功士さん:
単純におもしろかったですし、俳優さんたちもみんなカッコイイし、体もよく動いているなと思って見ていました。

学生たちにも聞いてみたんですが、「お父さんが見に行って『昔のヤンキー漫画みたいでかっこよかった、おもしろかった』(と言っていた)」と。わりとそうやっていろんな所に広がっているし、あまり否定的な話は聞かない。
前田有一さん:
コミックにみんな寄せてきている。
「トーマン(東京最大の暴走族)」というチームのリーダーである、“マイキー”を演じる吉沢亮さん、その親友である“ドラケン”を演じている山田裕貴さん。
どの役者さんを見てもすごくコミックに対するリスペクトがあるというか、見た目からして寄せてきているなというのを感じた。
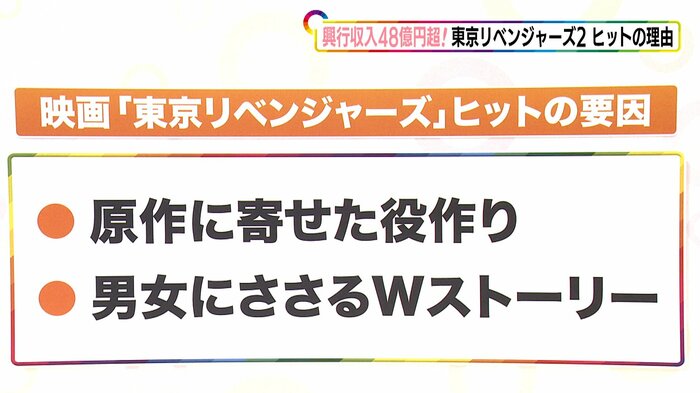
原作ものの映画の場合は特に大事で、あまりにも原作を無視したことをやると、今の時代、炎上しやすかったりする。
“パーちん”と呼ばれる林田春樹というキャラクターを堀家一希さんが演じているんですが、漫画版が結構ぽっちゃりしたキャラクターなので、それに似せるために15キロ以上増量したっていうんです。

日本ではなかなか、“デ・ニーロ・アプローチ”という体重を増減させたり、見た目を変えるアプローチを役者さんができないんですよ。
ハリウッド映画では十分な準備期間があったりするんですが、日本の映画はそこまで準備期間がなかったりするので。
別の映画の舞台挨拶の時に堀家さんを見たんですが、めちゃくちゃ痩せているんです。
「東京リベンジャーズ」の続編の時、どうするんだろうなと思って。また太らないといけないので。それを分かってでもやるというところが、すごく見事だった。
ヒットの要因(2)「男女にささるWストーリー」
前田さん:
「ヤンキーストーリー」と「タイムリープの純愛ドラマ」の要素がある。
ヤンキーストーリーと純愛タイムリープドラマは、ジャンルとしてはめちゃくちゃ離れているものだと思うんです。
この2つを合体させる、となんと意外なことにマリアージュでめちゃくちゃ面白いものができあがった。
ヤンキーストーリーだけだと男性客にはアピールできるが、女性客にはいまいち。
だけど“愛する女性のために何度も戻る”というタイムリープのドラマがあるおかげで、女性客が感情移入しやすくなって、普通のヤンキーものよりもかなりレンジの広いところに訴えることができたというのも勝因だと思います。
“ヤンキー”誕生の背景と大ヒット漫画
――“ヤンキー”というのはそもそもどういう形で日本に根付いていった言葉なのでしょうか。
難波さん:
“ヤンキー”というのはもともと英語で、アメリカ人の俗称で、アメリカとは関係あると思っています。

1970年代の書籍や雑誌では、不良っぽい人の私服ファッションのことを「ヤンキーファッション」と言ってみたり、ベトナム戦争で首都圏にいろいろな米軍基地の米兵がたくさんいて、週末に六本木や新宿のディスコに遊びに来る。
そういった米兵たちの私服ファッションを見て「カッコイイな」と思って取り入れていく中で、不良っぽい男性の中で広がっていった。
それを「ヤンキーファッション」や「ヤンキースタイル」と言っているうちに、不良っぽいファッションを全部“ヤンキー”とくくるようになった。
――1970年代、漫画がヒットして映画化された「嗚呼!!花の応援団」がヒット。これはどういう経緯で、はやっていったのでしょうか。
難波さん:
1970年代は高校への進学率がものすごく高まっていて、不良っぽい人たちも高校には通う。その中で自分を強く見せるために、制服を改造していくというのがものすごくはやります。
男性は学ランを長く、女性はセーラー服の(スカートの)丈を長く改造をする。
その前提として1960年代くらいから、大学の応援団で団長が一番丈の長い学ランを着るという大学の応援団の話があり、制服を改造する中高生の動きがうまく絡み合って、(「嗚呼!!花の応援団」が)ギャグ漫画として面白かったからはやったと私は受け止めています。
――社会への反骨というか何か若者として訴えたい、そういう思いとスタイルがリンクしていった部分もあるんでしょうか。
難波さん:
まだまだ親の権威も強いし、学校の先生も管理教育も世間の常識みたいなものも強かったので、守らなきゃいけない規範みたいなものが、今よりもだいぶ重く中高生にのしかかっていた。
それに反発する人もいたし、一般の生徒たちも反発する子たちを「カッコイイ」と思っているところがあったので、不良っぽい人たちが割とモテるというのもあると、やっぱりみんなそういう格好をしていたところもあると思います。
前田さん:
“ヤンキーってモテる”というのはあった。

今と違って本当に学校で先生の言うことに反発するだけでも、結構勇気のいる時代だったと思うんです。
学校にバイクで来たり、窓ガラス壊してまわるような時代でもあったので、「俺にはできないけれど…」みたいな憧れの目で見る風潮はあったと思います。
“ヤンキー”全盛期に「ビー・バップ」大ヒット
続く1980年代には、渋谷・代々木公園などで踊る「竹の子族」が登場。
日本の若者たちのファッションにもヤンキー文化が浸透してきた。

――1980年代に大ヒットしたのが映画「ビー・バップ・ハイスクール」。仲村トオルさんがヤンキーを演じ、中山美穂さんがマドンナ役を演じヒット。さらに映画「湘南爆走族」では織田裕二さん、江口洋介さんがヤンキー役を演じヒットしました。
前田さん:
特に「ビー・バップ・ハイスクール」はものすごくヒットし、世の中に影響を与えた。
最近ヤンキー映画がちょっとしたブームだったりしますが、それの原点、エポックメイキングとなったのはこの作品だと思う。
「湘南爆走族」は織田裕二さんのデビュー作。江口洋介さんも初主演映画で役名が「江口洋助」っていうんですよ。偶然だそうです。
この2つは漫画もすごくヒットしていて、このヤンキーものというのは漫画の人気から映像にいったというところも特徴的です。
“ヤンキー”文化が衰退後、“チーマー”へ
1990年代に入るとバブル崩壊とともに、次第にかつてのヤンキー文化が衰退していった。
難波さん:
バブルの崩壊があって、景気が良くなかったということが背景にあると思うんですが、70年代から80年代にかけてはまだまだ商店街も元気で、国内製造業建築土木の現場も潤っていた時代だった。
中高生の頃、少々やんちゃなことをしても何とか地元で豊かに生きていく道はあるという感じがあったと思います。

しかし(90年代以降)商店街は寂れ、製造業も空洞化し建築土木、公共事業もそんなに…となってくると、10代で少々無茶しても何とかなるよっていう感じではなくなってきて、そういう人たち(ヤンキー)を見ていてもカッコイイとは思わない。
将来があるように見えないところもあり、昔ながらのヤンキーは存在しなくなっていったと感じています。
――1990年後半になるとドラマ「池袋ウエストゲートパーク」などヤンキーとはまた違った不良たちの存在というのが出てくるかと思うのですが。
難波さん:
「チーマー」と言われる人たちや「カラーギャング」と言われる海外のストリートカルチャーに直結しているような不良カルチャーの方がカッコよくなってくる。
渋谷センター街辺りにたむろしている、東京の私立中高一貫校のお坊ちゃんお嬢ちゃんの集まりみたいなことを言われていました。
もともとは「俺たちは都会でセンスもいいし、暴走族とかヤンキーとは違うんだ」という意識は持っていたと思います。
しかし、だんだんいろんなチーマーが入ってきて、最初の頃のエリート層の文化というものではなくなっていったと思います。
――「池袋ウエストゲートパーク」があそこまでヒットした背景は。
前田さん:
あの作品はスタッフもキャストもめちゃくちゃ豪華なんです。

石田衣良さんのストーリーはもちろん、宮藤官九郎さんが脚本にして、監督の1人には堤幸彦さん。この人たちはもともと、既存の枠に収まらないタイプのクリエイターなんです。
“クドカン”脚本と言えば、それまでになかったリアルなセリフや今までのテレビドラマにないような過激な描写であるとか、ストーリー展開があって視聴者が驚いた。「スゲーのがあるな」という世界観に魅了された。
――2000年代に入ると「下妻物語」の映画など、ちょっとヤンキーが戻ってくるのかなという流れもまた出てきたんですが。
前田さん:
見た目からストーリーからギャップしかない映画で、映画的に見ると、ヤンキー少女とロリータ少女は地方文化と東京文化のメタファーでもある。
その2つが対立するけど最後は認め合うところが、普遍的なテーマだったところもあって、実は日本以外でも評判がよく、特にフランスでは高く評価された。
日本独特の土着的な文化だと思っていたヤンキーものが、実は海外の人にも響くということがわかった。
ヤンキー映画に変化 他ジャンルとの組み合わせ
――2010年代にドラマ「今日から俺は!!」という1980年代に連載されていた漫画をドラマ化したものがヒットしています。
前田さん:
全く新しいものがヒットしたのではなくリバイバルヒット。
このリバイバルヒットというのがすごく大事で、ある人気コンテンツができた時にそれを維持管理して後世に伝えるというのが、エンタメビジネスにおいてはすごく大事なんです。

一番分かりやすいのが「ディズニー」。
100年前に考えたキャラクターでいまだにビジネスを成り立たせている。
それをやるために、ただそれを扱い続ければいいのではなくて、時代に合わせて変化をさせたり、時には別のものとコラボしたり、いろいろな手を使ってやっているんです。
そういう観点からみると「今日から俺は!!」というのはぽっと出てきたように見えるんですが、90年代ずっといろんなビデオを出したりアニメをやったり、コンテンツをしっかりメンテナンスしてきた。
作ってきた人たちの努力が、リバイバルヒットとして実を結んだんだろうなと見ています。
――今後もヤンキーというスタイル、コンテンツの中には生き続けていくということになるんですか。
前田さん:
ヤンキーものというのは、普遍的なドラマが描かれている。
日本はしがらみの多い社会。小学生から大人になっても同じで、クラスの中で浮かないようにしなきゃとか、大人になれば行きたくもない飲み会に誘われたら「行きたいです」って行かなきゃいけないとか。
日本人は本音をなかなか出すことができない状況だと思うんですよ。
でもそんな中で映画やドラマの中のヤンキーたちは自分のやりたいことをまっすぐやってスカッと生きている。友情とか愛とかクサイよと言われるようなことを追いかける。
同じようにはできないけど、同じ思いを胸に秘めて明日の糧にするというか、日本人の琴線に触れる部分があると思うので、これからも続いていくのかなという気がします。
難波さん:
スカッとするエンターテインメントの一つのジャンルというか領域として、何年かに1回ずつヤンキーコンテンツというのは出てきそうな気がします。
(週刊フジテレビ批評」8月19日放送より 聞き手:渡辺和洋アナウンサー、新美有加アナウンサー)