福島第一原発事故から間もなく12年がたつ。敷地内では廃炉に向けた準備作業が続く一方、今年の夏にはいよいよ処理水が海洋放出される予定だ。地元福島の行政や漁業者の声は?福島第一原発の処理水作業の状況を取材した。

敷地内の96%でタイベック(防護服)着用が不要に
「正面に見えている大きな船のあたり、陸から約1キロ先に放水口があります。いま地下の掘削は830メートルまできていて、今年春ごろの開通を目指しています」
2月7日、福島第一原発の敷地内で、筆者が参加した日本記者クラブの取材団に対して東京電力の担当者はこう語り、処理水の海洋放出に向けて準備が着々と進んでいる状況を示した。
筆者は10年ぶりに福島第一原発の敷地内に入った。前回は事故発生からまだ2年で敷地内の線量は高くタイベック(防護服)を着用しての取材だった。しかし事故から12年で線量は大きく低減し、簡易マスク、ヘルメットに線量計装着のみで取材することができた。現在敷地内の96%でタイベックの着用が不要となっている。

燃料デブリの取り出しはこれから
今回の取材の焦点は2つ。1つはこの夏にも行われる予定の処理水の海洋放出に向けた準備状況と地元の声を聞くこと。もう1つは40年かかると言われている廃炉に向けた作業の進捗状況の確認だ。
事故当時1号機から3号機は電源喪失により原子炉を冷やすことができず、燃料が溶けて大量の水素が発生して1号機、3号機と、3号機に繋がっている4号機の建屋が水素爆発した。現在は各号機とも安定冷却を継続しているが、原子炉格納容器内の燃料デブリの取り出しはこれからだ(詳細は続編に掲載)。2号機は水素爆発こそ免れたが、使用済み燃料の取り出しに向け準備作業が行われている。

「今年の秋には処理水の計画容量に到達する」
そしてもう一つの課題が汚染水、処理水の対策だ。汚染水は地下水が建屋に流れ込み、放射性物質に触れることで増加する。流れ込む地下水の量を抑制するため、地面を舗装するフェーシングで雨水が染み込んで地下水が増えることを防いでいるほか、建屋周辺の井戸から地下水をくみ上げ、建屋を囲むように氷の壁を作った。これらの対策により、事故後1日あたり540立方m発生していた汚染水は、現在130立方mまで低減している。
それでも発生した汚染水は、含まれている放射性物質をALPS(=多核種除去設備)などで浄化処理を行ない、敷地内のタンクに保管している。しかし浄化された処理水は増える一方で、このままいけばいずれ敷地内に収容できる限界を超えることになる。敷地内には現在、直径10m、高さ15m、平均容量千トンのタンクが見渡す限りびっしりと並んでおり、東電担当者は「今年の秋には計画容量に到達する」と語る。

「我々は計画的に処理水を処分して行きたい」
「処理水の総保管容量は約137万トンです。いま処理水は約132万トンとなっていて、あと5万トンで計画容量に到達します。昨年シミレーションした結果は、今年の秋頃にも到達するというものでした。当時1日あたりの汚染水の発生量が130トンでしたが、今年度は比較的雨が少ないため4月から11月の平均は1日100トンぐらいで推移しています。ですから若干余裕が出てきているかもしれませんが、予断は許しません」
では容量に到達するとどうなるのか?東電担当者はこう続けた。
「満タンに到達してしまいますと、それ以上の汚染水の処理が出来なくなってしまいます。そうしますとこれまで建屋内の汚染水を汲み上げることができなくなり、汚染された水がどんどん溜まることになる。そうなれば例えば大きな津波が来た時に、海洋に出てしまうリスクが増えるわけです。なので我々は計画的に処理水を処分して行きたいのです」

「処理水放出にはやはり反対なんですよね」
こうした状況を受け政府は、2021年4月に処理水の海洋放出について基本方針を決定した。
東京電力は「基本方針を踏まえて安全を最優先に準備を進める」として、2022年4月からは海域のモニタリング強化のために採取地点を追加拡大し、採取頻度も増やしている。
しかし福島の人々、特に漁業関係者が最も懸念するのが「また風評被害が起こるのではないか」ということだ。県内有数の漁港である請戸港を抱える浪江町で、水産加工を営む柴栄水産の柴強社長は「処理水放出にはやはり反対なんですよね」と語る。
「事故以降皆大変な思いで福島の水産物の風評被害を払しょくしてきました。処理水放出によってまた風評が出る可能性が高い中、やはり処理水を流していいとはなかなかいえないです。たとえまた風評被害が出たとしたら、時間がかかると思うけど、もう一度安心安全でおいしい魚だと思われるように頑張っていくしか無いと思っています」

「国には消費者の皆さんに安全性を伝えてほしい」
柴栄水産は1897年創業の老舗だ。しかし津波によって加工場や事務所は全壊し、レストラン一店舗のみしか残らなかった。それでも2020年4月に事業を再開し、コロナの影響を受けながらも売り上げを順調に伸ばしてきた。柴社長は「震災から1年後に浪江に戻ってきたときは、何もない状態でした」と振り返る。
「しかし浪江町から水産が無くなるのは寂しいと思い事業を再開しました。国にはとにかく消費者の皆さんに安全性を伝えてほしいのと、月に10日しか漁に出られない漁業制限を早く無くしてほしい。お客さんから魚を求められても、提供できないのが一番辛いですから」

「風評被害は海だけでなく農業、観光にも問題」
さらに浪江町の吉田栄光町長は「風評被害は海だけではない」と語る。
「小委員会(※)からは科学的な知見から、基本的には大丈夫ですよと。しかしこの地域の将来を考えると、放出が続くのはどうかと。私は勉強中です。本当に危なければ止めなければならない。危なくないなら地域の復興考えれば申し訳ないけど流させてもらうしかない。また風評被害は海だけの問題ではなく、農業や観光にとっても問題。とてつもないエネルギーをかけて復興しようと言っているときに、この処理水は大きな課題です」
(※)多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会
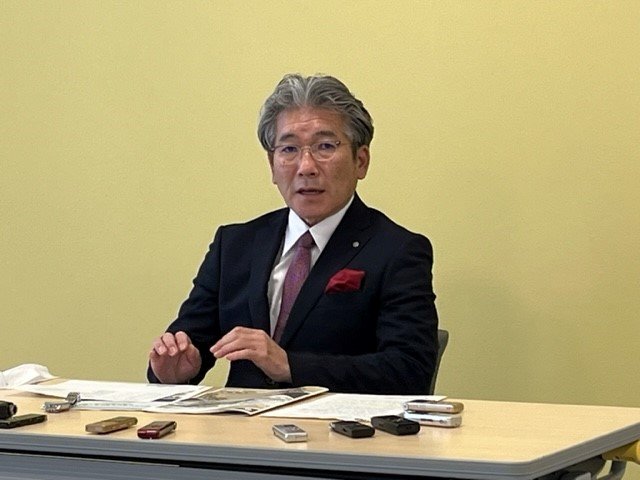
東電では、処理水を含む海水の水槽でヒラメやアワビなどを飼育する施設を敷地内につくり、通常の海水で飼育した場合との比較を行って、その状況をYouTubeなどで公開している。これを始めた理由を東電担当者は「処理水を入れた海水で、生物がちゃんと生きているのを見せてくれるのが一番安心に繋がるという話をたくさんお聞きしました」からだという。
「世界ではさらに放出量の多い原発がある」
東電が掲げる処理水のトリチウム濃度の運用基準は、1リットルあたり1500ベクレル以下だ。これは「国の規制基準である1リットルあたり6万ベクレルに対して40分の1」(東電担当者)だという。またトリチウムの年間放出量について東電担当者は、「事故以前のトリチウムの総量目標は22兆ベクレル以下で、今回もそれを踏襲している」という。
さらに東電担当者は「国内の原発でもPWR(=加圧水型原子炉)の発電所を持っているところは、もともと放出量が多いところもありますし、世界に目を向けてみると韓国やカナダ、イギリスやフランスではさらに放出量が多い原発もあります」として、今回の放出が世界的に見て決して多いものでは無いと強調する。

「事故以降我々は信頼を失っているところもある」
しかし東電がいうのはあくまで「事故前の上限目標の踏襲」だ。ある政府関係者は「事故前の年間放出量は約2兆ベクレルだったが、いまタンクに貯蔵されている処理水は約780兆ベクレルなので今回は上限値ぎりぎりまで放出するはず。つまり総量は10倍になる可能性があり、東電の説明はおかしい」と語る。
東電担当者は「事故以降我々は信頼を失っているところもあるので、繰り返し丁寧にご説明をさせて頂きます。風評被害が発生してしまった場合には、しっかり賠償させて頂きます」と語る。
東電の説明は果たして福島の漁業関係者や住民、そして国民の理解と納得を得られるのか? 一度失われた信頼を取り戻すのに、12年の月日で足りるのか。

(※)福島第一原発の敷地内の画像はすべて代表撮影
【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】






