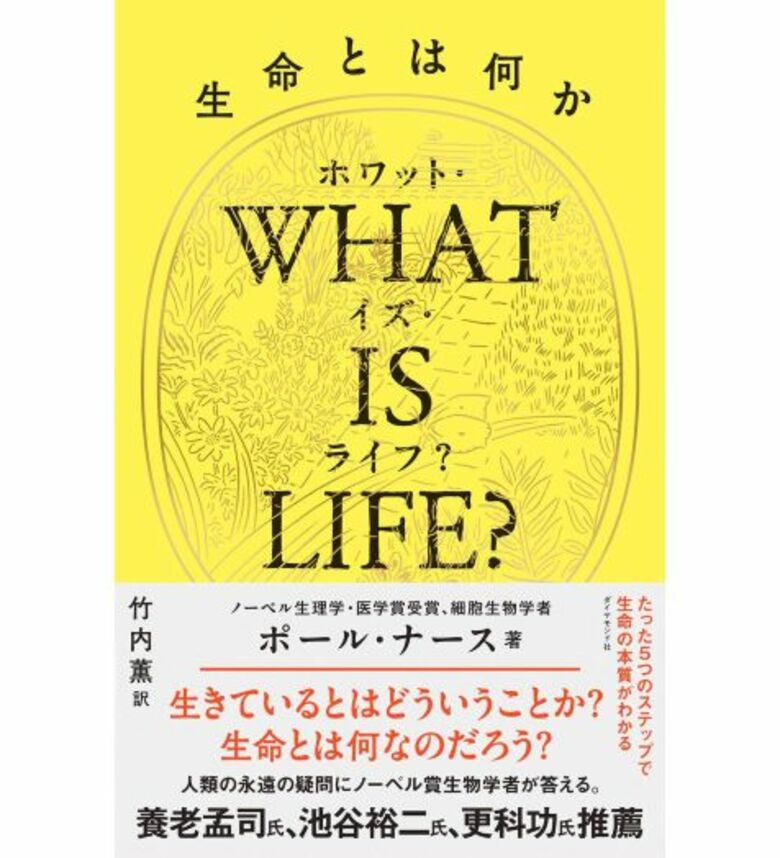今回の書評は、2001年にノーベル生理・医学賞を受賞した細胞生物学者が書いた『WHAT IS LIFE? (ホワット・イズ・ライフ?) 生命とは何か』(ポール・ ナース著 /竹内薫訳/ダイヤモンド社)である。
著者の魅力がにじみ出るサイドストーリー
かなり前に何かの本で、時代の最先端を研究する生命科学者は、意外にも宗教に深く帰依した人が多いと読んだことがある。生命体はため息が出るほど緻密にできていて、神を持ち出さないと納得できないことが多いからだという。
だが、この本を読む限り、著者のポール・ナースはそうは考えていないようだ。というより、はっきりと彼は「生命体は複雑な生化学機械である」と述べている。 徹底した無神論者ではあるが(学生時代にバプテスト派のキリスト教徒であることをやめている)、だからといって、冷徹で人間味のない人物ではない。それどころか、人間味豊かな愛すべき人物であることが、この本のあちらこちらでにじみ出ているのである。
この書籍は一般の読者向けの科学啓蒙書だが、サイドストーリーとして著者のこれまでの人生のエピソードも散りばめられていて、それがこの本をいっそう味わい深いものにしている。
イギリスの学者、それもノーベル賞まで受賞した人物に、人はどのような生い立ちを想像するだろうか。 両親ともオックスブリッジ(オックスフォード、ケンブリッジ両大学の総称)の教授、あるいは貴族か資産家の家系に生まれ育ったと思い込んでしまいそうだ。最近は緩みはじめたとはいえ、イギリスは先進国のなかでも階級社会の遺風が色濃く残っている国だ。 しかし、ポール・ナースは違う。
父親は缶詰工場の工員で、母親は清掃員だった。そして兄や姉は15歳で学校教育を終えている。典型的な労働者階級の出身なのである。それでは勉強が抜群にできたかというと、そうでもない。
彼は、大学入試に必要な外国語(フランス語)の試験に6回も落ちてしまい、自嘲気味に 「落第の世界記録」と述べている。 大学進学の夢破れた彼は、ある醸造所に併設された微生物学研究所の実験助手として働くことになった。幼いころから昆虫や生き物が大好きだった彼にとって、その仕事は天職といえるほど充実したものだったらしい。しばらくして、ある日、バーミンガム大学の教授がポール・ナースに、面接を受けるよう声をかけてきた。そして、その教授は面接での彼の深い生物学の知識に感銘したものか、大学にフランス語の落第に目をつぶるよう掛け合ってくれたのだった。
バーミンガム大学はイギリス屈指の名門国立大学である。そんな一流校が教授の口利きで入学を許されるなど、日本では考えられないことだ。不正入学だと糾弾されるだろう。だがイギリスは階級社会の遺風を残す一方で、融通無碍と表現できるほどの柔軟性をも見せるのである。そして、このバーミンガム大学の柔軟性は、三十数年後にこの大学にとって4人目となるノーベル賞受賞者輩出という栄誉をもたらしたのだった。
こういった懐の深さは、数値には表せないが一国の国力を示す。つまり、実力のある若者には、その経歴がどうであれ、その実力にふさわしい場を提供するという国民性もまた、将来の成長を約束する国力なのだ。戦前の日本もそういうところがあった。GDPや軍事力だけが国力ではない。
さらに生化学と細胞の本筋の合間を縫うようにつづられる人生のエピソードの中で、特に強い印象を受けたのが、著者がアメリカのロックフェラー大学の学長に就任するために 「グリーンカード」を申請したときの話だ。
出生証明書に両親の名前が記載されていないという理由で、申請は却下された。いらだちを覚えながら、出生証明書の完全版をイギリスから送ってもらったポール・ナースは、封筒を開けた瞬間、激しい衝撃を受ける。 彼の父と母は本当の両親ではなかった。祖父母だったのだ。 本当の母は彼の姉で、17歳で身ごもり、親類の家で出産し、その後、祖父母が自分たちの息子として彼を育てたのだった。シングルマザーが恥ずべきこととされていた時代のことである。「遺伝学者なのに、私は自分の遺伝について何も知らなかったのだ!」と彼は嘆く。
父親の欄にはただ横棒が引かれているだけ。そしてその時点で、経緯を知っている親族はみな亡くなっていた。逆にいえば、実の父親も自分の息子がノーベル賞を受賞したなど、夢にも思っていないだろう。
生命の基本単位「細胞」
サイドストーリーのエピソード部分の話が長くなってしまった。
本編の生化学や細胞の話に取りかかろう……といっても、評者は「生物」も「化学」も高校時代は全く得意ではなく、さすがに6回とまではいかなかったが、「化学」は赤点をとってしまったこともあった。ならば、なぜこの本を選んだのかと問われれば言葉の返しようもないが、とにかく科学啓蒙書が好きなのである。
ただ、そんな評者でも「へぇー」「ほう」と感心するページが数多くあった。 以下に列挙すると……
細胞は顕微鏡でないと見えないと思われがちだが、肉眼で見ることのできる巨大細胞もある。卵の黄身がそれである。なるほど、そうなのか。この他にも長い細胞もある。人間の背骨の付け根から足のつま先までつづく神経細胞は長さが1メートルもあるそうだ。しかし、全般的に細胞は極微の存在で、それは顕微鏡の発明とほぼ同時に発見された。
すべての動物は、生命の完璧な特徴を備えた「命の単位」(=細胞※評者注)の集まり、これも、単細胞生物などで漠然とは分かっていたが、多細胞生物の細胞が生命の完全な特徴を備えているとは新鮮な驚きがあった。つまり、人間も含む多細胞生物の細胞はそれ自体一つの生命で、30兆個以上の細胞で構成されている人間は、30兆個以上のそれぞれの生命の集合体ということになる。なんだか不思議な感覚をおぼえる。
細胞の内部は非常に複雑で、それは巨大な化学工場をはるかに上回るパフォーマンスを発揮する。分子モーターというべきタンパク質があり、それは配達ドライバーのように、細胞内の必要な箇所まで化学物質を運ぶ役割を果たす。
以下は一つの細胞内で繰り広げられている“化学工場“の描写である。
分子機械は、精巧に分岐した鉄道網のごとく、細胞の内側に縦横に張り巡らされた複雑な経路をたどり、この任務を遂行する。研究者が撮った、活動中の微小な分子モーターの映像を見たことがある。分子モーターは、まるで小さなロボットみたいに細胞内を「歩き回って」いた! 分子モーターには、常に前進し続け、他の分子と偶然衝突して道から外れないようにするラチェット機構まで備わっている。
くどいようだが、人間を構成する30兆個以上の細胞の中で、これらが昼夜休むことなく繰り広げられているのである。それでいて、よく統一感が保たれているものだと感心させられる。また、分子モーターの一つ一つは電子顕微鏡でないと観察することができないほどの小ささだが、このモーターが何千万もの筋細胞のいたる場所で何十億個もが一致団結して働き、蝶の羽根をはばたかせ、チーターを素晴らしいスピードで走らせるという。
さらに驚くことに、細胞の外膜は分子2個分の厚さしかないらしい。そしてポール・ナースは、この外膜こそが生命と物質を分かつ本質だとする。
最終的に外膜は、宇宙全体を覆っている無秩序や混沌へと向かう力に、生命が首尾よく抵抗できる理由を説明する。細胞は隔離してくれる膜の内側で、自分たちが稼働するために必要な秩序を定め、それを高めていく。同時に、自分を取り巻く周囲の環境に無秩序を生むことができる。こうやって帳尻合わせをすれば、生命は熱力学の第二法則(訳注:あらゆるものは時間とともに秩序立った状態から無秩序な状態へと向かう、という物理法則。生き物は秩序あるものを食べて無秩序なものを排せつすることで、体内の秩序を保っている)に背くことはない。
考えようによっては、分子2個分の外膜によって、細胞・生命体は熱力学第二法則的に「宇宙とは別の宇宙」を作ってしまっているとも解釈できる。外の宇宙と内なる宇宙。これは哲学的にもとても意義深い指摘ではないだろうか。
ノーベル賞学者の知性とダイナミックな着想
ノーベル生理・医学賞の受賞理由となった「細胞周期」の説明も、もちろんなされている。
「細胞周期」とは一つの細胞が分裂して二つの娘細胞を生み出すときに起こる事象と周期のことをいう。それが積み重なって、一つの細胞が分裂を繰り返して最終的に30兆個以上の細胞になり人間を形成する。
その際に時間の制御という問題が発生する。つまり、適切な時期に分裂し、適切な時期に分裂を停止しないといけない。考えてみれば当たり前のことだが、この制御ができてこそ、生命は極端な巨大化を避けることができ、臓器は一定の大きさにとどまるのである。それでも細胞は増殖する能力を内に秘めていて、そうすることによって傷は癒え、穴の空いた内臓は閉じることができる。非常に都合のいいシステムだが、彼は実験によって、この仕組みの化学的な説明に成功したのである。そしてこの仕組みはビール酵母から人間まで、すべての生命体に共通していることも。
そして、ポール・ナースはこの生命体の共通性に着眼して、大胆にもこう主張する。
生命の化学的基礎におけるこうした深い共通性は、驚くべき結論を指し示している。なんと、今日地球上にある生命の始まりは「たった一回」だけだったのだ。もし異なる生命体が、それぞれ何回かにわたって別々に出現し、生き延びてきたとしたら、その全子孫が、これほどまで同じ基本機能で動いている可能性はきわめて低い。
ノーベル賞学者の知性とダイナミックな着想に、ただただ、ため息が出るばかりである。
【執筆:赤井三尋(作家)】
『WHAT IS LIFE? (ホワット・イズ・ライフ?) 生命とは何か』(ポール・ ナース著 /竹内薫訳/ダイヤモンド社)