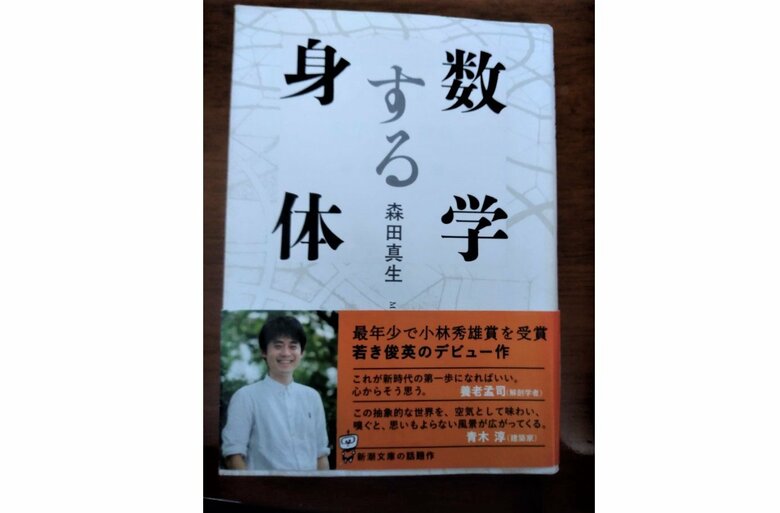リンゴの木の下に落ちているリンゴ3個と、日が昇り、沈み、また昇り沈むことを繰り返す3日は、同じ3である。だがそんな簡単なことに気づくのに、人類は気の遠くなるような時間を必要としたはずだという文章を何かの本で読んで、妙に感心したことがある。「3個」「3日」という具体的な「3」を抽象的な「3」に昇華させることによって、人は初めて「数」という概念を獲得したということなのだろう。
しかし、概念を手に入れることと、それを自家薬籠中のものにすることの間には大きな隔たりがある。小さな数字はともかく、巨大な数字は実感を伴って把握することが難しいというのも、その一例だ。
たとえば、日本の総人口はざっと1億2000万人余りだが、その数そのものの大きさ、凄まじさを実感できる人はそれほど多くはないだろう。
それを実感するために、まず一辺が1センチのやや小ぶりのサイコロを想像する。これをきっちり並べてタテ・ヨコ100個ずつの正方を作る。サイコロの数は100×100で1万個、一辺は100センチなので1m。つまりこの正方形の面積は1㎡である。サイコロを単位とすると1㎡=10000サイコロとなる。次に東京ドームあるいは甲子園球場のグラウンドを想像する。東京ドームも甲子園もそのグラウンド面積は約1万3000㎡である。つまり、そのグラウンドにすき間なくきっちりとサイコロを敷き詰めると、そのサイコロの数はほぼ日本の人口に相当する。そのさまを想像してみてほしい。思っていた以上に巨大な数であることが実感できるはずだ。
これはわたしが10年ほど前にあるウェブマガジンで書いた内容を焼き直したものだが、実感は「身体化」、あるいはその第一歩と言い換えることが可能である。
「数える」という行為
さて今回取り上げるのは、2016年に小林秀雄賞を受賞した『数学する身体』(森田真生 著・新潮社)である。
数学と聞いて拒絶反応を起こす人もいるかもしれないが、心配無用。著者は「はじめに」で以下のように述べている。
「全編を読み通すために、数学的な予備知識は必要ない。数学とは何か、数学にとって身体とは何かを、ゼロから考え直していく旅である」
実際、数学ができない代名詞のようにいわれる私学文系出身の評者でも、無事読み通すことができた。それは、その内容が、数学的というよりむしろ哲学的な傾向を示しているからだろう。たとえば「人工物としての“数”」「道具の生態系」「脳から漏れ出す」「行為としての数学」など、第一章の小見出しをピックアップしてみてもそれがわかる。
「人工物としての“数”」では、犬や鳥、ピラミッドや壺などが1つから複数描かれた絵を使って、パッと見た瞬間、その個数がわかるのはいくつまでかを調べたものだ。瞬間的に分かるのは3ぐらいまで。認知神経科学では3と4あたりを境界にして、個数を認識するのに異なったシステムが働くと考えられている。そして、数が多くなるにしたがって「数える」という行為が必要となってくる。そこで「指」という身体の一部の出番となる。
「羊の群れがいる。見ただけでは何匹か分からないので、羊が一匹通るごとに、指を一本ずつ折り曲げていく。そうして身体の助けを借りて、羊の数を捉える」
しかし手の指は10本しかないので、木や骨に刻みを入れて数を記録するようになった。漢数字の「一、二、三」、ローマ数字の「Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ」は刻み目の痕跡だろうし、アラビア数字の「1、2,3」の「2」と「3」も漢数字の「二」と「三」とほぼ同じの古代インド数字の草書体というべきものだという。そしていずれの数字も、4からは単純な刻み目とは違う形になっている。つまり先に触れた「3」と「4」を境とした認識方法の違いが、こんなところに痕跡をとどめているのである。
人工進化と2045年問題
さらに、数学そのものよりも、数学の周辺に位置する分野からもアプローチを試みている。
コンピュータの世界では「人工進化」という研究分野がある。課題を解決するために進化の手法を用いたもので、解の候補をランダムに大量発生させ、比較的優秀な解候補をもとにして「次世代」の解を作る。この世代を何代も繰り返して課題を解決するという手法である。
コンピュータは0と1の二進法によるビット列を使うが、たしかにこの列は遺伝子に似ている。選ばれたビット列を「変異」させて自己複製していくさまは「疑似進化」といえるが、ちょっと異質な人工進化の実験がイギリスで行われた。
ビット列ではなく、「物理的」なハードウェアを進化させるという試みだ。もちろんこれは著者の考えようとする「身体性」に深く関わっている。
課題は異なる音程の2つのブザーを聞き分けるというもので、それほど難しいものではない。実験はプログラム可能な論理ブロックを複数含んだ特殊な集積回路を使う。この論理ブロックはソフトウェアを使って互いに結ばれた配線を自由に変えることができる。
結果は大成功だった。4000世代の進化の後に、課題を達成するチップ(集積回路)を完成させることができた。
ところが、である。そのチップを調べてみると、奇妙な点がいくつも出てきた。
まず、そのチップは100ある論理ブロックのうち、37しか使っていなかった。これは考えられる最低限必要な数より小さい。機能するはずがない。また、使われた37個のブロックのうち、5個は他のブロックと繋がれていなかった。つまり何の関係もなく孤立していた。
そしてさらに奇妙なことに、この孤立したブロックのどれ一つ除外しても、機能しなくなるのである。
「実は、この回路は電磁的な漏出や磁束を巧みに利用していたのである。普通はノイズとして、エンジニアの手によって慎重に排除されるこうした漏出が、回路基板を通じて伝わり、タスクをこなすための機能的な役割を果たしていたのだ」
これは少しばかり不気味な光景である。人間が命じた手法以外の手法を使って、人間が気づかぬまま期待した以上の成果を上げてしまう。この実験だけですめばいいが、なんとも説明しきれない不安が残る。
「物理世界の中を必死で生き残ろうとするシステムにとっては、まさにWhatever Works、うまくいくなら何でもありなのである」
著者は触れてはいないが、おそらくこの実験結果は「2045年問題」に新たな一石を投じる。
「2045年問題」というのは「半導体の集積度は18カ月で倍になる」というムーアの法則から、2045年には人間の脳のキャパシティを超え、AIが自らプログラムを書いてさら優れたAIを生み出すシンギュラリティ(技術的特異点)がやってくるという議論だ。それ以降はあらゆる知的な営みがAIにとってかわられる可能性がある。その状況で「ソフトウェアから漏れ出した」コンピュータが「身体」を獲得したらどうなるか。与えなくとも、AIはいかなる手段を講じても手に入れるだろう。私たちはそういった時代に直面しているのである。
この著者は『計算する生命』(新潮社・1700円税別)という本も書いている。こちらのほうは哲学的な傾向はやや和らぎ、こなれた文章で数学史を一覧しているが、生身の人間と数学との関係を、特に計算という営みを通して考察する姿勢は、『数学する身体』と共通するテーマである。
【執筆:赤井三尋(作家)】