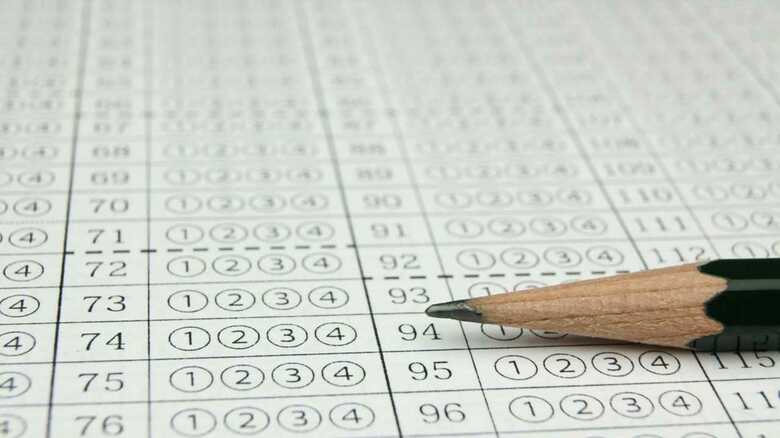「身の丈」発言に端を発した大学入試の英語民間試験の導入問題。
受験生や教育関係者だけでなく政界やマスコミを巻き込んだ騒動は、導入を5年延期することで決着すると、すでに「過去の事」として忘れ去られようとしている。
しかしここであらためて問いたいのは、今回の騒動から得られた教訓は何だったのかということだ。
「国が関わらなければ問題にならなかった」
「反省すべきところとしてあると思います。(しかし)大学入試センターが関わらなかったら、まったく問題になっていませんでした」
元文部科学相の下村博文氏は先週、都内の日本記者クラブで会見し、「拙速だったからこういう事態を招いたのではないか」との質問にこう強弁した。下村氏は文科相時代に大学入試改革の提言を行い、英語民間試験導入への道筋を作ったキーパーソンだ。下村氏はその理由をこう語った。
「実際に50%の大学が今年の春、これ(英語民間試験)を使っているわけですね。今年度は70%になるということですから、受験生には今まで通り、準備したものをそのままぜひ活用してもらいたい」

昨年度英語の民間試験を活用した大学は、国公立・私立合わせて740校中372校と半数に達している(推薦やAO入試を含む)。そして今年度はさらに増える見通しだ。
しかし今回の騒動では、「英語民間試験=公平公正に欠ける」というイメージが先行した。すでに多くの大学が英語民間試験を活用しているにも拘わらず、だ。
全国の教育現場は問題解決しようとしたのか
だが同時に下村氏は、「国が入試に関わるとなると、事情は変わってくる」と言う。
国が入試に関われば、これまで以上に公平公正が求められる。もちろん経済格差や地域格差など論外である。にもかかわらず今回文科省は、受験生に対する軽減措置や試験会場の問題を甘く見ていたのではないか。
これについて下村氏は制度設計が甘かったと認めつつもこう語る。
「今年の8月か9月になって11県の教育委員会が(会場提供に)協力すると決まりました。しかし本当は、47都道府県がそれぞれの県立高校を会場として提供し、先生方に試験官になってもらえれば、(民間試験導入は)やれたと思います」

受験会場の整備に関しては、これまで文科省が「民間に丸投げした」と批判されてきたが、都道府県の教育現場も積極的に問題を解決しようという姿勢があったのか。
国による全国一斉テストは時代に合うのか
今回の騒動を見て筆者が思うのは、国による全国一斉の学力テストが、そもそもグローバル化の時代に必要なのか?ということだ。
全国一斉テストは40年前、当時問題となっていた「受験戦争」緩和のために、「共通1次試験」として始まった(筆者はこれを経験した世代だ)。
与えられた選択肢から正解を選ぶマークシート方式は、採点の公平公正さは担保される。
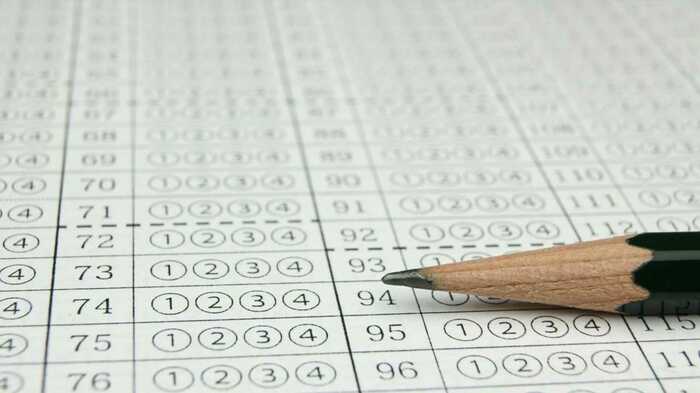
しかしこれからの社会に必要な思考力・判断力や表現力を養うものなのか、当初から疑念があった。
これを受け2020年の大学入試改革では、時代のニーズに合わせて、英語で言えば四技能、国語・数学であれば記述式問題の導入されることになった。にもかかわらず今回、英語の四技能試験を国はつくることができなかった。そして民間に託したものの、公平公正に欠けると批判され延期が決まった。
ならば各大学が独自に試験問題を作ればいいのだが、ほとんどの大学が「自分で独自に入試を作る余力が無い」(下村氏)のが現状だ。
ヒントはアメリカの大学入試制度にある
公平公正で思考力・判断力や表現力を試す入試を、今後国が行うことは可能なのか?
この一つの答えとなるのが、米国の大学入試制度だ。
米国では州や高校によって、学習指導のやり方が多様で、学力や評価基準が異なる。だから統一の学力標準テスト(「SAT」など)で、各大学は学生の学力を判定している。
しかしこのテストには国は関与しておらず、非営利団体が運営し、年に数回実施されている。

米国在住の作家で、著書「アイビーリーグの入り方」をもつ冷泉昭彦氏はこう言う。
「アメリカの大学はほとんどが書類審査で、履歴書や内申書、統一テストなど様々な要素を総合的に判断します。歴史あるアイビーリーグのような学校では面接もあります。アメリカの大学受験は、日本の就活に近いかもしれません」
米国の大学が最も重視するのは、大学独自のアドミッション・ポリシー(入学者の受け入れ方針)に学生が適合するかどうかだ。
入試では「学生がどんな人物で、高校まで何をやってきたのか」「これから大学や社会のためにどんな貢献をしてくれるか」が重要なポイントとなる。
ペーパーテストで暗記したものを埋めていく時代は、もうとっくに終わっているのだ。
入試は本来、大学が示したアドミッションポリシーをもとに、学生は自分に合った大学を選ぶものだ。だから大学が「独自に入試を作る余力が無い」と言うのは、本末転倒ではないか。
今回の騒動を通じて試されているのは、実は大学自身の入試への向き合い方なのだ。