適量はどのくらい?
弊害や依存性があるとはいえ、カフェインにはメリットもありますし、普段口にする飲料や食品に含まれていますから、どれくらいなら取っていいのかという点は気になるところでしょう。
まず主な飲料に含まれているカフェインの量を見ていくと、コーヒーは60mg/100mL。エナジードリンクや眠気覚まし飲料は製品により異なりますが1本あたり36~150mg。紅茶は30 mg/100mL。煎茶・ほうじ茶は20mg/100mLとなります(参考:日本食品化学研究振興財団「既存添加物名簿」)。
このような中、一般的には成人は1日に300~400mg程度――コーヒーであれば、平均的な大きさのコーヒーカップにして1日4~5杯まで――にするべきだと言われています。500mgを超えると、動悸(どうき)を自覚したりすることが起こってくる場合があります。

妊婦さんの場合はこれよりも少なくしたほうがいいでしょう。カフェインが胎盤を通過することはありませんが、胎盤の血管を細くするので子供の低体重などに影響する可能性があるためです。
脳が成長過程のためカフェインに反応しやすい未成年の場合は、より気を付けるべきです。特に15歳未満の場合、1日の摂取量は150~200mgに抑えてほしいですね。
ただし、成人でもカフェインに敏感な人や精神疾患を持つ人などは、カフェインの摂取で具合が悪くなってしまうことも。また動悸や過呼吸などのパニック発作が出てしまう場合があります。カフェインに対する過敏性は人によって異なる点には注意が必要です。
作用と弊害、そして依存性を念頭においてカフェインと付き合ってください。
(カフェインとの上手な付き合い方についてはこちらの記事へ)
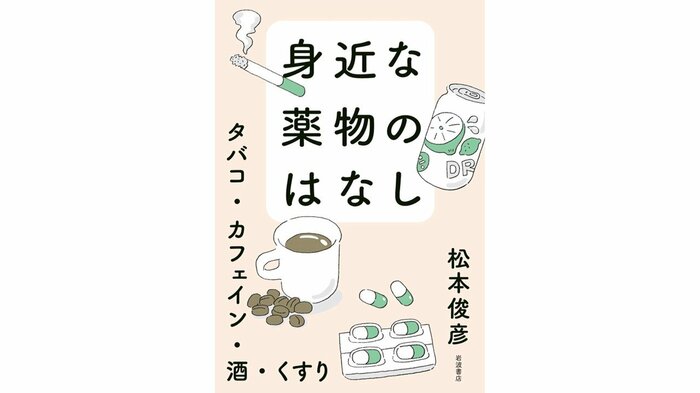
松本俊彦(まつもと・としひこ)
精神科医。薬物依存症や自傷行為に苦しむ人を対象に診療を行う。国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部部長。著書に『自傷行為の理解と援助』(日本評論社 2009)、『自分を傷つけずにはいられない』(講談社 2015)、『薬物依存症』(ちくま新書 2018)、『誰がために医師はいる』(みすず書房 2021、第70回日本エッセイスト・クラブ賞受賞)、『身近な薬物のはなし──タバコ・カフェイン・酒・くすり』(岩波書店 2025)他多数。






