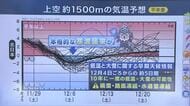岩手県久慈市山形町は、平庭高原の白樺林、東北唯一の闘牛、そして沿岸と盛岡市を結ぶ歴史ある野田街道など魅力にあふれる町です。
2006年に旧・山形村は久慈市と合併し、久慈市山形町として今も新しい魅力を紡ぎ続けています。この「山形」の由来を探ります。
岩手県内の地名を長年調査してきた宍戸敦さんによると、「『山形』は山形県と同じ漢字を書きますが、沿岸に近い低地を『川目』と呼ぶのに対し、山の方向・方面を『山形』と表現したことが由来。山形町というのは、久慈の低地の大川目から見た山の方向で『山形』と名付けられたいわれている」と話します。
久慈市山形町にある「道の駅白樺の里やまがた」には、なんとも不思議な大きな卵のオブジェがあります。
久慈市山形総合支所産業建設課の梶谷祥吾さんは「ガタゴンと呼ばれる未確認生命体の卵」と説明します。
梶谷さんによると、平成4年6月、旧山形村の畑で奇妙な足跡が見つかり、研究機関が調査しましたが、何の足跡かまだ分かっていないといいます。旧山形村の「ガタ」と怪獣のような「ゴン」を合わせ、「ガタゴン」と命名されました。今では町のシンボルとなり、毎年8月には「ガタゴンまつり」が開催され、地域に親しまれているということです。
さらに、久慈市山形町と聞いて思い浮かぶのは、江戸時代に盛岡藩が整備した「塩の道」野田街道です。三陸・野田で作られた塩を盛岡などへ運ぶ重要な交易路で、山形町はその途中に位置し、中継地として人や物が行き交い賑わいました。
町内には、この「塩の道」と関わりのある地名が今も残っています。
宍戸敦さん
「山形村の塩の道に関係する地名として大きいのは『関』という地名がある。この『関』は、例えば沿岸の野田から盛岡に牛で塩を運ぶ時に、南部藩から南部藩に行くわけだが、途中の一部分が八戸藩になっている。その八戸藩の場所(境界)が山形村の「関」ということで関所を設けたことから地名になったと言われている」
久慈市山形町霜畑地区にある「関」には、かつて関所があったことを示す「関御番所跡」が残されています。
久慈市文化財保護調査委員の嵯峨力雄さんは、「関番所という関所が置かれたことから『関』という名前がついた。ここを通過する物や人を厳しく取り調べていた」と話します。
さらに嵯峨さんによれば、この場所は葛巻・盛岡・野田・久慈などへ通じる6つほどの街道の結節点であり、交通の重要な場所だったといいます。
そしてこの山形町霜畑地区にはもう1ヵ所、塩の道の重要なポイントとしてかつて賑わっていた場所があります。それが「馬寄平」です。
久慈市文化財保護調査委員 嵯峨力雄さん
「少し葛巻寄りに進むと『馬寄平』と呼ばれる場所がある。牛や沿岸からの荷物を馬寄平で交代・積み替えを行った。盛岡や雫石の方に運んだ。牛や荷物の中継点が馬寄平だった」
久慈市山形町内に残る「関」や「馬寄平」という地名は、塩の道の歴史を今に伝えています。人や物が行き交い、にぎわった往時の姿を想像させる場所です。