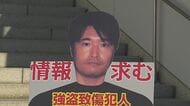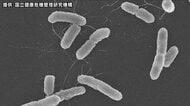秋の訪れを告げる佐久地域の郷土食「小ブナの甘露煮」。食文化を後世に残そうと9月5日、長野県佐久市の道の駅で作り方を教える講習会が開かれました。
秋の訪れを告げる佐久地域の郷土食「小ブナの甘露煮」。9月5日、佐久市の道の駅で開かれた料理講習会で作りました。
佐久地域では農家の副収入として昭和50年代に「フナの養殖」が広まりました。
小ブナは5月下旬ごろに水田に放たれた親から生まれ、3カ月ほどで4cmから7cmほどに成長します。9月ごろに水揚げされた後、各家庭では「甘露煮」として食べられ佐久地域の「秋の風物詩」となってきました。
しかし、40年ほど前は約150人いた生産者も高齢化などで年々減り今は50人ほどに。食卓に並ぶ家庭も減ってきているということです。
地域の食文化を守ろうと市は8年前から「小ブナの甘露煮」の料理講習会を開いています。
5日は15人が参加。講師を務める市内の女性らでつくる「農村生活マイスターの会」のメンバーから調理のコツなどを教わりました。
まずは生きた小ブナを水でよく洗います。
そして、しょうゆと酒を煮たたせた鍋に入れます。そして、ザラメを投入。後から入れることで光沢が出るそうです。全体に味が行きわたるようにタレを回しかけます。
農村生活マイスターの会・長岡のり子さん:
「今のうちから少しずつかけていく。これがいろいろやってみたコツですよね」
農村生活マイスターの会・矢野由喜江さん:
「あまりお玉で押さえつけないように。魚がつぶれちゃうので」
煮込むこと約50分-。
農村生活マイスターの会・長岡のり子さん:
「(鍋を傾けると)汁がとろんとして少なくなってきたから、ここでいったん食べてみて頭のところがやわらかければ出来上がりです」
水分がなくなるまで煮込んだら「小ブナの甘露煮」の完成です。
市内から:
「めちゃくちゃおいしい。あまりフナを食べるところってないと思うけど、全国から来た友達に『これが郷土料理だよ』って文化とかも伝えられたらいいなと」
「昔から受け継がれてきた味ですね。佐久市に住んでいるので1回は作ってみたいと」
(記者リポート)
「甘辛い香ばしさが口の中いっぱいに広がります。骨もやわらかく煮込まれていて、とても食べやすいです」
秋の訪れを告げる小ブナの甘露煮。地域の郷土食を後世まで残していきます。
農村生活マイスターの会・長岡のり子さん:
「次の代まで続いて食べていかれる、代々につながって、伝統料理になればいい」