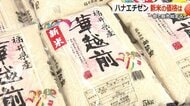終戦から80年。当時、戦場には亡くなった日本兵の遺品が数多く残されていましたが、アメリカ兵らが戦利品として持ち帰り、遺族の元へ返されたのは、ごく一部です。
そんな中、あわら市に住む男性は、譲り受けた遺品を遺族に返そうと活動しています。その思いを取材しました。
◆「子供たちに戦争の悲惨さを」と譲り受けた遺品
出征する兵士を思う寄せ書きが記された「日章旗」といわれる日の丸や、戦場で活動した軍犬の名前が書かれた日の丸。こうした旧日本兵の遺品を所有している、学習塾を運営するあわら市の吉江龍太さん(40)。
輸入業を営む知人がアメリカ人から譲り受けたもので「塾に通う子供たちに戦争の悲惨さを伝えてほしい」と吉江さんに託しました。
遺品について、塾の子供たちにこう説明します。
「戦争に行った人の名前がここに書かれている。周りには仲間の寄せ書きがあって『頑張ってね、戦争に行っても忘れないよ』っていう思いが込められているんだね」
吉江さんは、どうにかして遺品を遺族の元に返したいと手を尽くしてきました。
◆日章旗を“お守り”に戦地へ
“寄せ書き日の丸”ともいわれる日章旗は、出征する兵士の戦場での活躍を願うもので、家族や親戚、近所の人たちが自分の名前を書きました。「無事に帰ってきてほしい」との願いが込められています。
兵士たちは、この日の丸をお守り代わりに、戦場に赴きました。
クボカワオキヒデさん、あるいはキシュウさんとも読める名前が記された日章旗には約70人の寄せ書きがあり、「武運長久」のほか「義勇奉公」「天壌無窮」など国家を第一とする言葉が並びます。
吉江さんは「これだけの人が名前を書くということは、これだけの期待を背負って戦争に行っていたということ。この出征旗は、生きた証しとして遺族に返還できたらと思う」
クボカワさんの名前を頼りに靖国神社、日本遺族会などにも問い合わせましたが、現在のところ有力な情報もなく遺族は見つかっていません。
◆戦地に赴いた軍犬の日章旗も
あまり目にすることがない軍犬の日章旗もあります。「チルダ」という名前のイヌが軍で訓練を積み、日の丸を背負って戦地に赴いたと考えられます。
日本の軍犬について県立歴史博物館の橋本紘希学芸員は「日中戦争からアジア太平洋戦争が終わるまでの間に、大体5万頭から10万頭が動員されたと聞いている。例えばシェパードなどが軍隊に連れていかれ、そこで敵を偵察したり、部隊間の伝令などで使われていたと言われている」と話します。
◆けがをして放たれた軍犬も
5年前、福井テレビが取材した元陸軍兵の小林信さん(当時97)は、戦場で行動を共にしていた軍犬について証言していました。
戦争体験者の小林信さん:
「軍用犬が2頭いたが、それが砲弾の音で耳から空気が入って、バンと当たって目玉が飛び出してクンクン鳴きながらいる姿は本当にどうしてやることもできず…自分たちが生き延びるのに精一杯で、イヌには何もしてやれなかった」
学芸員の橋本さんは「戦場で病気になったり、けがをしたりして、その場で放たれるという場合もあったようだ。仮に生き残ったとしても、やはり戦後の混乱の中でその場で置き去りにされることがあったようだ」と話します。
◆「ぜひ返してあげたい」
吉江さんは、戦場の遺品を見ながら塾の生徒たちにこう語りかけました。
「日章旗には、帰ってきてほしいという気持ちもあったはず。もちろん戦争に勝って欲しいという気持ちもあかもしれないが、これが、もう最後の渡すものになってまうかもしれないんだから…やっぱり、遺族に返すというのは大事だと思う」
続けて、軍犬の日章旗見ながら「イヌって、(戦地に)行きたいか行きたくないか選べず、何も反抗できずに連れて行かれた。そのイヌが生きた証、頑張った証」と言葉に思いを込めます。
吉江さんの話を聞いた中学生は―
「戦争となると、いい思い出はないからつらいし、戦争はやめたら世界が平和になると思う」
「イヌは無関係だけど強制的に連れて行かれるのって、かわいそうだと思う」
「アメリカまで行っても(遺品が)こうやって戻ってくることも素敵だし、遺族もやっぱり帰ってきてほしいものだと思うので、ぜひ返してあげたい」
終戦から80年。遺族の世代もかわり、遺品の返還は難しくなっている現状もあります。
これからも捜索を続けるという吉江さん。子供たちのためにも、戦場に残された「生きた証」を返還したいと強く願っています。