中国・北京市でアステラス製薬の日本人社員がスパイ罪で懲役3年6月の有罪判決を受けた。
この事件は、中国の反スパイ法に基づく邦人拘束の一例であり、近年、同様の事案が相次いでいる。
問題は、反スパイ法の曖昧さにより、何が違法行為とされるのかが明確でない点にある。この不透明さは、中国に進出する日本企業にとって重大なリスクとなり、ビジネス環境の不確実性を増大させている。
反スパイ法の曖昧さと日本企業への影響
中国の反スパイ法は、2014年に制定され、2023年に改正された。
この法律は、国家の安全を保護する目的でスパイ行為を広範に定義するが、具体的な違法行為の基準が不明確である。例えば、企業活動における情報収集や市場調査が、意図せず「国家機密の窃取」と見なされる可能性がある。
アステラス製薬の社員のケースでも、具体的な違法行為の内容は明らかにされておらず、企業側が事前にリスクを回避することは極めて困難である。
この曖昧さは、日本企業にとって予測不可能な法的リスクをもたらす。
中国に進出する企業は、通常のビジネス活動が当局の恣意的な解釈によってスパイ行為とみなされる恐れがある。

特に、医薬品やハイテク産業など、技術やデータの取り扱いが重要な業界では、日常的な業務が当局の監視対象となりやすい。このような環境下では、企業はリスク管理に多大なコストと労力を割かざるを得ない。
さらに、反スパイ法の運用は、中国国内の政治的・社会的状況に大きく影響される。米中対立の激化や台湾問題を背景に、中国当局は外国企業や外国人に対する監視を強めている。
日本企業は、こうした地政学的緊張の高まりの中で、意図せず当局の標的となる可能性がある。この状況は、日中関係の悪化と連動しており、企業活動の自由度をさらに制約する。
地政学的視点から見た日中関係の課題
日中関係は、経済的な相互依存関係が強い一方で、地政学的な対立要因も多い。中国の太平洋進出や南シナ海での領有権主張、台湾有事を巡る緊張は、日中間の信頼を損なう要因となっている。

特に、台湾問題は、日本にとって安全保障上の重大な関心事であり、中国の軍事的な動きが活発化する中で、日中間の対話は一層複雑化している。

米国との関係も、日中関係に大きな影響を与える。米中間の戦略的競争が激化する中、日本は米国との同盟関係を強化しつつ、中国との経済的結びつきを維持する必要がある。
このバランスを取ることは容易ではなく、米中対立が先鋭化すれば、日本企業は中国市場での活動においてさらなる圧力に直面することが予想される。例えば、中国への先端半導体輸出規制のように、米国が中国に対する経済制裁や技術輸出規制を強化し、日本が米国と足並みを揃えるような行為に出た場合、中国側は報復措置として日本企業への監視や規制を強める可能性がある。
また、中国国内の治安当局による日本人や日本企業への監視圧力は、日中関係の温度感に左右される。関係が良好であれば、当局の対応も比較的穏健になるが、関係が冷え込むと、日本人駐在員や企業活動に対する監視圧力が強まると考えられる。
我々は、個別の事案が政治的な意図や地政学的文脈の中で解釈される可能性を常に念頭に入れておくべきだろう。
日中関係の後退リスクと日本企業の対応
日中関係の後退リスクは、複数の要因によって高まっている。
まず、中国の太平洋進出に伴う軍事的緊張は、日本を含む周辺国との摩擦を増大させる。中国が海洋進出を加速させる中で、日本は自国の安全保障を強化する必要があり、これが中国との関係にさらなる政治的緊張をもたらす可能性がある。

次に、台湾有事を巡る不確実性は、日中間の対立を一気にエスカレートさせる要因となり得る。仮に台湾海峡で軍事衝突が発生した場合、日本企業は中国市場での事業継続が極めて困難になるだろう。
また、米中関係の悪化は、日中関係に間接的な影響を及ぼす。中国が米国との対立を深める中で、日本企業が「西側」の一員として標的にされるリスクは無視できない。
このような地政学的環境下では、日中関係が現状維持すら困難になる可能性があり、企業活動のリスクは一層増大する。

こうした状況を踏まえ、日本企業はリスクヘッジの観点から戦略的な対応を視野に入れておく必要がある。
まず、駐在員の数を可能な限り最小限に抑えることが重要となる。駐在員の削減は、人員の安全を確保するだけでなく、企業が現地での活動を縮小する際の柔軟性を高める。
また、現地採用の強化やリモートワークの活用により、駐在員の数を抑えつつ事業継続を図ることも有効策だろう。
また、日本企業は中国市場への依存度を下げる戦略を検討すべきである。中国は依然として重要な市場であるが、今後の日中を取り巻く地政学リスクを考慮すると、事業の多角化や代替市場の開拓は重要な選択肢となる。東南アジアやインドなど、成長が見込まれる市場へのシフトは、リスク分散の有効な手段となり得る。
今後の展望と日本企業の戦略的選択
日中関係の今後は、地政学的要因によって大きく左右される。
中国の太平洋進出や台湾問題、米中対立の行方は、日本企業にとって予測不可能な変数である。これらの要因が重なり合う中で、日中関係が今後後退するリスクは十分にあり、日本企業はそれを意識した危機管理対策、ビジネスモデルを検討するべきだろう。
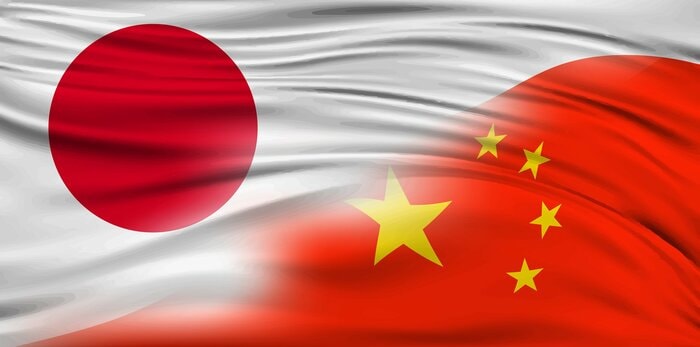
中国の反スパイ法による邦人拘束は、日本企業にとって大きな不安材料だ。
日中関係は、地政学的要因により今後後退リスクが十分に考えられ、台湾有事や米中対立の影響は無視できない。日本企業は、駐在員数の最小化や市場の多角化を通じて、リスクヘッジを進める必要がある。
同時に、中国市場の重要性も考慮し、事業継続とリスク管理のバランスを取る戦略が求められる。
地政学的視点から日中関係の不確実性を見据え、柔軟かつ戦略的な対応が日本企業の今後の成功を左右するだろう。
(執筆:株式会社Strategic Intelligence代表取締役社長CEO 和田大樹)






