「年功型」の組織の割合は、この「入社からの年月」と「年齢」と「組織の中での地位」の3つがそろって上昇していきますので、その秩序が安定しています。
「年輪」と「年功」が重なっている状態だからです。しかし、「脱・年功」が進み、年齢と役職が紐づかなくなる一方で、「何年に入社したか」という「年輪」を重視する人間関係は相変わらずこびりついています。
この「年輪」と「年功」にギャップが生まれるとき、上司にとっても部下にとってもコミュニケーションがギクシャクしはじめるのです。
混乱が起こる3つの要素
さらに「入社の年輪」と「生まれて何歳である」という「加齢の年輪」と、「組織内地位」という3つの要素にギャップが生まれたとき、人間関係はかなり混乱します。
タメ口と敬語のどちらが適切なのか、「部長」「課長」などの役職呼びをすべきか、「くん・さん呼び」かといった言葉遣いの秩序も乱れます。

「年功」は人事制度によってコントロールできますが、この「年輪型」の秩序は制度で消し去ることができず、悪さをし続けます。
「年輪型」社会に生きる日本人は、「年上の人」のことを先輩的に扱い続けつつも、指示系統としては立場が上になることによって、気苦労が絶えない状態になります。
「上下関係が逆転するときに従ってくれない、非協力的な人間がいる」(46歳、男性、医療・介護)
「部下と言いながら、歳が10以上も上で、文句ばかり言って言うことを聞かない」(49歳、男性、製造業)
このような現場からの声は枚挙にいとまがありません。これは、学術的に言えば「エイジズム」の問題です。マネジメントも、職場も、年齢によって期待値が異なります。
「年齢が上であるのにも関わらず、成果が少ない」「年を取っているのにもかかわらず仕事ができない」といった偏見です。
パーソル総合研究所の調査によると3割の若手社員が、自社のシニアに対して「給料を貰いすぎ」「成果以上に評価されている」と感じています(※)。
こうした「年上部下」をマネジメントする管理職トレーニングを実施している企業も、エイジズムの問題についてきちんと研修を行っている企業も、極めて少数です。管理職は「習ったこともない」コミュニケーション・ギャップに悩み続けています。
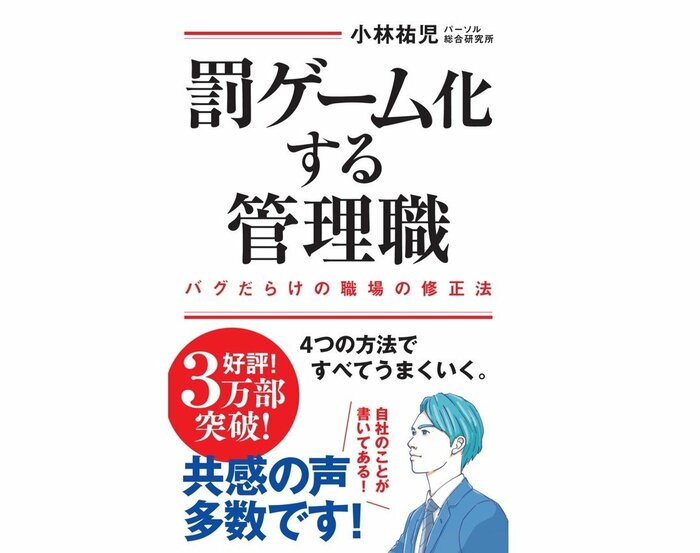
小林祐児
パーソル総合研究所主席研究員/執行役員 シンクタンク本部長。労働・組織・雇用に関する多様なテーマについて調査・研究を行っている。専門分野は人的資源管理論・理論社会学。
(※)パーソル総合研究所 「シニア従業員とその同僚の就労意識に関する定量調査」






