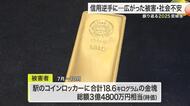3月11日で東日本大震災の発生から14年、様々な角度から震災を見つめるシリーズ「あの時、そして今」です。震災発生直後、宮城県内では亡くなった人の火葬が間に合わず「仮埋葬」として一時的に遺体を土葬しました。当時のあまりに厳しい現実、そして、残された教訓と課題を考えます。
「このへんだな」
石巻市の今野浩行さん(63)。東日本大震災で亡くなった父・浩さん(当時77)を「仮埋葬」としてこの山に一時的に土葬しました。
今野浩行さん
「やっぱりきちんと火葬してやりたかった。埋めておけば腐ってしまうし。ただ、あの時はしょうがなくて」
東日本大震災では県内の火葬場の能力をはるかに上回る人が亡くなりました。火葬場の被災に加え、遺体を運ぶ車や火葬に必要な燃料も確保がままならない状況に。
被災した自治体からはすぐさま、仮埋葬、つまり一時的な土葬で対応する必要があると声が上がりました。結局、県内では発生10日後の3月21日から6月まで、2108人が仮埋葬されました。
今野浩行さん
「お墓も駄目になったし、遺体をどこに持っていけばいいのかわかんなくて。それで行政と、もめたことがあって。『遺体引き取ってもらえませんか』と言われ、ただ家もないし、置き場所もないし、避難所のロビーに置いていいのかと。そういうことでけんかになったりもしたけど。やっぱ行政も対応をどうしたらいいか分からなくて、やっぱりその中で土葬というのはしょうがないと思うし、あの時はそれが最善の手だったのかなと」
今野さんは浩さんのほかにも、母・かつ子さん、長女・麻理さん、次女・理加さん、長男・大輔さんを亡くしました。
父の浩さんが見つかった震災発生直後、県内で火葬できるのは1日50人程度でした。5月以降はほとんどの遺体を県内で火葬できるようになりましたが…。
今野浩行さん
「親父が見つかって、おふくろが見つかっていなくて、一緒に火葬をしてあげましょうと、夫婦だから、そう考えて親父を土葬にしてしまったというかな。結構周りの人からも言われた、『なんで土葬にしたのか』と、おふくろと一緒に火葬しようと思ったら、おふくろと長女がほぼ同時に見つかって。それでおふくろと長女を一緒に火葬したから、親父だけがここに残ってしまった」
行政の対応も困難を極めました。
県の武者光明企画部長は、当時、墓地や埋葬を担当する課で対応にあたりました。発生直後、県警からは、「遺体は3週間で傷むため、それまでに一定の対応を考えてほしい」と言われていたと話します。
県 武者光明企画部長
「3月11日からの3週間なので3月末ぐらいまでに、何千という遺体、亡くなった方々を荼毘(だび)に付すことは、非常に難しい状況になってきていて、ある時、自治体のほうから、『もう火葬は無理なので埋葬を本格的に実施したい』と話があり、市町村がそこまで覚悟を決めてやるのであれば、県とすれば一生懸命応援するしかない、やってあげるしかないだろうと始まった」
県は対応を急ぎ、手順などをまとめたマニュアルのたたき台を震災発生3日後には完成させました。
県 武者光明企画部長
「せめて火葬ができないのであれば、棺(ひつぎ)ぐらいは全国にお願いして集めて、確保しようということで、一生懸命やっていました。冷たい海の中、津波の中で亡くなった方々を冷たい土の中に埋葬することは、遺族にとってはとてもとても辛いかったと思う。遺族の心中を察することがやっぱ一番辛かった」
火葬は他県にも協力を求め、最終的には、9道都県が2559人を受け入れ、武者部長は「本当に助けられた」と振り返ります。
一方で、想定していなかったことも起きていました。当初2年は埋葬しておく想定でしたが、火葬場の復旧に伴い掘り起こして火葬する「改葬」の動きが出ていたのです。
県 武者光明企画部長
「最初それを聞いたとき『え、掘り起こすのか』と思ったが、遺族からすると当然の気持ちだと。やっぱり夏場から秋口にかけてはかなりご遺体の傷みもひどかったので、掘り起こした事業者も、とても大変な思いをしたと聞いているし、掘り起こしてから体を洗ったり、でも遺族に見せられない状態なので、火葬してお骨になった段階で引き渡したと聞いていた。とても大変な作業だったと思う」
こうした経験から武者部長は、「しないで済むのであれば、土葬という選択肢は避けるべき」と考えています。改葬は2108人全員について行われ、11月にすべて終わりました。
大規模災害時、遺体の火葬をどうするのか。東日本大震災の時点では、岩手、宮城、福島を含む38道府県で、広域火葬計画が策定されていませんでした。
広域火葬計画とは近隣都道府県を含めて火葬場の所在地や能力を事前に把握し、棺やドライアイス、遺体を運ぶ車両の確保などを事前に決めておくものです。
東日本大震災のあと、国の要請を受け、おととし3月までにすべての都道府県で策定されました。
防災政策の専門家は「策定の意義は大きい」と評価します。
東北大学災害科学国際研究所 丸谷浩明教授
「対応の優先順位は当然命を救うことが、最大の問題となるので、遺体の対応はやや遅れ気味になってしまうというのを、あらかじめ協定を結んでおくことによって、対応が早くなることは意義が大きい」
その一方で、全てが解決されるわけではなく、南海トラフ地震など広範囲で多くの犠牲者が想定される災害では、結局、物資の数や搬送の問題などは残ると指摘します。
そのうえで、行政には、「仮埋葬を前提としないものの、選択肢の1つとして残す覚悟も必要だ」と話します。
東北大学災害科学国際研究所 丸谷浩明教授
「全て火葬に回せるわけではないだろうという条件がある以上は、行政はどういう段取りで、何をするべきなのかということは、学んでおくべきだと思う。大混乱になると遺体対応で、さらに遺族が悲しい思いをすることもある。仮埋葬の方法はある程度確立して、体制も整っていないといけない」