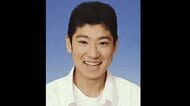陸上養殖に大手企業の参入が相次ぐ中、NTTコミュニケーションズが陸上養殖システムの販売に乗り出す。バクテリアを使わない独自技術で効率的な養殖を可能にし、食料自給率向上や地域活性化を目指す。
NTTの技術で効率的な陸上養殖を実現
NTTコミュニケーションズは、情報通信技術を活用し、水質などを魚の種類に応じて管理する陸上養殖システムの販売を開始すると発表した。

バクテリアを使わないろ過技術により、狭い水槽でも多くの魚を育てることができるとして、まずは沖縄の高級魚アーラミーバイなどハタ類の養殖から始めて、順次種類を増やすことにしている。

NTTアクア・山本圭一社長:
陸上養殖はそれ(生産環境)をコントロールすることができるので、生産計画も立てやすいですし、なにより在庫数が分かる。そういう意味では企業参入しやすいのは、陸上養殖ではないかなと。
魚介類の4割を輸入に頼る中、陸上養殖を巡っては商社など大手企業の参入が相次いでいる。
NTTコミュニケーションズは、システム販売により参入へのハードルを下げ、食料自給率の向上や地域活性化につなげたいとしている。
大企業だからこそ取り組めるプロジェクト
「Live News α」では、エコノミストの崔真淑(さい・ますみ)さんに話を聞いた。
堤礼実キャスター:
陸上養殖のシステムを販売するということですが、どのような背景があるのでしょうか。

エコノミスト・崔真淑さん:
日本では食用魚介類の自給率が2023年度で50%ほどと年々減少傾向にあるため、そうしたことを補いたいという狙いがあると思います。輸入品に頼る割合が増え続けるということは、日本国民が魚を食べ続けるには、為替リスクにさらされ続けることになります。
また、地政学リスクが高まっている昨今では、食料安全保障という視点からも自給率を高めることは必須です。従来の対策としては海上養殖があるんですが、環境問題や、台風などの不確実性が増す中で、あまり現実的でないと思うんです。
今回の陸上養殖というのは、CO2排出や環境負荷を考慮しても、持続可能性を高めるためには非常に面白い取り組みだと思います。
堤キャスター:
異業種の大手企業参入が相次いでいるのは、なぜでしょうか。
エコノミスト・崔真淑さん:
なぜ水産業社以外が取り組むかについては、ファイナンスの視点からも見えてくるものがあると思っています。
大規模な陸上養殖は莫大な資金力が必要になるため、大企業だからこそ取り組めるプロジェクトでもあります。なので、最近ではNTTやソフトバンク、JRなどが陸上養殖に参入しています。
こうした大企業の多くは、現預金を新たな投資先に振り分けられず、新たな投資先を見つけて資本効率を高めることが株主から求められているんです。
だからこそ、世界で魚類の消費量が増えている中で、新規事業に参入したい、そんなインセンティブがあるのかなと思います。
“国策に乗る”新規事業拡大に重要な視点
エコノミスト・崔真淑さん:
そして、もう一つ重要な視点があります。実は、政府が2032年度までに食用魚介類の自給率を94%にまで引き上げたいという目標を掲げているんです。
新規事業を拡大するには、国策に乗るというのは経営においても重要な視点となります。政策のトレンドに乗りたいという大企業参入がさらに増えるのかなと私は想像しています。

堤キャスター:
通信の技術や、これまでのノウハウを生かして、水産業の盛り上がりや、食料自給率の向上につながることを期待したいです。
(「Live News α」12月2日放送分より)