マイナ保険証利用は100人中たった5人
病院に行って健康保険証でなくマイナンバーカードを出すと、昨年までは「すみません、機械がまだ来ないので受付けできません。保険証お持ちですか」と言われることがよくあったのだが、年が明けてようやくそんなこともなくなった。

マイナ保険証が根付いたのかなとも思ったのだが、一方でマイナ保険証を取得できない人、したくない人のため、保険証の代わりになる「資格証明書」を取得しやすくなった。
12月には普通の保険証が廃止され、形式的にはマイナ保険証のみになるのだが、実際にはマイナ保険証なしに保険医療を受けられる。これではマイナ保険証は普及しないのではないかと薄々思っていたのだ。

案の定、2月6日付けの朝日新聞に「マイナ保険証利用、国家公務員も低迷。利用訴える厚労省は4.88%」という記事が出た。
あれだけ国民にマイナカードと保険証を合体させると言っている厚労省の官僚100人のうち、マイナ保険証を使っている人はたった5人しかいない。ずいぶん国民をナメた話ではないか。
政治家と官僚が国民をナメている

これについて武見敬三厚労相は6日の会見で「国家公務員はもっと頑張らなきゃいけないな。これではまだ低すぎる」と語ったという。頑張らなきゃいけないな、か。ずいぶんのんびりしてますな。
筆者は高齢者にこそデジタルは必要なものだと思っている。だからマイナカードについてもこれまでその必要性を説いてきたつもりなのだが、厚労相がその程度の認識ならもう言うのやめようかな。

そう言えば一昨年、ある野党の議員が菅義偉内閣の政務3役はマイナカードを持っているのかという質問主意書を出したことがあった。答えは77人の政務3役のうち10人が持っていなかった。
政治家や官僚が「マイナカードはデジタル社会にとって必要だ」と言うから、筆者は7年前にマイナカードを取得し、1度更新もした。いちいち区役所に行かねばならずホントに面倒くさかった。マイナ保険証の手続きもすぐにした。
だが実は政治家も官僚も、マイナカードやマイナ保険証は別にあってもなくてもいいと思っているのではないか。
アナログ日本でいいんじゃないの?
マイナカードやマイナ保険証が根付かないのは、デジタルを「敵視」する高齢者の問題なのかと思っていたのだが、どうやら違うようだ。推奨している側の政治家や官僚に当事者意識がないことが理由だったのだ。
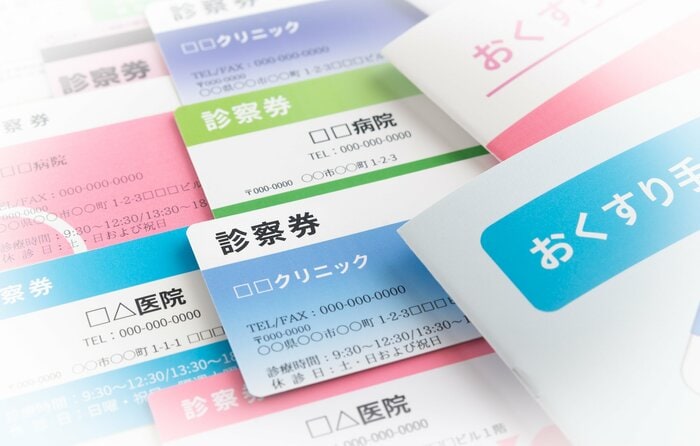
たとえば病院にマイナカードを持って行き、受付けしても、それだけではすまない。診察券を出せ、問診票も書けという。薬局に行くと、おくすり手帳を出せ、問診票を書けという。そういうのはマイナになればなくなると思っていたのだが昔のままで、理由を聞いても誰も教えてくれない。これではマイナ保険証を使う人は増えないだろう。
これは厚労省および医療業界の意識の問題だと思うのだが、他のマイナカードを使えるサービスも一事が万事こういう感じだ。

マイナカードを「持っていれば得をする」のであれば使う人も増えるかもしれない。マイナ取得にポイント還元というのもあったし、政府は例えばマイナカードを提示すればショッピングや飲食で割引、という制度を考えているという。
それはそれでいいと思うが、「持っていれば得」には限界があって「持ってないと損」にしないとだめだと思う。だがそれは日本においては無理だろう。

結論から言うと日本にはマイナカードも、マイナ保険証も、そしてデジタルそのものも、しばらくの間は限定的にしか使われないと思う。それは日本がアナログでも十分に便利な国だからだ。おそらく今年65歳になる筆者が生きている間、この国はアナログのままなんだろうな。






