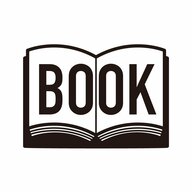効率性を求める消費行動を指す「タイパ(タイムパフォーマンス)」。
最近はなじみのある言葉として定着し、意識してみたり、口に出して使っていることもあるだろう。
だが「タイパ」を求めることは合理的なのだろうか。ニッセイ基礎研究所生活研究部研究員・廣瀬涼さんの著書『タイパの経済学』(幻冬舎新書)から、一部抜粋、再編集して紹介していく。
1日24時間は変わらないのにあふれる情報
今から10年以上前に流行した「コスパ(コストパフォーマンス)」。支払った費用(コスト)とそれにより得られる効果(パフォーマンス)を主観で比較した際に、安い費用で高い効果が得られれば「コスパがいい(高い)」となる。
例えばコスパは「お金がないから安いものを求める」という行動は合理的だ。
一方、タイパにおいては「時間がないから時間のかからないものを求める」という行動は、一見合理的に思えるが、ファスト映画のように本編を見ずに内容を知って満足するという行動に合理性があるとは思えない。
2020年、世界のデジタルデータの年間生成量は59ZB(ゼタバイト)を超え、2025年には180ZBに到達すると予想されている。
私たちになじみ深いGB(ギガバイト)で換算すると「1ZB=1兆GB」となり、180ZBが途方もない数字であるとわかるだろう。昔よりも圧倒的に処理しなくてはいけない情報が増えているのだ。

「1日24時間」は変わらないのに、消費者はYouTubeをはじめとした動画プラットフォームやサブスク、SNS、あわせて従来のメディアであるテレビ、マンガ、ゲーム、雑誌、音楽も消費しなくてはならない。
情報がありあまるなかで、時間的な制約が存在しているともいえる。
しかし、情報があふれているからといって、それを必ずしも消費しなくてもよい。
また、YouTubeやTikTokの視聴にしても、Twitterのタイムラインを遡るにしても、私たちは惰性的に時間(情報)を消費している側面がある。
目的を持って消費を行っているわけではなく、ただ流れてくるものを受動的に消化し、「明日も早いしそろそろ寝るか」「そろそろ最寄り駅だ」「頼んだラーメンが出てきた」と、消費(視聴など)をやめるきっかけも自発的というよりは外部要因によるもので、コンテンツの消費は行動と行動の間をつなぐ側面も大きくなっている。
明確な目的もなく、情報やコンテンツを受動的に浴びている現代の消費者は、なぜ時間の消費に対して効率性を追求するのだろうか。
節約した時間は有効的に使えているのだろうか?
「タイパ」で生まれた時間を有効活用できているか
消費者は経済的制約があるなかで、「どうせ消費するモノなのだから」お得に済ませて、余剰を増やしたり、最大限の効用を得ようとすることは、合理的な消費行動といえるだろう。
ざっくり言えば、コスパはお金に余裕がないから、お得に消費したいから追求されているわけだが、タイパは時間がないわけではないし、節約した時間を有効的に使うわけでもないのに追求されているのだ。
例えば、ジムに通ったり、能動的な趣味に使ったり、家事に回すなどといった目的があるわけではないのに、一般的に必要と思われる消費の過程すら省いてまでも、時間を節約しようとすることは合理的といえるのだろうか。
タイパの概念が広く認知されるようになったきっかけは、若者を中心に行われていたファスト映画や倍速動画視聴文化が顕在化したことにある。
ファスト映画は映画の映像を無断で使用し、字幕やナレーションをつけて10分程度にまとめてストーリーを明かす違法動画のことで、著作権法違反で2021年6月に初めて逮捕者が出ている。
この若者の動画視聴方法の姿勢に関しては、2022年4月にライターの稲田豊史氏による『映画を早送りで観る人たち ファスト映画・ネタバレ――コンテンツ消費の現在形』(光文社新書)で深く論じられており、メディアでその問題が取り上げられるきっかけを生んだといえるだろう。
日本トレンドリサーチの「WEB上の動画に関するアンケート」(2021年)によれば、ファスト映画の視聴経験がある人は全体の9.3%であった(そのうち「違法と認識したうえで視聴した」割合は15.6%)。
もちろん、著作権法違反であると認識している視聴経験者が素直に「ある」とは回答しないだろうが、それでも「ある」の割合は大多数とはいえないだろう。

しかし、皆さんも以下のような経験はないだろうか?
・ネット広告でたまたま目に入ってきたマンガの一部を読んで、課金したくないけど結末が気になるからネタバレサイトやレビューを探す
・ドラマや音楽番組を見逃したので、Twitterで検索して違法アップロードの切り抜き動画を視聴し、タイムライン上の話題についていこうとする
・映画視聴前にTwitterであえて他人の感想やネタバレ投稿を見てから、映画館へ足を運ぶ
これらの事例も、あえて内容を知るために著作権法を犯したり、あえて新鮮さを放棄してコンテンツの中身を知ろうとしており、ファスト映画と根底にある消費欲求は同じといえるだろう。
例えば、映画の楽しみは映像美、内容、役者の表情、音楽、間など、さまざまな要素が挙げられるだろうが、それらを全部無視して、要約されたコンテンツを消費するということは、端的に言えば初見の感動を放棄してまでもタイパを追求していることになる。
それは映画の楽しみそのものを放棄することになるわけで、内容を知ったうえで視聴したり、倍速で視聴したり、そもそも内容だけ知って観た気になるという消費行動そのものはまぎれもなく非合理的な行動といえるだろう。
でも、その非合理的なことが求められてしまっている。これは、コンテンツが鑑賞(芸術)対象から消費(消化)対象になっているからに他ならない。
タイパを重視するあまりコンテンツを消費するような傾向になりつつある今、その背景にあるのが「圧倒的なコンテンツ量」にある。
そして、私たちが膨大なコンテンツを受け取るようになったからこそ、「事前にネタバレを読む」ということも起きている。
#2では、なぜ人はネタバレを読むのか、考察していく。
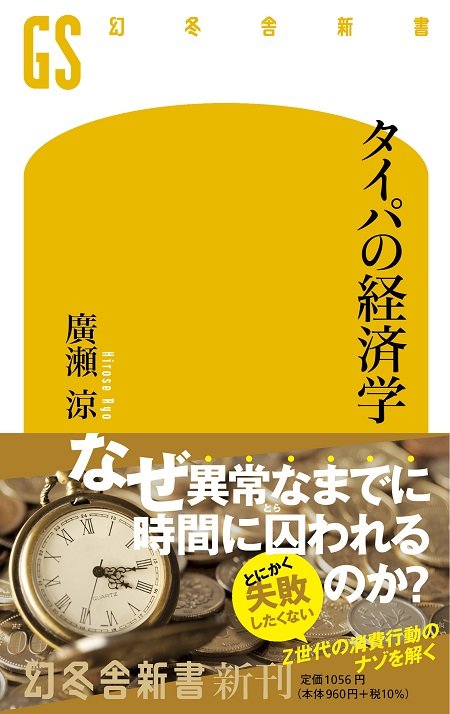
廣瀬涼
ニッセイ基礎研究所生活研究部研究員。専門は現代消費文化論。著書に『あの新入社員はなぜ歓迎会に参加しないのか Z世代を読み解く』(金融財政事情研究会)がある。