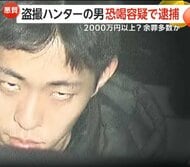物価高対策として行われている、電気やガス料金などへの補助について、政府の経済財政諮問会議が「段階的な縮小・廃止」を提言した。
経団連の十倉会長ら民間議員が提言したものだが、街では波紋が広がっている。
なぜこのような提言がなされたのか、第一生命経済研究所の永濱利廣首席エコノミストに聞いた。
9月末には物価が落ち着くとの期待
ーー物価高対策はそもそも何のため?
ロシアのウクライナ侵攻を受けて、世界的に食糧、エネルギーの値段が上がってしまったため、ガソリンや電気、ガス料金の負担が増えてしまいました。
そこで、生活をサポートするために政府が打ち出した支援策となります。
当初の予定では、今年の9月末が期限なので、延長しなければ10月以降は電気・ガス・ガソリンの負担が増えてしまいます。

ーーなぜ9月末が期限?
政府の見立てとしては、例えば、原油先物価格などを見れば去年の夏ぐらいがピークで、その後かなり下がっていたので、おそらく9月末ぐらいになればかなり物価も落ち着いているだろうと考えたんだと思います。
逆に言うと、今年度の後半になれば、物価の上昇よりも、賃金の上昇の方が上回るだろうという期待があったので、期限を9月末にしたのだと思います。
“実質賃金”は14カ月マイナス
物価高対策の中身を見ると、政府が負担している電気・ガス料金への補助金は、東京電力管内の標準的な家庭で1カ月1820円。
東京ガスのモデル世帯で900円と、合わせて毎月約2700円にのぼる。
20日の経済財政諮問会議では、「今後賃上げなどで、実質賃金がプラスになることが期待できる」として、物価高対策を「段階的に縮小・廃止すべきだ」と提言された。
しかし永濱さんは、「少なくともあと半年は継続する必要がある」と指摘する。

ーー賃上げは起きている?
今年の春闘では、30年ぶりの賃上げ率が実現したということで、賃上げ自体は進展してます。
ただ、物価が予想よりも減速していなくて、直近の賃金データを見ると、“実質賃金”は14カ月連続マイナスになっています。
30年ぶりの賃上げは実現しましたが、それ以上に物価上昇が進んでいるので、実質賃金という意味では、1年以上マイナスが続いているという状況になります。

ーー物価と賃金の関係はどうあるべき?
国の経済というのは、物価と賃金が相互依存的に上がっていく状況で、かつ、物価上昇よりもやや賃金の上昇が高いというのが望ましい姿です。
ただ今の日本は、ようやく賃上げが動き始めた状況で、まだ物価上昇の方が高い水準になっているので、もう少し物価上昇が落ち着いて、賃金上昇が上回ってくるまでは、日本経済は厳しいのかなと思います。

ーー賃上げだけで年金受給者などにも対応できる?
実際に賃金が上がれば、それに応じて年金も上がると思いますが、賃金上昇が物価上昇を上回るところまでは物価高対策を延長して、家計を支えるべきだと私は思います。
なので、少なくともあと半年は続ける必要があります。
半年経ったタイミングで、賃金上昇が物価上昇を下回っている状況であれば、さらに延長した方がいいし、逆に、賃金上昇が物価上昇を上回るような状況になっていれば、段階的に縮小を始めるべきだと思います。
物価高対策の延長に期待
補助金の縮小・廃止は、あくまでも賃上げが前提で、さらに、物価上昇を上回る状況でなければ、制度は延長すべきだと永濱さんは話す。

ーーなぜ9月末で終わらせようとしている?
30年ぶりの賃上げが実現したのと、“財政の規律”を重視する側面が諮問会議では強いということです。
ただ、昨年度の税収は、当初の予算ベースよりも6兆円以上も上振れをしていて、かなり物価が上がったことで民間が税金をたくさん納めてる状況にあるわけです。
そういう中で、賃金上昇が物価上昇に対して不十分な状況であれば、その一部を還元するという意味でも、物価高対策は延長すべきだと思います。

ーー諮問会議は政府の意向を反映する?
民間議員の意見を聞きながら、政局なども占って、総合的に岸田政権が判断することだと思います。
今回、民間議員から、いわゆる物価高対策を「もう終了したほうがいい」という意見が出たとしても、まだ決まったわけではないので、個人的には延長されることを期待しています。