性教育に関して国連のユネスコは、身体や生殖のみでなく、ジェンダー平等や性の多様性など、人権尊重をベースに幅広いテーマを扱う「包括的性教育」を提唱している。しかし日本ではいまだ性教育にこうした視点がほとんど見られない。包括的性教育に取り組む現場を2回にわたって紹介する。
幼稚園で年長さんに「命の教育」を行う
「皆は産まれる準備をしていました。どこで?」
「ママのお腹の中!」
「そのころ自分の大きさってどのぐらいだと思う?砂の一粒より小さかったんだよ」
「えーーーー」
「でも皆5歳、6歳になるとこんなに大きくなるね。これが命の力です」
東京都八王子市にある八王子学園なかよし幼稚園で、年長の子どもたちに「命の教育」を行うのは大葉ナナコさんだ。大葉さんはこうした取り組みを18年間全国で行ってきた。対象の子どもは幼稚園から高校生まで。また保護者や教職員にも「命の教育」の大切さを伝えている。いまこうした「命の教育」を行う講師は、全国で150人に上るという。

性行為は扱わずに性犯罪予防教育を行う困難
性教育は幼児にはまだ早いのではないか?こうした疑問に対して大葉さんはこう語る。
「小学校3、4年生になるとポルノデビューするといわれています。今回は年長さんが対象でしたが、この子たちもあと4年もたつとスマホやネットで性情報に触れ始めます。そうすると暴力的な性情報がスタンダードになってしまうかもしれません。ですからその前に命につながる性、誕生から伝えることが大切なのです」
しかし学習指導要領には「はどめ規定」があり、学校教育の中で「性行為」は取り扱わないことになっている。これについて大葉さんはこう語る。
「学校では性行為について教えられませんが、性犯罪や性被害の予防に向けた教育は行わなければならない。ですから学校の先生たちは本当に困っているんです。ユネスコ(=国連教育科学文化機関)では、適切な時期に適切な性教育を受けることは、子どもの人権であると言っています」
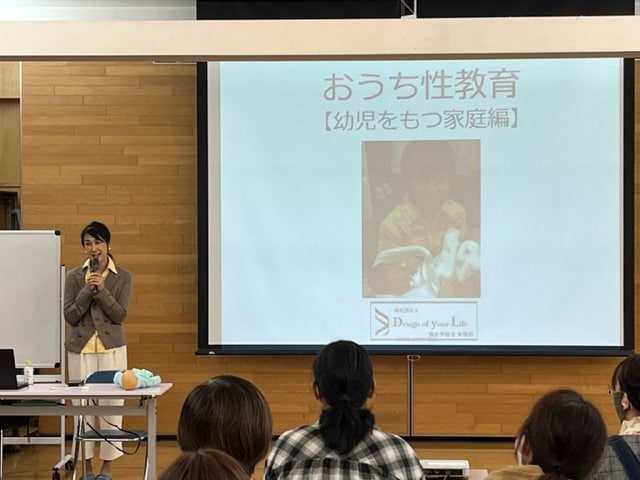
「性被害が最も多いのは小学校1年生です」
今回大葉さんを講師として招いたのは清水弘美園長だ。清水園長は以前小学校の校長だった。なぜ清水園長は幼稚園で「命の教育」を行おうと考えたのか。
「小学校では4年生の保健体育で、身体の変化や妊娠、出産について教えていました。しかしどうやって命がつくられるかについては、はどめ規定で教えられない。避妊教育も行われないから、望まない妊娠が防げない。2003年の七尾養護学校事件(※)以来、日本の性教育はピタッと止まってしまいました。性教育に対するバックラッシュ(=反動的な動き)が起きたためです」
(※)東京都立七尾養護学校で、知的障害を持つ児童に行われた性教育の内容が不適切だとして、東京都教育委員会が当時の校長らに厳重注意処分を行った。

清水園長にも「性教育は幼児には早いのではないか」と尋ねると、「いま性被害が最も多いのは小学校1年生です」という答えが返ってきた。
「しかも子どもの性被害の8割は身近な人によるものです。ですから小学4年生になって初めてプライベートゾーンについて習って、『あれ?私がされていることはおかしいんじゃないか』と気づく。そして担任に相談して大騒ぎになって児童相談所が動くということが実際に起こっているのです。性犯罪を予防するための教育が幼い頃にされてないから、子どもたちはそれがいけないことだとわからない。だからこの幼稚園では、プライベートゾーンについても教えることにしています」

生きていくためのスキルとしての性教育とは
京都の産婦人科医の池田裕美枝さんは、大阪の中学校で14年間性教育の出張授業を行っている。性教育を始めたきっかけを池田さんはこう語る。
「産婦人科には人工妊娠中絶や性感染症の治療に来院される方がいらっしゃいます。なかには『いままでよく生きてこられたね』という状態の女性もたくさんいました。性教育を始めたきっかけは、望まない妊娠や性感染症を予防する以前に、『自分の身体は自分のもの』で、生きていくためのライフスキルとして性教育は大事なのではないかと強く思ったからです」

ではなぜ性教育はライフスキルなのか?池田さんはこう続ける。
「いま中学3年生への性教育の授業の中で、正確な知識とともに、コミュニケーションスキルを強調するようにしています。たとえば『性感染症や妊娠のリスクはわかっているけど、コンドームをつけてと言ったら嫌われるかもしれない』と、相手に言えない女性がいます。だけど自分が自分と向き合うことを大切にできれば、自ずと『パートナーにも自分自身と向き合ってもらわないと』という話になります。お互いが自分を大切にしながら歩み寄れるようなコミュニケーションはスキルであり、学習が大切です」
身体や生殖だけでなく人権を教える包括的性教育
ユネスコは「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」において、性について正しい知識やスキルを身に着けることで、性行動が慎重化しリスクを減らすことができると述べている。そして性教育は、身体や生殖のみでなく、ジェンダー平等や性の多様性など人権尊重をベースに幅広いテーマを包括的に扱うべきだとして、「包括的性教育」を提唱している。
しかし日本の公教育では、包括的性教育はほとんど行われていない。池田さんは「授業は1時間なので人権教育には全然時間が足りません」という。
「まずは『性暴力とは何か』を伝えています。こうした安全教育は、ユネスコのガイダンスのキーコンセプトにも『暴力と安全確保』としてあります。しかし私は包括的性教育の全体像を日本人に根付かせたいと思っています」(池田さん)

「性と生殖に関する健康と権利」は基本的人権
そこで池田さんは、SRHR(=セクシャル・リプロダクティブ・ヘルス・ライツ)についての情報発信を続けている。SRHRは「性と生殖に関する健康と権利」として基本的人権の1つだ。
「SRHRは、個人個人が子どもを産むことや性について健康な状態でいられて、子どもを産みたいと思ったタイミングで産めるように社会が変わりましょうという考えです。しかしこうした考え方は日本ではまだ普及していません。包括的性教育はそのためのとても重要なツールです。『あなたはあなたを大事にする権利があるんですよ』という教育ですから」

次回【ココがおかしい日本の性教育②】では、日本の性教育を変えようと立ち上がった若い女性たちの取り組みについてお伝えする。
【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】





