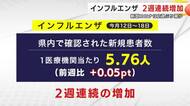感染増でも「ピークアウト」の声 そのワケは
東京都の新型コロナウイル対策を話し合うモニタリング会議が、今月4日に開かれた。会議では、新規陽性者数の7日日間平均が、前回の2万9868 人から、3万2921人に増え、過去最多を更新したとのデータが示された。
その一方で、増加比は、前回の180%から110%に減った。 感染者は増えているが、拡大スピードが緩やかになっていることを意味する。「ピークアウトか」との指摘もある。しかし、国立国際医療研究センターの大曲貴夫国際感染症センター長は、こうクギを刺した。


「検査に関して届いていない方もいらっしゃるんじゃないか、ということを言われております。これは現場でも感じているところであります」 と。検査を希望する人が、あまりに増えて、検査能力が追いついていないということだ。
検査ができない“潜在的感染者”が多くいるとすれば、実際の感染者数は「3万2921人」よりも、さらに増える可能性がある。このため、大曲氏は、“ピークアウト”は慎重に判断すべきとの見方を崩していない。
ベッドは空いているけれど・・・
「検査そのものにたどり着けない方々のイライラ感は非常に感じます」 。モニタリング会議のメンバーで、東京都医師会の猪口正孝副会長は、検査の陽性率で 51.4%と過去最高値となる中、発熱外来のひっ迫をこう表現した。
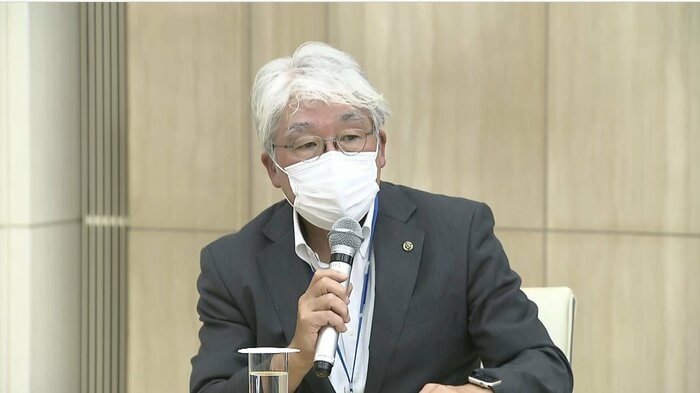
入院患者数は、前回の3725人から4091人に増加。一方で、東京都の病床使用率は6割以下にとどまり、病床に“空き”はある。しかし救急搬送は「受入不能」回答が多く、入院調整が「翌日に持ち越し」も相次いでいるという。医療現場としては「歯がゆい状態」とのこと。
そんな中、医療従事者が感染したり、濃厚接触者となるケースは、確実に増えている。猪口氏の病院でも、全体の1割の職員は出勤できない状況にあるという。「ベッドは空いている」のだが、受け入れ態勢としては「限界」に達しているとのことだ。
「全数把握」大流行では 逆にリスクも
医療機関や保健所が“本当に医療が必要な人”に集中できない原因の一つが「感染者の全数把握」とされている。確かに全数把握を徹底すれば、感染経路などを追跡調査することができる。「感染源」が把握できれば、効果的な対策を打つことも可能だ。しかし、それは感染者数が“追える程度”の時に限られるという。

大曲氏は、現状のような”大流行”の場合では、感染源特定に「限界」があると指摘。さらに、「全数把握のために、医療従事者や行政の手がとられてしまって、本当に医療が必要な人や、急な対応が必要な人が漏れてしまう。そのリスクは高まるだろう」との懸念を示した。
後遺症患者急増に懸念 “指さし”伝達も
「感染者がここまで増えると、後遺症患者も急増する可能性が高い」。医療従事者などの間では、後遺症患者”急増”の懸念が高まっている。
後遺症は、症状の種類が多く説明が難しいこともあり理解されづらい。後遺症外来で知られる「ヒラハタクリニック」の平畑光一院長は、後遺症の症状を「PS0」から「PS9」までの10段階に区分けをしている。

●PS0・倦怠感がなく平常の生活が可能
●PS1・通常の生活できるが、時々、倦怠感
●PS2・通常の生活できるが、全身倦怠のため、しばしば休息が必要
●PS3・全身倦怠のため、月に数日、社会生活できず、自宅にて休息必要
●PS4・全身倦怠のため、週に数日、社会生活できず、自宅にて休息必要
●PS5・通常の社会生活が困難、軽作業は可能。週のうち数日は自宅で休息
●PS6 ・調子の良い日は軽作業可能だが、週の50%以上は自宅で休息
●PS7・身の回りのことができ、介助は不要だが、通常の社会生活は不可能
●PS8・身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助必要、日中の50%以上は就床。●PS9・身の回りのことできず、常に介助必要。終日、就床が必要。
後遺症を10段階に区分けした理由について、平畑院長は、「体調が悪いときは症状の説明をすることすら辛いので、そういう場合は『PS』を、指で示すだけでも、どういう状態かが伝わる」と話した。
また、平畑院長は、10段階のうち「PS6」を分岐点と位置づけている。この段階になると、一人で暮らすことが困難になるという。海外の研究では、後遺症で働けない人が増えることへの懸念も出ていて、今後、後遺症についての理解が求められる場面が増えるだろう。
(フジテレビ社会部・都庁担当 小川美那)