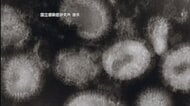500も1000も下がるということはない
「厳重な警戒が必要であります」
1月28日に開かれた東京都のモニタリング会議。感染状況については、新規陽性者の7日間平均が先週の1471人から1015人に減ったものの、緊急事態宣言発令前の1月6日とほぼ同数で、第2波のピーク時の約3倍と、依然として高い値が続いているとの分析が示された。
緊急事態宣言の“期限”とされる2月7日に、感染者数が500人となると思うか問われた国立国際医療研究センターの大曲貴夫国際感染症センター長は、その難しさを「1~2週間で500も1000も下がるということはないと思います」と表現した。

医療は危機的状況が続いている
「医療提供体制の逼迫が長期化し、通常の救急医療等も含めて危機的状況が続いています」
医療提供体制について東京都医師会の猪口正孝副会長は、今の感染者数に対応する病床を確保するためには、通常の医療をさらに縮小せざるを得ない、と厳しい現状を伝えた。
「(新型コロナウイルスの)患者が退院したあと、すぐ次の患者が入院する状況が続いており、入院調整が難航しています」
病床が足りず入院調整が非常に難しくなり、救急受け入れが困難になっていること、予定していた手術が制限されていることなど、都民が必要とする通常の医療がこれまで通り実施できない状況であることも加えた。

高齢者や基礎疾患ある人を重点的に調査
「発生時の封じ込めが難しくなっている」
保健所業務が膨大になっていることなどから、東京iCDC専門家ボードの賀来満夫座長は、今後は感染経路・濃厚接触者についての調査や健康観察は、高齢者や基礎疾患のある人、医療機関、高齢者施設、障害者施設、特別支援学校などを重点的に行っていく、との考えを明らかにした。
つまり、高齢者でなく、基礎疾患もない人が感染した場合、これまで以上に自らの行動や体調を自分でしっかり把握していかなければならないということだ。
昼も夜も飲み会は無し ホームパーティーも無し
小池知事は、強い口調で「今も緊急事態宣言下にあるという認識をもう一度改めてお持ち頂きたい」と述べ、ステイホームやテレワークの徹底を求めた。
「友人とのやりとりもリモートで」「昼も夜も飲み会は無し、ホームパーティーも無し」
そして、自民党の松本純衆議院議員の“深夜のクラブはしご”への憤りだろうか、「23時まで開いているお店もあったようですが、ぜひここはご協力を」とも述べた。

新規感染者数は減ってきても、入院患者や重症患者は決して減っていない。
再度引き締めていくためには、やはり一人一人が自分の行動と対策を見直して徹底していくしかないのだろう。
コロナ治療に期待の抗寄生虫薬「イベルメクチン」
「家庭内感染や施設内感染を抑えるのに有効なのではないか」
ある都の関係者は抗寄生虫薬「イベルメクチン」への期待を示す。
イベルメクチンは、2015年にノーベル医学・生理学賞を受賞した北里大学の大村智特別栄誉教授が開発。タブレット型で扱いも簡単、アフリカなどで寄生虫による感染症に大きな効果をあげた。
これまでに細胞を用いた実験で、新型コロナウイルスの増殖を抑えることが分かっている。
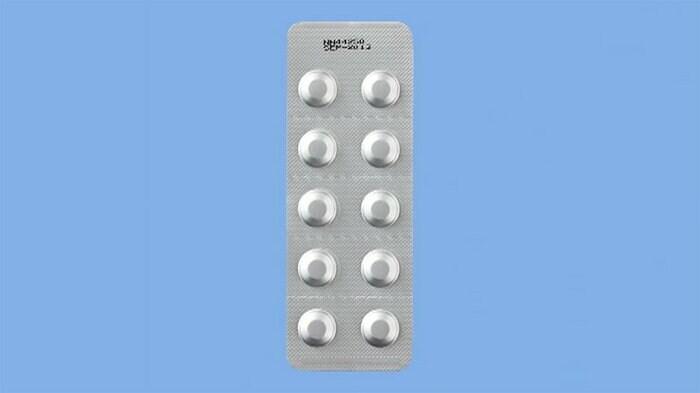
「家庭内や高齢者施設などで誰かが感染した場合、周囲の人も予防的服用をすることで感染の広がりを抑えられるのでは」
その関係者はこういった面でも期待感を示した。
まずは、実際に効果があるのか確認する治験が重要で、この治験が速やかに進むことが望まれる。
(執筆:フジテレビ都庁担当・小川美那記者)