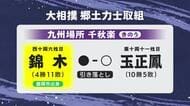岩手県九戸村の折爪岳。その展望台から広がる景色は、まさに絶景です。この折爪岳を中心に、地形にまつわる地名や不思議な伝承を探ります。
長年、岩手県内の地名を調査してきた宍戸敦さんによると、「折爪岳の『折』は崖や斜面を意味し、『爪』は端(つま)と同じで先端部を指します。つまり折爪岳とは『山の斜面の下りた先端の部分』ということになる」と説明します。
折爪岳を降りる途中、「オドデ様」という像があります。
麓にある道の駅おりつめ「オドデ館」前で、九戸の民話をよく知る木村正樹さんに話を聞くと、「オドデ様は『上がフクロウで、下が人間』という怪鳥で、江刺家岳(折爪岳)に住んでいたと伝えられている」ということです。
江刺家岳は、九戸村での折爪岳の呼び方です。
昔、ある家の神棚にオドデ様が座り、人間の言葉を話し、落し物の場所や翌日の天気を言い当てたといいます。
九戸歴史研究家 木村正樹さん
「噂が広がり、占ってもらう人が増えると、それを見た大家が下に賽銭箱を置いた。オドデ様いつも上ばかり見てたので、たまたま下を見て賽銭箱にお金がいっぱいあるのを見て驚き、『オレハ、シランシラン、ワッハッハ、シランゾ、ドデン、ドデン』と言って飛び去ったという話。こうして「オドデ様」と呼ばれるようになった」
「ずんぐりむっくりの、かっこいいといえばかっこいい怪鳥ですよね」と木村さんは笑って話します。
地域の人々にとって、不思議でありながら愛される存在なのです。
「オドデ様」が住むと伝えられる折爪岳の麓には、山の名前と関わりを持つ地名が残っています。
行政区として「柿の木」と呼ばれる地域がありますが、柿の木が多かったわけではありません。
宍戸敦さん
「『柿」』は『欠ける』、そして『の木』」は『除く』(無くする)という意味で、どちらも崩れることを示す言葉。崖地に多い地名で、折爪岳の先端部が崩れやすい地形、そういう状況にあっているということになる。そのものずばりの露骨な表現を地名はあまりしない。見た目の良い字や楽しいものを優先した付け方をするので、『柿』という字は、県内でも全国でもよく見られるパターン」
もう一つの地名「日の脇」も行政区としてある地名です。
日向の脇、つまり日当たりの良い場所から少し離れた場所を意味すると宍戸さんは説明します。
宍戸敦さん
「県内には気象に関する地名がある。そのうちの一つが九戸村にある『日の脇』という地名。『日の脇』は日向の脇の部分、ちょっと離れた場所になる。それに対して「日影」という地名は日が当たらない場所。県内には日影と日向が対になる地名があり、住田町世田米の方には日向と日影を意味する「西風」(ならい)という地名がある。陰と陽が対になっている地名があり注意深く見てみると面白いと思う」
折爪岳、柿の木、日の脇など九戸村には地形や自然の姿を映し出す地名が数多く残されています。地名から読み解いてみると、九戸村の魅力がより深く見えてきます。