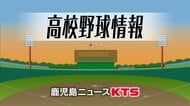8月5日は語呂合わせで「発酵の日」。
というわけで発酵食品の味噌について考えます。
鹿児島の味噌は原料に麦を使う「麦味噌」ですが、全国的には珍しいんです。
同じ味噌でも甘さが特徴と言われる鹿児島の「薩摩味噌」。
その現状と秘めた可能性を河内アナウンサーが取材しました。
夏休みに開催された、とある親子教室。
親子の前に並んでいるのは大豆、水、塩、そして麦麹。麦味噌を作るためのキットです。
機械を使わず全て手作業で行うため、こねるのも、潰すのも一苦労。
食べごろになるのは約1か月後で、夏休み中に完成するので自由研究の題材としても人気だと言います。
参加した子供
「麦をこねるのと大豆をつぶすのが楽しかった」
親
「鹿児島県の味を娘と一緒に作りたいと思って(参加した)」
みそ作り講習会 講師・永野正江さん
「この教室に参加した人たちが『やっぱりこれだよね』と話しているので、小さい時から麦味噌に親しんできたんだなと」
鹿児島ではおなじみの「麦味噌」。
ですが原料別に全国の味噌の出荷量を見てみると、その割合は4%未満と少数派なんです。
米の生産量が少ない九州では麦味噌が主流になったと言われていますが、中でも鹿児島の味噌=薩摩味噌はその甘さに特徴があります。
田園風景が広がる鹿児島市東俣町の工房を訪ねました。
学校の校舎だった建物を工場にした「ほたる醸造」。
この場所で30年前から味噌作りを行っている小城章裕さんです。
家で味噌造りをしていた母親の影響を受け、この世界に飛び込みました。
タンクに入っているのは、蒸した麦に種麹を付けて作った「麦麹」。
ほたる醸造・小城章裕さん
「少しだけ白っぽく見える。今、麹菌が繁殖しているところ。これから真っ白になっていく。あと20時間ちょっと(かけて)」
この麦麹を36度から38度で管理しながら寝かせます。
翌日、表面が白っぽくなった麦麹が完成しました。
この麦麹と、ミンチ状にした大豆、塩、水を混ぜ合わせます。
薩摩味噌の甘さの秘密は、麦麹と大豆の割合にあるそうです。
小城さん
「大豆の量に対して麦麹の量が3倍くらい多い。通常の米味噌は麹と同じ量の大豆を使う。麦はデンプンを含むので甘みが多くなる」
こうしてできあがった味噌のもと。
特別に味見をさせてもらうと・・・
河内杏月アナウンサー
「しょっぱい。塩の味が強くて」
ここから樽で発酵・熟成させることで味噌の味が作られていきます。
期間は約1ヶ月。
熟成に半年から数年必要な味噌もある中で、この期間の短かさも薩摩味噌の特徴です。
小城さん
「熟成すればするほどアミノ酸が出てきてうまみが増すが、鹿児島の人が好きな甘い味からは離れるので頃合いを見て出している」
河内アナウンサー
「口に入れた瞬間にふわっと麹の香りがします。熟成前はかなり塩気が強かったが、まろやかになって甘みの方が強く感じます」
麹の原料や熟成の期間によって味わいが変わる味噌。
小城さんは毎回ノートをつけているそうです。
小城さん
「味噌は1000年以上作られているので、科学的に分析される前にできあがっている。それを今、科学的に裏付けしている状態」
長年の歴史がある薩摩味噌ですが、実は今も研究が進められています。
県工業技術センターの加藤由貴子さんです。
県工業技術センター 食品・化学部 加藤由貴子さん
Q.麦味噌の全てを100としたら研究はどの程度進んでいる?
「20~30%ぐらいだと思う」
研究が進む中で、薩摩味噌のこんな可能性が見えてきたそうです。
加藤さん
「鹿児島の味噌の特徴として『麹の割合が大きい』というのがある。その特徴を生かすことで、他の味噌より減塩ができるとわかってきた」
薩摩味噌は水分が多い大豆の使用量が他の味噌に比べて少なく、雑菌の繁殖のリスクが低いそうです。
そのため雑菌を防ぐために使う塩の量も減らせて、より健康的な減塩味噌が開発できるといいます。
加藤さんは、この特性を生かし、新しい形の薩摩味噌を模索しています。
こちらは、味噌だけをフリーズドライにしたもの。
河内アナウンサー
「食べやすいですね。すごく軽くて、お菓子感覚で食べられる」
加藤さん
「通常塩の味噌で作るとしょっぱすぎて食べられないが、塩分を下げることで、食べられるスナック状にできる」
研究が進む薩摩味噌ですが、その一方で食の西洋化や人口減少などに伴い、年々、出荷量が減り続けているという課題もあります。
加藤さん
「(味噌を)今まで使っていなかった人にも使ってもらう方向を向いていかないといけない」
ほたる醸造・小城さん
「(味噌が)無くなることは無いと思うが、ここで下げ止まってほしい。味噌屋の一員として、味噌を使ってもらえるような取り組みや発信をしていかないと」
長きにわたり、鹿児島の食文化を支えてきた「薩摩味噌」。
「ふるさとの味」を受け継ぎながら、未来につなぐための取り組みが進められています。