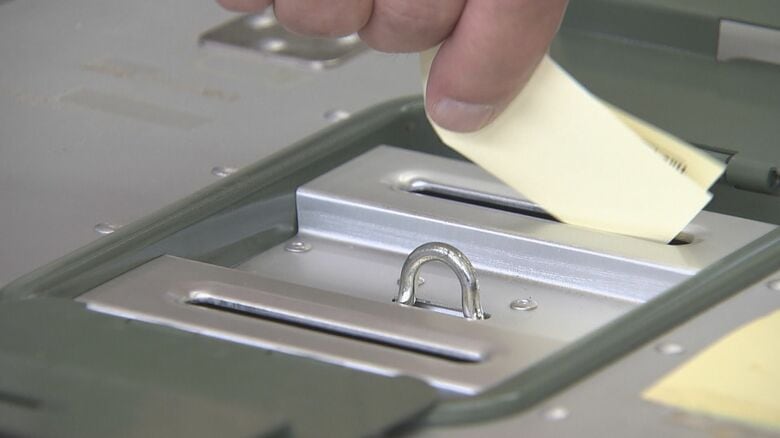2025年は、選挙権をめぐる3つの節目の年です。一つ目は多くの人が選挙に参加できるようになった現在の選挙権の基礎となる「普通選挙法」の成立から100年、二つ目は女性の参政権獲得から80年、三つ目は選挙権が18歳以下に引き下げられてから10年です。現在、投票率は50%台と低迷が続いていますが、政治とのかかわりをひも解きます。
まずは、福井県民に選挙に対する考え方を聞きました。
県民は―
「投票は行きます。権利を持っているし、自分の意思を伝えるのは大事」
「(投票に行かないのが)慣れっこになってしまった。大体決まっているのではないかと思ってしまう」
「子供が3人いるが、選挙をしても何も変わらないという思い。生活面やお金の面を考えてくれる熱い人がいい」
◆女性の選挙権は大正デモクラシーの20年後
普通選挙法が成立したのは100年前の1925年(大正14年)。日本で最初に作られた選挙のルールです。それまでは、お金を持ち税金を多く納めている人だけに選挙権が与えられていましたが、この法律で25歳以上のすべての男子に選挙権が与えられました。
国民主体の政治を目指す民主主義的なこの運動は「大正デモクラシー」と呼ばれています。
しかし、女性の声を政治に反映する仕組みはまだ整えられませんでした。
その後、日本は戦争に突入し敗戦。戦前の反省に立って憲法や法律が作り変えられる中、1945年(昭和20年)に選挙権の年齢が20歳に引き下げられ、初めて女性にも選挙権が与えられました。
翌年の昭和21年4月に行われた衆院選の様子を報じた福井新聞の記事は、福井市内の投票所入り口に多くの女性が並び、長蛇の列ができていた事を伝えています。中には、子供を連れて並ぶ女性の姿もあったとあり、関心の高さがうかがえます。
この衆院選の全国の投票率は72%、全国で39人の女性国会議員が誕生しました。
その後、日本は高度経済成長期に突入し、政治も次第に安定していきました。県内の衆議院選選挙の投票率の推移をみると、1955年(昭和30年)には自民党と社会党の2大政党が誕生し「55年体制」といわれた衆議院選挙の投票率は84.1%、昭和38年の衆議院選挙の投票率は83.7%でした。池田勇人首相が国民所得倍増計画を進めていたことから「所得倍増解散」と呼ばれました。
◆「政治への失望から投票率が低下」
福井新聞の県政記者や論説委員長として、長年選挙取材にあたってきた政治ジャーナリストの橋詰武宏さんに話を聞きました。「昭和30年頃、日本の経済社会は力強く復興の最中にあった。日本が急成長し坂を上っていくような政治状況。政治への力、期待が高まっていた」
ただ、橋詰さんはある出来事が政治への失望を生み、その後の投票率の低下につながったと指摘します。それは、元総理大臣の田中角栄氏が逮捕されたロッキード事件です。昭和58年、田中元首相が実刑判決を受けた後の田中判決解散。投票率76.6%は、現在から見れば非常に高い数字ですが、橋詰さんは、この頃から有権者の意識が変わったと振り返ります。
「ロッキード事件で逮捕されるという象徴的な出来事があり、政治の裏を見せつけられたと同時に、ハード面への要求が低くなってきた。高度経済成長が行き詰まり、新しい社会が成熟し、福祉や教育、高齢化社会の対応などへ国民意識が転換した。それと同時に政治が明確に応えられなかったということが背景にある」
その後、投票率は低迷の一途をたどり、現在は50%台が続いています。そして、高齢化が進み人口減少時代に入る中、10年前には選挙権年齢が引き下げられ、18歳以上のすべての国民が投票できるようになりました。
18歳になった人は―
「(選挙については)まだ考えていない。あんまりよくわかっていない」
若い世代の政治への関心の低さについて、橋詰さんは「何をしても社会は変わらないという閉塞感があり、若い人の政治への関心が薄れてきている。政治は分かりやすく、新しい時代に対するテーマ性を出さないと投票行動に結びつかない」と分析しています。