自民党の議員でありながら、自民党の政権運営を批判し続けてきた石破首相。
現在、自民党総裁、そして国の道筋を決断する総理大臣という立場になった石破首相は、その“批判”精神を持ち続けられているのだろうか。
現役の政治家として異例な数の著書を執筆し、日本が抱える問題について論じてきた石破首相が、かつて新潮新書から刊行した4作から、その思考の真髄がわかる論考だけを集めて編んだ『私はこう考える』(新潮新書)から、一部抜粋・編集して紹介する。
自民党が下野し、そして政権に戻る際、石破首相は何を考えていたのか。
もう政権に戻れないと思った頃
2012年の政権復帰以降、自民党は選挙で勝利を続けてきました。
そのあとの自公政権しか知らない人にとっては、これが永遠に続くかのような幻想を持つのも無理のないことなのかもしれません。特に野党でそう思う人は、焦るあまりに、その場しのぎの離合集散を演じ、かえって自らの首を絞めてしまう、ということも多くの国民が目にしたことです。
しかし、私にはそのような幻想を持つことは到底できません。
2009年に野党に転落したときの衝撃は非常に大きく、忘れられないものだったからです。

あの時、自民党の議席は300議席から119議席にまで減りました。ほぼ3分の1になったのです。すでに世論調査などから敗北必至であることはわかっていましたし、実際に事前予想では120議席という数字も出ていました。
ほぼその通りとはいえ、それでもなお、結果にはたいへんな衝撃を受けました。
あの時、多くの自民党幹部は、こんな風に思っていました。
「ああ、これで10年間は政権に戻れない」
小選挙区制を採っている国で政権交代が起こった場合、10年間はその政権が続く、というのは常識でした。英国やカナダでもそうです。小選挙区とはそういうものなのです。
私は当時、農林水産大臣でしたが、「もう自分が国会議員でいる間は政権に戻ることはないかもしれない」と思っていました。
ただ、野党になってすぐにやらなければならないこともわかっていました。なぜ自民党は敗れたのか。野党にならなければいけなかったのか。このことを徹底して検証することです。
当分政権に戻ることはないとしても、その間にできることは何か。何をすべきで、何をすべきではないか。

もう一つ、強く思ったのは、自民党が分裂するような事態は絶対に避けなければいけない、ということでした。
かつて金丸信先生は、「野党になったら馬糞の川流れだ」と仰ったそうです。いささか品の無い表現かもしれませんが、要は政権から降りたとたんにバラバラになる、という意味です。
自民党を支えているのは権力なのだ、それゆえに権力を絶対手放してはいけない。
これは自民党がずっと抱えてきた、執念のようなものだったと思います。だからこそ、ある時期には日本社会党委員長の村山富市さんを総理に担いでまで政権に返り咲いたわけです。
非難を浴びることは承知のうえだったのは間違いありません。それでも当時の幹部たちは決断したのでしょう。
しかし、権力への執着が行き過ぎることは自重せねばならないと考えています。自民党の核となる政策を枉(ま)げてまで与党たろうとすることは、国民政党のすることではないと思うからです。
「自民党、感じ悪いよね」
自民党を破り、華々しく誕生した民主党政権は、当初、国民やメディアの喝采を浴びて始動します。この民主党政権が本当に国民国家のためになる政権であれば、われわれ自民党の出番は本当にしばらくの間なかったでしょう。
しかし、結果はご存知の通りでした。
年金問題、子ども手当、高速道路無料化、財源はすべて「事業仕分け」で見直すことで捻出する。
私も「もしかすると、全く今までとは違う視点で解決策を実行できるのだろうか」と思うところがなかったわけではありません。
ところが政権運営はあまりに稚拙で、理想はあったのでしょうが、それを現実的な政策に落とし込むことも、実行することもほとんどできませんでした。そしてその民主党政権の最中に、あの東日本大震災・大津波・原発事故が起きたのです。
こうなっては、何としても自民党を立て直し、国民生活の安定を我々が担う以外にない。それが、私たちの使命となったのです。
このときの記憶が生々しく残っている以上、私たちが与党に戻り、いくら安倍政権は盤石だと言われても、自公政権がずっと続くなどという楽観的な考え方を持つことは、私にはできません。

そもそもあの時、なぜ自民党は野党に転落したのでしょうか。なぜ有権者に嫌われたのでしょうか。
私は、決して自民党の政策が間違っていたのではなかったように思います。それよりも、党のあり方に対する厳しい見方が大きかったのではないでしょうか。
簡単に言ってしまえば、「自民党だけは嫌だ」という思いが有権者に蔓延していた気がします。
そうした国民の気分に対して、当時私は「『自民党、感じ悪いよね』と思われないようにしなければならない」と発言したこともあります。そう発言したことに対しての批判もありましたが、実際にそういう気分の国民が多くいたのは間違いなかったと思います。
では、「自民党だけは嫌だ」と思われた理由は、たとえばどのようなものだったのでしょうか。
まずは、その時々の政権の失策や失言、不祥事などで、総理が次々に代わってしまったということが挙げられるでしょう。
2009年の時点で、私は議員になって23年が経っていました。その間に総理大臣がどれだけ代わったか。
私が初当選した1986年は、中曽根康弘総理でした。そのあとの名前を並べてみましょう。竹下登、宇野宗佑、海部俊樹、宮沢喜一、細川護熙、羽田孜、村山富市、橋本龍太郎、小渕恵三、森喜朗、小泉純一郎、安倍晋三、福田康夫、麻生太郎…、四半世紀足らずの間に、実に新しい総理が14人も誕生していたのです。
平均すれば1人あたり2年も続いていません。
このうち細川、羽田、村山を除けばすべて自民党です。このような状況に国民から拒絶反応が生まれるのは当然でしょう。

総理はまだそれでもましかもしれません。大臣に至ってはそれどころではなかったからです。
たとえば、私は福田康夫内閣において防衛相をつとめましたが、2007年に入って9カ月で、すでに4人目でした。私の前が高村正彦先生、その前が小池百合子先生で、さらに前が久間章生先生です。
次の麻生内閣では農水相をつとめましたが、第一次安倍政権時代に「鬼門」と揶揄(やゆ)されたポストだけあって、安倍政権から麻生政権までの2年で、実に私が6人目でした。前任者は松岡利勝先生、赤城徳彦先生、若林正俊先生、遠藤武彦先生、再び若林先生、太田誠一先生。
やむをえない交代もなかったわけではないでしょうが、こんなに大臣がコロコロ代わる様を見て、国民がウンザリしないわけはありません。
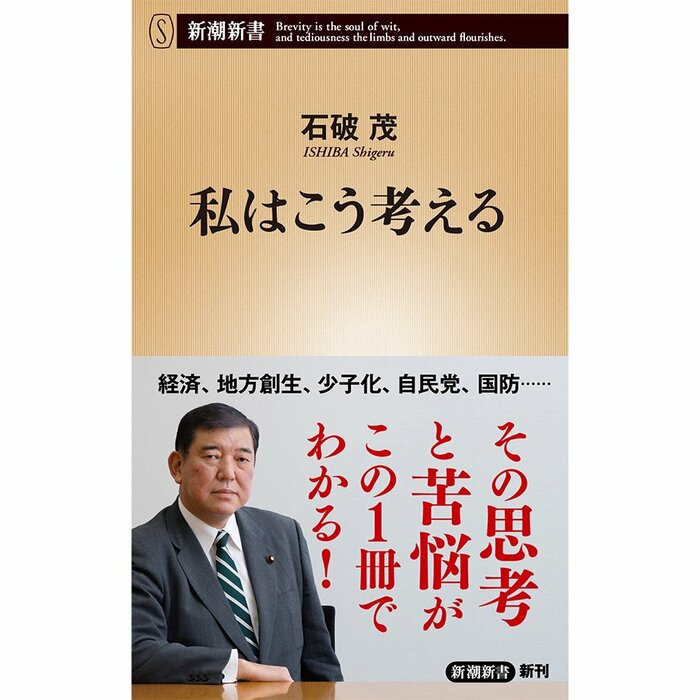
石破茂
1957(昭和32)年生まれ、鳥取県出身。慶應義塾大学法学部卒。1986年衆議院議員に全国最年少で初当選。防衛大臣、農林水産大臣、地方創生・国家戦略特別区域担当大臣などを歴任。2024年、第102代内閣総理大臣就任。著書に『国防』『日本列島創生論』など。






