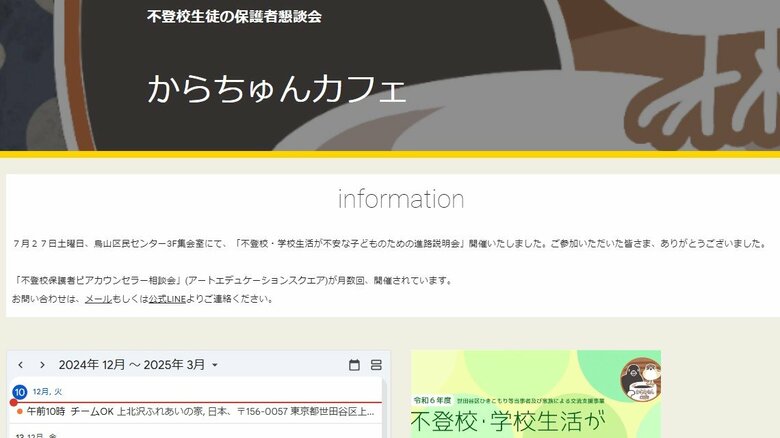毎朝、子どもたちが通学する時間になっても、自分の子どもは自宅から出られないという状況が続く日々に、進学や将来のことを考えると不安でたまらないし、原因の1つに自分の子育てが間違っていたからではないかと、親自身の自己肯定感も下がっていくケースもある。
そうした保護者たちの悩みを聞いてくれる団体が、東京・世田谷区の「からちゅんカフェ」だ。

地域の保護者が自主的に運営する団体で、月に一度、区の施設で平日の午後1時から夕方まで、不登校の子どもを抱える5人から10人の保護者たちが集まる。
共同代表の島田有子さんは「不登校になった場合どうすればいいのか、区の教育委員会のHPでは、不登校のための施設がありますなどと紹介されていますが、実際問い合わせてみると、なかなか入れない狭き門だったりします。
体験をクリアしないと、入学できません、などハードルがあったり実際に行ってみると、子どもが必要としている支援と違うケースがあったり。
私たちの会では、保護者同士の連携を通して、行政からのお知らせだけではわからない体験談や、口コミ情報をもとに、施設の長所や短所、子どもの状況に応じた適切な支援機関、支援方法はないのかなどを話し合ったりしています。」と話す。
保護者の心が軽くなると子どもにも良い影響が
「からちゅんカフェ」設立の目的は、保護者の心を軽くすること。
子どもが不登校になると、親は不登校を受け入れられるかという悩みに直面する。

子どもの将来や進学を考えると不登校は認めたくない、認められない、という気持ちになってしまうが、不登校であることを受け入れることができると、心が軽くなる。
共同代表の安井敦子さんは、「親の心が軽くなると、子どもにも良い影響を与えるようになる」という。
同じ境遇の人の言葉に共感する
安井さんは、「会に参加される保護者の皆さんから聞かれるのは、共感できたという言葉です。子どもが不登校になると学校の先生とか教育機関のサポートはありますが、当事者でないとわからない焦りは、先生や学校へ行っている人から『学校いかなくても大丈夫だよ』、と言われても響かない。同じ境遇の人から、不登校の様々な体験談を聞いて初めて心が軽くなる。
心が軽くなって家に帰った時に優しい目で子どもを見られるようになるし、子どもは、親と違う人生を歩む一人の人間だということに気づかされます」と話す。

さらに、「会に初めて参加する保護者は、体験の話をしながら涙を流す方もいるが、回を重ねるごとに明るくなる。経験がない人に言っても、『大変だね』で終わってしまったり、自分の中で話してもすっきり感がない。そういう気持ちを会にきて話すことで、元気になってもらっています。」という。
「大人も子どもも余裕がない」
不登校のそもそもの原因について聞いてみると、「世の中が、『子どもには好きなことをやらせてあげなさい』という風潮に変わってきているのに、学校は昭和の時代から変わっていない。義務教育に入れられると突然縛られてしまう。子どもからすれば『今まで良かったのに、なんで?』と驚いているのではないか。
今は子どもに暇な時間がなさすぎる。ぼーっとしている時間は大事なのに、『ぼーっとしているなら宿題していなさい。』と言われる。大人も子どもも余裕がないと思う」などの点を挙げた。

「からちゅんカフェ」のHPには「学校へ行けなくなってしまった我が子にどう接すれば良いのかわからず、私自身がパニックだった頃……私を救ってくれたのは、同じような経験をした保護者仲間でした。仲間から得た情報を元に親子が元気になれる方法を模索する…、保護者の方がそんな行動を起こせるようなお手伝いができたら…、と考えています。」などとつづられている。
“悩みを吐き出す”、そうした時間・場所を提供し、同じ境遇の仲間、自分を受け止めてくれる人がいることで、保護者の心の余裕や安心感にもつながる。
「からちゅんカフェ」は、不登校・学校生活が不安な子どものための進路説明会なども開いていて、今後も、「子どもたち、保護者のために、少しでもお役に立てるよう活動していきたい」としている。
(取材・執筆:フジテレビ社会部 大塚隆広)