消費者の「あったらいいな」を生成AI(人工知能)で具体的な商品イメージに変えて、企業に提供する「架空商品モール」が登場し、消費者のニーズを可視化する。
専門家は、「AIが進化すれば、売れる数の予測も精度が上がり、商品化が容易になる」と期待を寄せている。
AIの架空商品で消費者の声を企業へ
生成AIが商品のイメージを作り、消費者の「あったらいいな」を製品化につなげる。

旅行帰りでくったくたに疲れているとき、キャリーバッグのタイヤをふく手間を軽減してくれる、タイヤ部分から外せるキャリーバッグ。
こんな「あったらいいな」が本当に商品化に結びつくかもしれない。
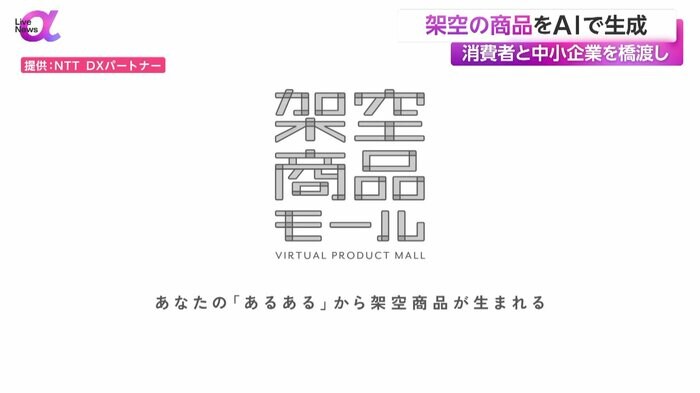
そんな消費者と中小企業を橋渡しする、商品開発のプラットフォーム「架空商品モール」が登場する。

「架空商品モール」では、消費者がチャットに書き込んだ「こんな商品があったら…」という希望を、生成AIが企業の持つ技術をもとにして架空の商品イメージを作り、サイトに掲載する。

例えば、「部屋を好きな香りで満たしたいけど、面倒なことはしたくない」という声からは、「こすると香りが出るアロマストーン」という架空の商品を生成。
AIで開発の期間やコストの圧縮も期待できる。

掲載した商品には、消費者が評価できる機能をつけることで、ニーズを可視化。
企業側はそこから、消費者の「欲しい」に応える商品開発につなげていくというのが狙いだ。
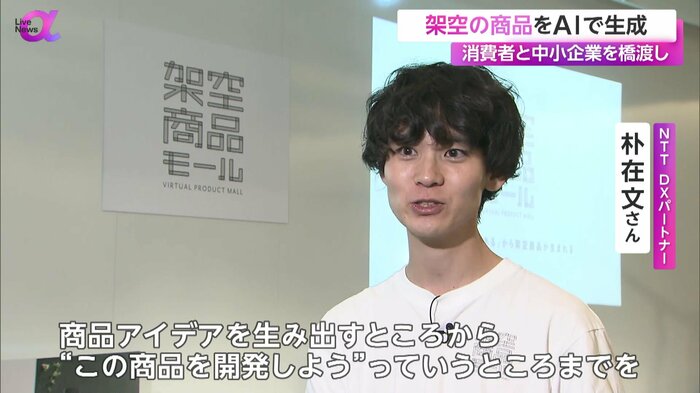
NTT DXパートナー・朴在文さん:
商品アイデアを生み出すところから、“この新商品を開発しよう”っていうところまでをしっかりと後押しできる。
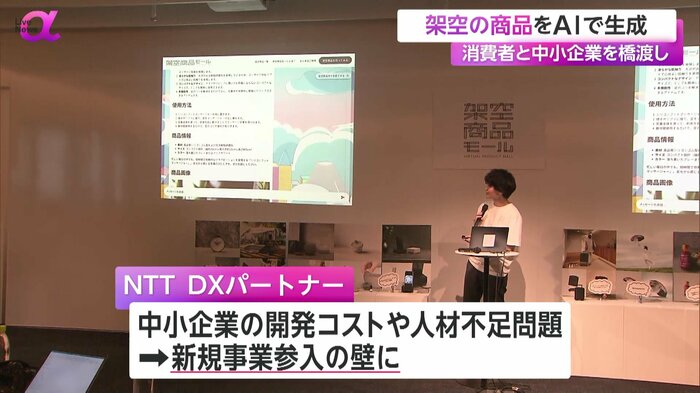
開発を手がける「NTT DX(ディーエックス)パートナー」は、企業のDXを進めてきた中で、特に中小企業は、開発期間やコスト、人材不足といった多くの課題を抱え、新規事業への参入が難しいと認識したという。

NTT DXパートナー・朴在文さん:
開発期間とコストを1年以上かけてやってきたのにもかかわらず、まったく売れないという悩みは非常に多く聞いていたので、「架空商品」でも、需要がしっかりと可視化できるような状態を目指せるのであれば、そこは経営者にとって投資を後押しする非常に大事なところかなと。新商品開発を成功体験へと変える、このためのサービスだと考えている。
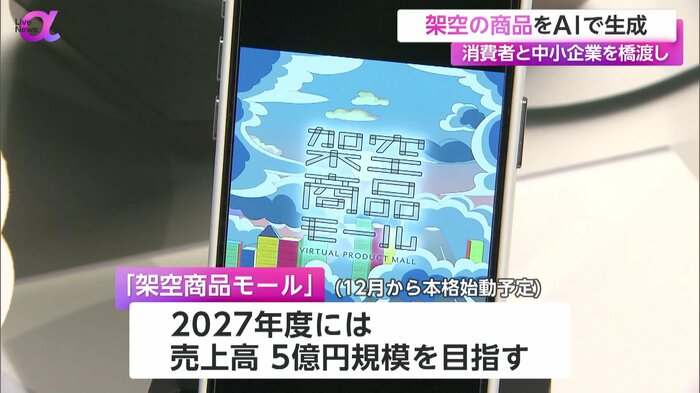
消費者と中小企業をつなぐ「架空商品モール」は、2027年度には、売上高5億円規模を目指すとしている。
ニーズ分析・在庫リスク減でニッチ狙う
「Live News α」では、消費経済アナリストの渡辺広明さんに話を聞いた。
堤礼実キャスター:
ーーAIによる架空商品の取り組み、どうご覧になりますか?

消費経済アナリスト・渡辺広明さん:
これまで780品を超える商品開発に携わってきた者としては、この分野にまでAIが進出してきたというのは驚きであり、身が引き締まる思いがします。
かつて、商品開発といえば、マスマーケットの「みんなが欲しがるもの」を目指していました。
それが、消費の多様化が進み、右肩上がりで成長する商品がなかなか生まれず、マーケットが成熟したことで、ネット販売を中心に、「誰かが欲しがるもの」にターゲットを絞ったニッチな商品開発が広がり、ここではAIの活用が進んでいくと思われます。
堤キャスター:
ーーどうしてAIとニッチな商品開発は、組み合わせの相性がいいのでしょうか?
消費経済アナリスト・渡辺広明さん:
顧客のニーズを分析できることもありますが、リアル店舗での販売は、売れ残りの在庫リスクを避けるため、思い切った発想の商品の発売をちゅうちょするケースがあります。
ましてや、経営体力に限りがある中小メーカーの場合、なかなかリスクを取れません。それが、限られた顧客、ニッチなマーケットを対象にしたネット販売なら、在庫リスクを低くすることができます。
さらに、AIが進化していけば、売れる数の予測も、かなりの精度でできるかもしれません。すると、ネット通販を前提に、初回製造数がそれほどでなくても、商品化に踏み切りやすくなります。
架空商品が消費者へ気づきを与える
堤キャスター:
ーー今回の試みでは、架空の商品モールがネット上に展開されますが、これについてはいかがですか?

消費経済アナリスト・渡辺広明さん:
興味深いのは、実際に商品化する前に、みんなの「欲しい」が集まるのか、ネット上にある架空の商品モールで検証できることです。
そもそもネットの強みは、全国、さらには世界を対象に訪問者を広げられることです。「とがった商品」、「これまにないアイテム」が見つけられるという認識が広がると、架空の商品モールへの訪問者も増えていくはずです。
今回の試みを通して、実際に商品化されたものが限られた顧客を対象にしたニッチ商品であっても、消費者に気づきを与えることにより、ニッチからマスへと転換して、生活習慣を変えるような商品が生まれる可能性を秘めているように思います。
堤キャスター:
消費者のこんなモノがあったらというという思いが商品化につながり、企業側はユーザーのニーズを探ることができます。
商品開発のハードルが下がることで、新しいチャレンジを後押ししてくれるように思います。
(「Live News α」7月24日放送分より)




