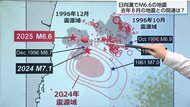能登半島地震では新潟県内でも学校を中心とした避難所に多くの人が避難したが、そうした場所に避難したくてもできなかったという声が上がっている。
ひきこもりや不登校の子どもたちだ。様々な理由で学校に行けない子どもたちが年々増える中、どう避難させ、命を守るか課題となっている。
「避難できなかった」石川から相談も
「不登校やひきこもりのお子さんの避難の難しさを訴えるものが複数あった。その視点はこれまで見えてきていなかった」
こう話すのは、新潟市のNPO法人・みらいびらきラボの佐藤裕基代表だ。

佐藤さんは小学校の教師として働く傍ら、NPOの代表として年々増えている不登校やひきこもりの子どものカウンセリングなどに取り組んでいる。
そうした子どもや家族向けのフリーペーパーを全国へ配布する活動も行う佐藤さんのもとには、地震後、新潟県内だけでなく、石川県の被災地からも子どもの避難に関する複数の相談が寄せられているという。

「避難所はほとんど地域の学校になっている。学校に行きにくいお子さんにとって、なかなか顔を合わせづらい方がいたり、環境自体になかなか対応できない。お子さんの避難をさせられなかったというような内容の相談もある」
中には半壊した自宅でさらなる揺れに怯えながらも避難できなかった子どももいるという。
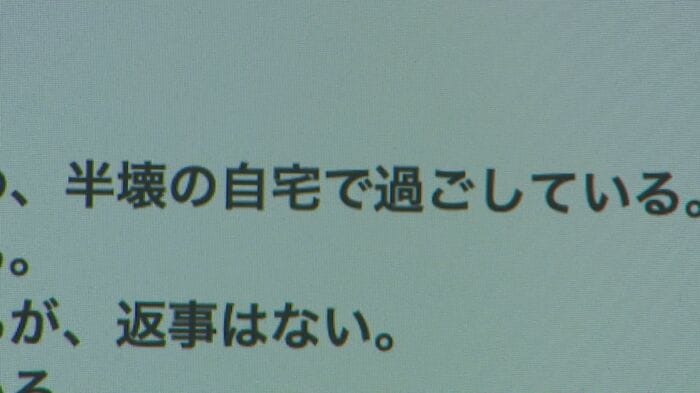
今後の災害時に、ひきこもりの子どもを避難させられるか不安を訴える声も上がっている。
避難させるために…重要な“事前準備”
不登校やひきこもりの子どもたちをどのように安心して避難させるか…
佐藤さんは「特別な配慮が必要なお子さんに対する特別な事前準備というものも想定しておく必要がある。何を持っていけば安心して避難ができるのかというのを事前に確かめておく」と話す。

具体的には…
▼一人用のテントや寝袋といったプライベートスペースをつくるための準備
▼タブレットやぬいぐるみなど、子どもによってあると安心できるアイテムの準備

こうした準備をしておくことによって、避難所でも安心して生活が送れることを子ども自身が事前に認識しておくことが不登校やひきこもりの子どもの避難行動のために重要になるという。

現在、佐藤さんはこうした避難のポイントを不登校やひきこもりの子どもがいる家庭に周知するべく、マニュアルづくりに取りかかっている。
「例えばペットを連れて行ける避難所も行政のホームページにちゃんと示されるようになっているし、そういった様々なニーズがある。同じように家を出にくいお子さんとかそういった方々に対してはどんな事ができるんだろうというのを考える契機にも今回の地震はなっているんじゃないかなと思う」
ひきこもりや不登校の子どもが避難できる環境を平時から備えておくことが重要となる。
(NST新潟総合テレビ)