安倍派の政治資金パーティー問題を受けて、岸田首相が22日に行った人事で、新たに自民党の政調会長に就任した渡海紀三朗氏は就任会見で「派閥にはいろいろな弊害がある。弊害は取り除いていかなければならない」と語った。その上で、1989年にリクルート事件を契機に、自民党内でとりまとめた政治改革の指針「政治改革大綱」の最新版策定に向けた意欲を示した。

安倍派と二階派の政治資金パーティーをめぐる捜査を契機に、今改めて派閥の弊害が注目されるようになり、派閥のあり方の改革、あるいは派閥を解消すべきだとの声が出てきている。一方で自民党は、過去に何度も派閥の解消を打ち出しながら、結局元通りになってきた歴史がある。
では一体、派閥の何が弊害で何故なくならないのか、そして岸田首相はどこまで改革するつもりがあるのだろうか。
24年前の政治改革大綱での派閥改革
渡海氏が言及した1989年の政治改革大綱には、政治資金をめぐって「冠婚葬祭などへの寄付禁止の強化」「株取引の規制」などと並び「パーティーの自粛と新たな規制」が盛り込まれている。そして自民党の派閥については「派閥の弊害除去と解消への決意」を掲げ、以下のように派閥の問題点を明示している。

「派閥は過去においてもいくたびか、党改革の最重要課題としてとりあげられ、その解消への努力が行われてきたが、現状はむしろいっそう強固になってきている。一部には派閥による活力を評価する向きもあるが、派閥と政治資金のかかわりや派閥の内閣、国会および党の全般にわたる人事への介在、派閥本位の選挙応援など、さまざまな弊害を生んでいる」
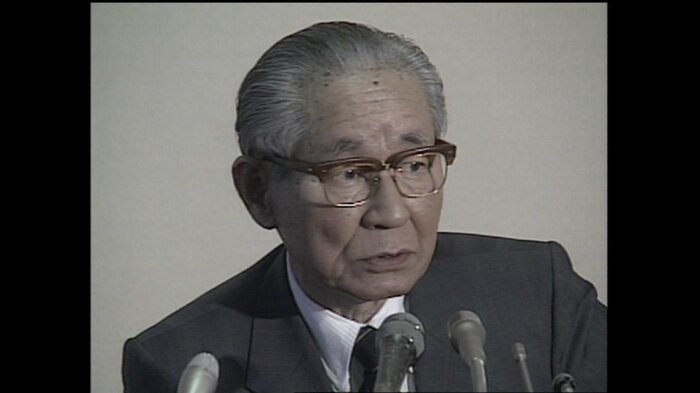
これを見て驚くのは、現在指摘されている派閥の問題点とほとんど変わらないことだ。
唯一、派閥本位の選挙応援については、この後、小選挙区制が導入されたことで党本部主導へと変化し、派閥色は一定程度薄まっている。そして大綱では、「かりに現状のような派閥中心の党運営が続くならば、党が真の意味での近代政党、国民政党へ脱皮することは不可能である。したがって我々は少なくとも早急に次の措置を講ずることにより、派閥解消の第一歩とする」として3点の改革をあげた。
イ. 最高顧問は派閥を離脱する
ロ. 総裁、副総裁、幹事長、総務会長、政務調査会長、参院議員会長、閣僚は、在任中派閥を離脱する
ハ. 派閥の実務者間によって、実質的にあたかも党機関にかわる意思決定と誤解されるようなことは行わない
このうち「ロ」の、総裁をはじめとした党役員や閣僚の派閥離脱は、一時行われていたものの、岸田首相が先日まで派閥の会長を務めていたように、行われなくなって久しい。

そして「ハ」の派閥の実務者間の意志決定については現在ほとんど行われていないが、岸田首相・麻生副総裁・茂木幹事長による三者会談は、奇しくも主流派3派閥のトップによる岸田政権の意思決定という格好になっている。
1994年に派閥解消もまさかのスピード復活
この政治改革大綱が策定されて以降も自民党内の組織が、たびたび派閥の解消を含む改革案を提言したが実現しないまま、1993年の総選挙で惨敗、細川内閣発足に伴い野党に転落した。そして翌1994年、自民党は党改革の一環としてついに派閥の解消を決定し、小渕派、宮沢派、三塚派、渡辺派などが解散式や解散総会を行った。

これで派閥は消滅と思いきや、そうはいかなかった。各派閥は「人のつながりは永遠だ」などとして、解散から半年も経たないうちに新たな政策勉強会を設立して「政策集団」の形に衣替えしたのだ。今回の派閥パーティー問題でも、多くの政治家が「政策集団が…」と説明しているのはここにルーツがある。
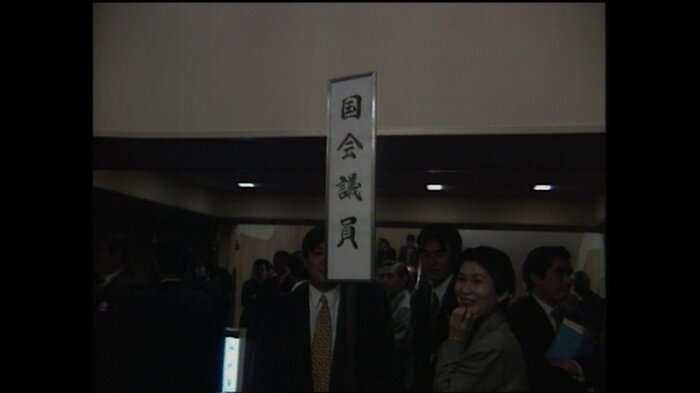
各派閥が名称に、「平成研究会(現茂木派)」「清和政策研究会(現安倍派)」などと「研究」を入れたのも、政策集団としての外見を意識してのものだった。各メディアは、派閥は解消されているという前提で「旧小渕派」「旧宮沢派」などと「旧」を使ってこの政策集団を表現した。
しかしその後、各政策集団は自民党が政権復帰を果たす中、懇親会、パーティーなどを復活させ、派閥の弊害と指摘されたはずの人事をめぐる調整も行われるようになった。政策集団という外見は維持しつつ、金とポストの配分という派閥としての機能を取り戻していったということだ。
それに伴いメディアも派閥名から「旧」を取り除きはじめ、橋本政権では、小渕派、加藤派、山崎派が主流派となり、小渕政権後期と森政権では、小渕派、森派・村上派が主流派として政局を主導した。
小泉首相の脱派閥も中途半端に 麻生氏は派閥主導にグチも
そして2001年、脱派閥を掲げた首相が誕生した。小泉純一郎首相だ。小泉首相は総裁選で脱派閥を掲げて国民からの大きな支持を受け、橋本元首相や亀井静香氏を破って当選した。

しかし、その小泉首相をもってしても、脱派閥は十分に進められなかった。組閣において、各派閥からの推薦を受けなかったことは国民から評価されたが、小泉首相が直近に迫った参院選の自民党候補者は、派閥を離脱して臨むべきだと表明したところ、橋本派の幹部で参院の実力者である青木参院幹事長が猛反発。

青木氏は、説得に来た党政治制度改革本部長に対し、現実的に無理だとして拒否。食い下がられると「衆議院と同じ目で参議院を見てもらっては困る。そんなに言うなら、衆議院が先行して派閥解消すればいいじゃないか」と一喝した。
さらに、小泉首相は総裁選で勝利する上で、会長を務めていた森派のバックアップを受けていたが、入れ代わりで首相を退任した森氏が会長に復帰したのだ。森氏は「小泉総理の言う派閥解消という理想のため協力しなければならないが、現実の目の前にある参院選挙は無に出来ない。理想に近づけるため、政治基盤を安定させることも重要だ」と派閥維持に動いた。

小泉政権に続いて、第1次安倍政権が誕生した際には、国民的にも人気のあった安倍氏を主要派閥が支持する流れができ、対抗馬として出馬した麻生太郎氏は「まだ政策発表が揃う前から何となく流れが決まったかのようで、派閥の復活みたいな話だ。何のために派閥解消をやったのかよくわからない」と不満を示していた。

その後、民主党政権時代を経て政権に復帰した自民党は、初の無派閥出身首相、菅義偉政権を誕生させるなどしてきたが、岸田政権では自身と麻生氏、茂木氏という派閥のトップを中心とした政権運営が続いている。
派閥の機能「数は力 力は金」の説得力と弊害 改革のポイントは
こう振り返ると派閥は、自民党にとっていかに解消が難しい存在かということがわかる。渡海氏も「派閥というのはあっていいものだ。人間集まればグループができて、いろんな情報交換をしたり、例えば志を同じくして、この国の未来を担う人材を支えていこうという風な形で派閥ができることは健全であり一向に問題無い」と語っている。つまり今回の改革で自民党の方から派閥解消に踏み切ることはないとみよさそうだ。
では、どんな改革が考えられるのか。派閥の機能とは何かというと、大まかに言って「議員交流」「政策勉強」「首相候補者の支援」「ポストの配分」「お金の配分」の5つに分けられる。
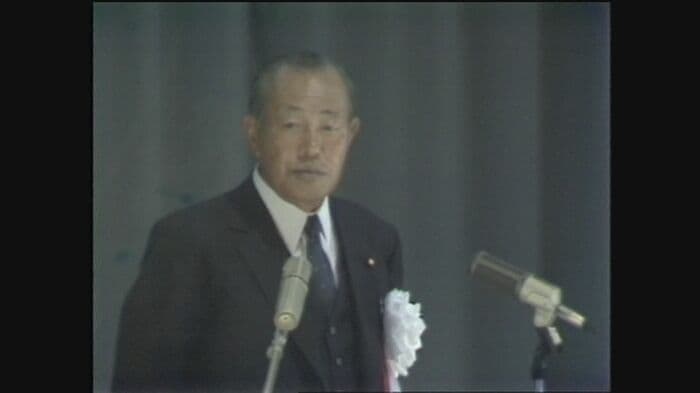
このうち議員交流と政策勉強は、派閥でなく議員連盟などでも代替可能なので、残り3つが中核機能といえ、その改革がポイントとなる。ここで思い出すのが、田中角栄元首相の「政治は数、数は力、力は金」という言葉だ。これこそ派閥の機能に通じるものがある。総理大臣を生み出すための力は仲間の議員の数であり、そのためにポストという権力と、政治資金を融通するための装置が派閥だと言えるのではないか。
その派閥の機能から、金とポスト配分の機能を制限して、政策勉強会の形に近づけることは今回の改革案として有力な選択肢とみられる。ただ、方向性を打ち出すだけであれば1994~95年のように逆バネが自然に働く可能性は高そうだ。だとすれば、それを防ぐのは、法律で網をかけることと、国民の監視の目ということになり、パーティーの制限強化や政治団体間の献金の規制など、政治資金規正法改正も視野に入ってくる。
名門派閥「宏池会」のトップを務め、他派閥の支援で首相に上り詰め、今も派閥の支持が政権の生命線となっている岸田首相が、検察の捜査を踏まえてどんな改革案を提示し、どんな法改正を打ち出すのか。2024年前半の大きな注目点となりそうだ。
【フジテレビ政治部デスク 髙田圭太】






