看護師など長時間の夜勤がある職場で「120分間(2時間)の仮眠」をする時に、「1回でまとめてとる」よりも「90分間と30分間に分けてとる」方が、早朝の眠気を抑え疲労感の低減効果が優れている…。このような研究結果を広島大学大学院の折山早苗教授が10月26日に発表した。
3つの条件で疲労感などを比較
折山教授は今回、これまでに収集した実験データを再分析し、16時間夜勤を伴う二交代制勤務の看護師の一般的な夜勤の時間帯を想定し、以下の3つの条件で睡眠状態、心拍変動、眠気や疲労感などを比較した。
・120分間の仮眠(午後10時~午前0時)をまとめてとる
・90分間(午後10時30分~午前0時)と30分間(午前2時30~午前3時)に分けて仮眠をとる
・仮眠をとらない
その結果、仮眠をとった時の睡眠状態と仮眠直後の体温、眠気、疲労感、計算数の相関関係から、総睡眠時間が長いと「120分間の仮眠」は疲労感が増加した。
「30分間の仮眠」は眠気が増加することが明らかになり、「90分間の仮眠」は睡眠潜時(静止期時間帯の始まりから入眠までの時間)が短いと、体温が上昇し、眠気や疲労感も増加することが示されたという。
そのうえで、「夜間睡眠が限られる長時間の夜勤状況下においては、1回の仮眠をとるよりも2回に分けて仮眠をとる方が、眠気や疲労感の低減に繋がることが示された」としている。

今回の研究では、2回に分けて仮眠をとる方が眠気や疲労感の低減に繋がることが明らかになったのだが、この理由としては、どのようなことが考えられるのか? また、今回の研究結果はどのようなことに活かされるのか?
広島大学大学院の折山早苗教授に聞いた。
「夜勤時にとる仮眠の効果が注目されている」
――看護師の「長時間の夜勤」の現状は?
看護師は診療報酬の制度上、「三交代制」が基本とされてきましたが、1992年の通達により、「なるべく三交代制であることが望ましいが、保険医療機関の実情に応じて二交代制の勤務形態があっても差し支えない」とされ、事実上、「二交代制」が容認された結果、これ以降、「二交代制」を導入する病院が増えてきています。
最も長時間の夜勤は16時間とされ、看護師の疲労や眠気の増加による医療安全に対するリスクの増大が危惧されています。
こうした状況の中、夜勤時にとる仮眠の効果が注目されています。しかし、長時間夜勤の眠気や疲労を軽減し、作業能力を維持するための有効な仮眠のとり方は十分に明らかになっていません。

――今回の研究で「長時間の夜勤」の“仮眠”に注目した理由は?
これまでの仮眠の研究では、昼間にとる15分間の仮眠など短時間仮眠の有効性が明らかにされています。
また、夜間の仮眠については「120分間以上の仮眠」が推奨されています。しかし、看護師の勤務は、交代で休憩に入るため、仮眠の取得時刻や時間は一様ではありません。
患者の急変や頻回のナースコールによって、ほとんど仮眠がとれない場合もありますし、120分間の仮眠の取得時刻によっては、長時間の夜勤終了時まで効果を持続することは難しい場合もあります。
そこで今回、2011年に収集した「120分仮眠」と、2014年に収集した「90分間と30分間の仮眠」、2018年に収集した「仮眠をとらなかった」データを再分析し、仮眠による眠気や疲労感の変化を明らかにしました。
2回に分けてとった方がいい理由
――今回の研究で仮眠の時間を120分間(2時間)に設定した理由は?
通常、眠りには「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」の2種類があり、約90分間のサイクルで繰り返されています。
眠りにつくまでの時間を考え、十分に1サイクルの睡眠効果を得られるよう、仮眠時間として120分間をまとめてとる条件と、1サイクルの90分間とノンレム睡眠の睡眠段階3の「徐波睡眠(深睡眠)」に到達する前の30分間を組み合わせた条件を設定しました。
――仮眠の条件に「60分+60分」を入れなかった理由は?
60分間は「ノンレム睡眠」の「徐波睡眠(深睡眠)」の時に覚醒することから、睡眠の効果が十分に得られないばかりか、覚醒時の眠気の残存が課題となるため、60分間を設定しませんでした。
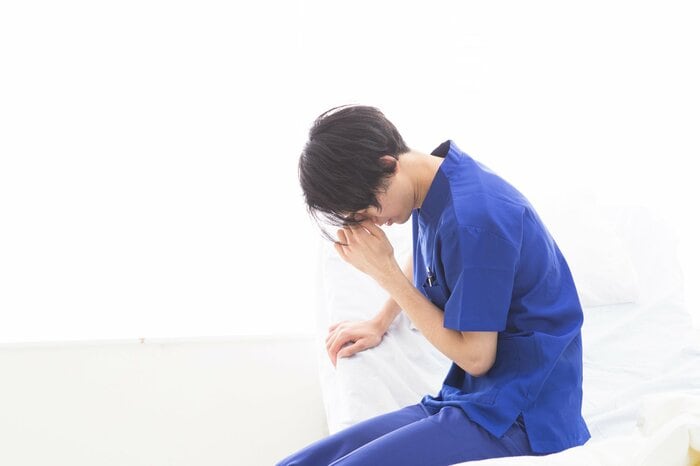
――「2回に分けて仮眠をとる方が眠気や疲労感の低減に繋がる」。この理由としては、どのようなことが考えられる?
仮眠を120分間まとめてとった場合には、仮眠後4時間の効果しか期待できません。
つまり、午後10時~午前0時に仮眠をとった場合には、午前4時ごろまで効果がありますが、それ以降は仮眠をとらない場合と同じになってしまいます。
2回に分けて仮眠をとる場合には、「90分間の仮眠」の効果に加えて、「30分(午前2時30分~午前3時)の仮眠」の効果として、午前6時まで眠気の抑制効果と他の条件よりも朝方の疲労低減が示されました。
こうしたことから、「30分間の仮眠」の眠気の低減効果は3時間可能と考えますし、疲労感の低減については、さらに持続すると思います。
「看護師の離職防止にもつなげたい」
――今回の研究結果をどのように受け止めている?
この結果が、そのまま臨床現場に適用できるとは考えていませんが、仮眠を分けてとることで朝方の眠気や疲労感を低減する効果が得られる可能性が明らかになりました。
今回の研究では、計算など複雑な作業については効果が見られなかったことから、目的に合わせて仮眠の組み合わせを工夫する必要があると考えています。
――研究結果をどのようなことに活かしたいと考えている?
今後はこの結果をエビデンスとし、これまでに収集した16時間夜勤に従事する看護師を対象とした臨床データを解析し、臨床現場で適用できる仮眠のとり方を明らかにしたいと考えています。
また、仮眠環境の整備や夜勤時の眠気や疲労感などの負担を理由に離職する「看護師の離職防止」にもつなげたいと考えています。
さらに将来的には、看護師だけでなく、夜行バスのドライバーや交代制勤務に従事する工場で働く労働者などを対象に仮眠のとり方を開発することで、労働者の心身の負担軽減と安全安心な職場環境の醸成にも寄与したいと考えています。

看護師など長時間の夜勤がある職場における、より効果的な「仮眠のとり方」を明らかにした今回の研究。1回でまとめてとる方が、疲れがとれるイメージがあっただけに結果は意外と感じた人も多いかもしれない。






