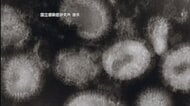「5月の訪日外国人客は、前年同月比99.9%減の1700人」
インバウンドが消滅した旅行業界は、都内感染者数の連日100人超えでさらなる苦境に立たされそうだ。コロナと共生する社会での新しい旅のかたちとは?「GoToキャンペーン」は起死回生の起爆剤となるのか?星野リゾート代表の星野佳路氏に聞いた。

インバウンド蒸発でも旅行市場の減少は7%
――コロナによって日本の観光産業は大打撃を受けているのですが、まず完全に消滅してしまった訪日外国人3千万人によるインバウンド景気をどうするかです。
星野氏:
インバウンドは治療薬やワクチンが完成するまで、戻ってこないと私は思っています。私は91年に軽井沢の実家の旅館を継いだ4代目ですが、インバウンドが伸びてきたのはこの20年で、それ以前はほとんどありませんでした。いま旅行市場は28兆円ですが、内訳は国内旅行が22兆円、海外旅行が1.2兆円、インバウンドは4.8兆円です。海外旅行は現地で使っているお金も入れると3兆円ですね。

インバウンドの4.8兆円は確かに無くなりましたが、コロナの影響で海外旅行に行くことはできませんから、おそらく3兆円は国内に戻ってくるだろうと予測しています。そうなると旅行市場全体ではマイナス1.8兆円です。28兆円の中の1.8兆円は、たったの7%。インバウンドとアウトバウンド(海外旅行)が同時に無くなっても、減少幅は7%しかないのです。つまり、勝負所は国内旅行市場ですね。

台湾では海外旅行に行く観光客の比率が実は大きいのですが、コロナの影響によってこの人たちがすべて台湾島内に行き先を移したので、台湾にある星野リゾートの「星のやグーグァン」は台湾の方のお客様がたくさんいらしてくださっています。
「地元」を楽しむマイクロツーリズム
――なるほど。つまり国内旅行市場をどう活性化させるかがポイントですね。
星野氏:
国内旅行を伸ばすには「マイクロツーリズム=小さな旅行」と「休暇の分散化」が大事です。まずマイクロツーリズムですが、いまコロナは自粛から緩和となっているものの、今後も東京では感染が拡大するので、地方に旅行出来ない時期がまた来ると思います。マイクロツーリズムは自宅から車で30分から1時間で行ける範囲での観光です。東京のホテルや観光地の生き残りのためにも、関東圏での旅行の需要はもっと作らなければいけないと思います。
――マイクロツーリズムは地方でも?
星野氏:
私は県外の移動を全国一律に規制する必要は無かったと思っています。たとえば島根県の玉造温泉はマイクロツーリズム商圏に鳥取県の米子市があります。しかし県境を越えた移動になるので9割需要を下げてしまいました。
マイクロツーリズム商圏をもっと意識して、きめの細かい県境の自粛のあり方を考えれば、第二波、第三波の自粛期間に4割減で留まるかもしれません。こういうことも含めて自治体と国には、規制・自粛のあり方の改善を考えて欲しいと考えております。

全国を5地区に分けてGWをずらして休む
――休暇の分散化についてはどう考えるべきですか?
星野氏:
私が休暇の分散化を提言し始めたのは2004年です。当時私は軽井沢の実家で旅館をやっていましたが、年間100日が黒字で265日は赤字でした。265日が赤字となる理由は、同じ日に皆が休みを取っているからです。
観光産業の雇用者は75%が非正規雇用です。なぜならGWは満室で価格は普段の2倍以上ですが、翌週になるとお客様が減るので、正規雇用のスタッフは必要なくなります。
観光産業の生産性を考えるとき、22兆円の巨大需要を持っているのは日本の強みです。この巨大需要を分散化すれば、価格が下がりますし、道路の渋滞も減り、観光地の混雑も緩和されます。
観光事業者にとっても年間を通して利益が出るようになりますから、結果的に正規雇用も増えます。つまり、観光産業の様々な課題が一気に解決していくことが、大きなポイントなのです。
――休暇の分散化は具体的にどう進めればいいですか?
星野氏:
フランスでは大型連休を地域別に取得しています。日本でも全国を5地域ブロックに分けて、GWの日程をずらして取得していけば、4月の最終週から5月いっぱいまでがGWになります。そうなれば価格は下がりますし、混雑は緩和されます。観光事業者にとってはGWが1ヶ月半続くことになるので、適度に需要がある状態が続くと思われます。さらに秋のシルバーウィーク、旧正月の後に春休みがあり、その後5地区のGW、7,8月の夏休みと続くと、年間を通して需要が分散しますね。

祝日が多い日本は同時休暇が定着
――学校や会社では祝日に合わせて休みを取得するので、これをどうするかですね。
星野氏:
GWの祝日をみると、わざわざ連休にするために祝日を意図的に作ったものもあります。4月29日はかつて昭和天皇の誕生日でしたが、その後みどりの日になり、いまは昭和の日として、みどりの日は祝日と祝日の間にあった5月4日に移動させました。日本は祝日が先進国で一番多いため、日本では全国同時に休むという習慣が定着してしまったのです。
――確かに日本の祝日は15日と、アメリカ(10日)やイギリス(8日)、ドイツ(9日)に比べて多いですね。休暇をたっぷりとっているイメージのフランスでも11日です。
星野氏:
海外の先進国は休まない祝日も多いですし、祝日自体が少ないので有休を取りやすいというのもあります。日本では最近有休を意識的に取得しようとしていますが、子どもの休みが重ならなくて、お父さんお母さんだけが家でぽつんといるという「有休取得のための有休」も多いです。
諸外国のように全員で休む祝日が少なくて、自由に有休を取れるのが一番理想的です。子どもの休みや事情に合わせて有休を取る人もいれば、子どもが独立した人は有休を自由に取って夫婦で旅行する。そうなれば、自然と休暇が分散していきます。
休暇分散化の議論をすると「祝日は日本の文化だから止められない」という話になりますが、だからこそ大型連休そのものを地域別にしたらどうかということです。
夏の「Go Toキャンペーン」は密になる
――国が進めている「GoToキャンペーン」についてはどう思いますか?
星野氏:
目的をどこに置くかだと思います。観光市場を元に戻すためのキャンペーンだとすると、夏休みに一気に盛り上げようとなりますが、やはりコロナの性質からいうと盛り上げて人を集めて、密にすることは向いていません。
そう考えると第二波や第三波が来たときに、どうやって9割減の売り上げを3.4割減に抑えるかという使い道を考えた方がいいと思います。それが、やはりマイクロツーリズムなんです。たとえ首都圏や関西圏から移動できなくなっても、マイクロツーリズム商圏ごとに県境を開けて予算を分配すれば、自粛期においても4割減ですむ。そのための予算として使うのがいいのではないかと思います。
――コロナでテレワークが増えていますが、小泉環境大臣は観光地で働く=ワーケーションを提唱していますね。
星野氏:
祝日がぽつんと週の真ん中にある時は観光事業に影響が無かったのですが、今後企業内でテレワークが増えて、木曜日祝日だけど金曜日は観光地でテレワークすれば土日まで連休になるという効果が期待出来ますね。今後は観光地側がワーケーションに向けた環境整備をしていかなければいけないと思っています。ただ、何週間、何ヶ月間も観光地に移動して、仕事をするというタイプの職種は限られるかなと思います。
――最後に星野代表にとっての旅とは何ですか?
星野氏:
僕にとって旅はスキーなんですよ(笑)。年間60日滑るのを人生の目標にしているんです。自分で旅をするのは、スキー以外ほとんど無いですけどね。毎年3月は北海道に、7,8月はニュージーランドにいましたが、現地ではテレワークをやっていました。
テレワークは僕にとって10年前からやっていたのですが、ここにきて皆さん始めていらっしゃるので、観光地にとってはポテンシャルになると思いますね。
――ありがとうございました。
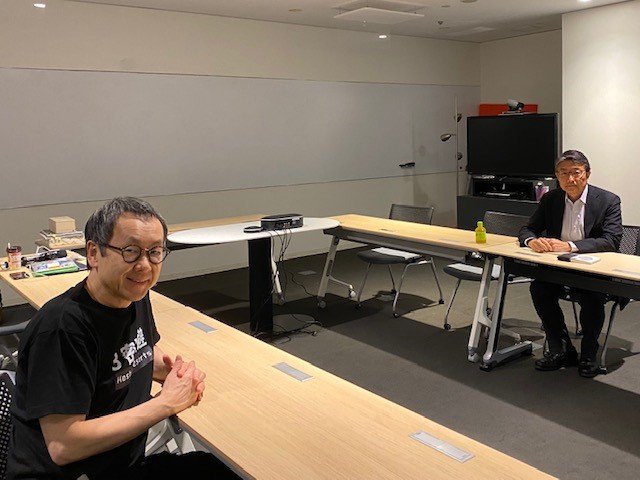
【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】