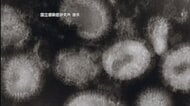有効成分は3分の1、3週間あけて2回
「はい、この位置に打つからね」 都内の5歳から11歳までの子どもを対象にしたワクチン接種が、2月26日、足立区から始まった。
5歳から11歳を対象とした接種は、ファイザー製の子ども用ワクチンを使用。有効成分の量は12歳以上の3分の1で、3週間の間隔をあけて2回接種する。 接種は12歳以上のような「努力義務」にはなっておらず、接種には保護者の同意と立ち会いが必要だ。
“都内初”接種 必要性を考えて
「痛くなかった。最初はちょっと怖かったけど。元気にドッチボールしたい」都内で初めて接種を受けた8歳の男の子は、接種前後とも冷静な様子。 「基礎疾患があるので、早く打ててよかったなと思っています」男の子の母は「副反応については自分なりに調べて、かかりつけの先生にお話をして、ワクチンの有効性、必要性を考えて打とうと思った」と“決断”について話した。

先生が同じだったので安心して
「下の子が少しぜんそく気味ですので、かかったときに重症化するであろう、と先生と色々お話しましたので、それだったら受けたほうがいいと思いますし、私も受けましたので」こう話すのは11歳女児と10歳男児の父。
「特に怖いとかはなかったけど、イ ンフルエンザの時と同じように先生が同じだったので、安心して打てました 」(11歳女児) 「学校の友達とかにうつさないように、注射できて良かったと思います」(10歳男児)

しっかりと話す子供たちについて、都内初の5歳から11歳の接種をおこなった足立区医師会副会長で千住中央診療所の山本亘医師はこう話す。 「ワクチンの必要性っていうのは、子供たちも、よく、もう知っているんです」 そのうえで実際の「都内初接種」後に気づいたこととは・・・。
大人の2~3倍の時間がかかる

「大人とちょっと違うのは、時間がとてもかかります。だいたい私の今日の印象だとやっぱり(大人の)2倍から3倍の時間がかかります」大人より時間をかけて、しっかり話をして、緊張を和らげてからでないとうまくいかないので、とのこと。
5~6歳が“大変” 他ワクチンとの間隔も注意
「実際に大変になるのは、たぶん5歳から6歳のこどもたちの、就学されてない子供たちの方が大変だと思います」就学前の子供たちには、接種自体の難しさの他に、接種場所で感染しないように、予防対策にも細心の注意を払わなければならない、と話す。
また他のワクチンとの間隔も注意が必要で、「基本的には生ワクチンに関してはだいたい3週間から4週間をあけてほしい。不活化ワクチンの場合は2週間でよろしいかと思います」と話した。

発熱には「2つある」 薬の準備を
「発熱っていうのは2つあると思うんですね」山本医師によると、接種後6時間以内の発熱は、体内にウイルスが隠れていて、抗体が一気に上がることによる反応だという。一方、6時間後からの発熱は、基本的には抗体が上がったことによるものだという。
「一番心配なのは、やっぱりアナフィラキシーとかのアレルギーなんですけども」山本医師は、接種後、発熱した時のために、解熱剤を用意しておくことを勧めている。さらに、ぜんそく・アレルギーといった疾患がある人は、かかりつけ医と相談して、必要な薬を準備するようアドバイスする。
ワクチンは後遺症の予防にも
「小さい子たちに、是非、打ってもらわなきゃいけないワクチンだと思っています」山本医師は、ワクチンは重症化だけでなく後遺症の予防にもなる、と話したうえで、教育の機会や子供たち同士のふれあいを作ってもらうためにもワクチン接種を進めるべき、との考えを示した。
ワクチン供給量はそんなに心配はないが
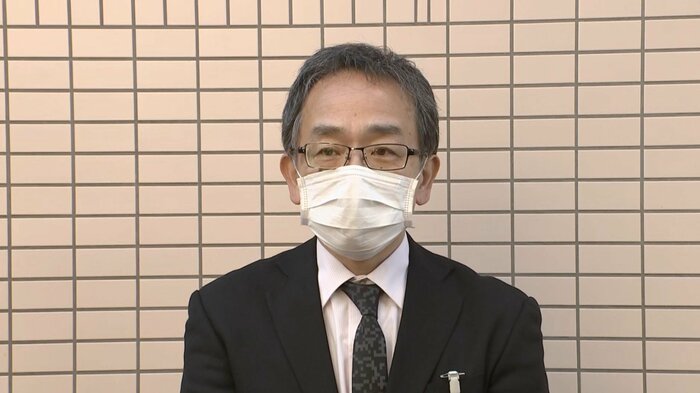
「ワクチンの供給量に関してはそんなに心配はないのかな、と思っています。とにかく課題として一番大きいのは、接種に関する不安をいかに解消していくかって言うことになるかと思います」足立区には接種対象となる子供が3万6000人いるという。足立区のワクチン接種担当部の絵野沢秀雄部長は、対象者8割分のワクチンが、4月25日の週までに届くので、不安なく接種を受けてもらえるよう丁寧な説明を重ねていく考えを強調した。
(フジテレビ社会部・都庁担当 小川美那)